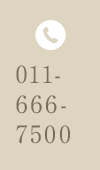舌を噛む癖はストレスが原因?簡単セルフチェックと正しい治し方

こんにちは。医療法人 札幌矯正歯科 宮の沢エミル矯正歯科の理事長の尾立卓弥です。札幌で矯正歯科を検討中の方は、ぜひ医療法人 札幌矯正歯科 宮の沢エミル矯正歯科でご相談ください。こんにちは。医療法人 札幌矯正歯科 宮の沢エミル矯正歯科、理事長の尾立卓弥です。食事中や無意識に舌を噛んでしまう癖、実はストレスだけが原因ではありません。歯並びや噛み合わせ、疲れによる舌の変化など、身体的な要因も大きく関わっています。この記事では、ご自身の原因を探るセルフチェックから、自分でできる簡単な治し方、歯科医院での専門的な治療法までを詳しく解説します。癖を正しく理解し、つらい悩みから解放されましょう。
1. もしかしてあなたも?舌を噛む癖の簡単セルフチェック
食事中にうっかり舌を噛んでしまう経験は誰にでもあるでしょう。しかし、「最近よく噛むな」「気づいたら舌に歯形がついている」という場合、それは単なる偶然ではなく、無意識の「癖」が原因かもしれません。舌を噛む癖は、自分ではなかなか気づきにくいものです。まずは、ご自身の状態を客観的に把握するために、簡単なセルフチェックを行ってみましょう。
1.1 あなたの舌の状態をチェック
鏡を用意して、舌をリラックスさせた状態でじっくりと観察してみてください。特に舌の側面や先端に注目しましょう。
| チェック項目 | 当てはまる場合に考えられること |
|---|---|
| 舌の側面(両脇)に、ギザギザとした波のような歯の跡がついている | 最も分かりやすいサインの一つです。無意識のうちに舌を歯に強く押し付けていたり、睡眠中に食いしばったりしている可能性があります。この歯形は「舌圧痕(ぜつあっこん)」と呼ばれます。 |
| 舌の同じような場所に、繰り返し口内炎ができる、または白くなっている | 特定の箇所を頻繁に噛んでしまうことで、粘膜が傷つき炎症を起こしている状態です。治りにくい口内炎は、慢性的な刺激の証拠かもしれません。 |
| 舌の先や側面が部分的に赤くなっていたり、ヒリヒリとした痛みを感じたりする | 物理的な刺激が続くことで、舌の表面が炎症を起こしている可能性があります。食べ物や飲み物がしみることがあります。 |
1.2 日常の行動や感覚でチェック
次に、普段の生活の中での行動や身体の感覚を振り返ってみましょう。舌を噛む癖は、口の中だけでなく全身の不調と関連していることもあります。
| チェック項目 | 当てはまる場合に考えられること |
|---|---|
| 朝、目覚めたときに舌に痛みや違和感、顎のだるさを感じる | 睡眠中に歯ぎしりや食いしばりをして、一緒に舌を噛んでいる可能性があります。質の良い睡眠が取れていないサインかもしれません。 |
| 食事の際に、以前より頻繁に舌や頬の内側を噛むようになった | 疲れや体重の増加によって舌がむくんでいたり、噛み合わせが変化していたりするサインです。加齢による筋力の低下も一因です。 |
| パソコン作業中やスマートフォンの操作中など、何かに集中しているときに、ふと気づくと上下の歯が接触していたり、舌を噛んでいたりする | これは「歯列接触癖(TCH)」と呼ばれる癖の可能性があります。本来、リラックスしているとき、上下の歯の間には隙間がありますが、無意識に接触させることで舌を噛むリスクが高まります。 |
| 原因不明の肩こりや頭痛に悩まされている | 口周りの筋肉の過度な緊張は、首や肩の筋肉にも影響を及ぼします。舌を噛む背景にある食いしばりやTCHが、全身の不調を引き起こしているケースも少なくありません。 |
1.3 チェック結果の評価
いかがでしたか?もし、これらの項目に1つでも当てはまるものがあれば、あなたは無意識に舌を噛む癖を持っている可能性が高いと言えます。特に複数の項目に心当たりがある方は、その癖がすでに慢性化し、お口や身体に何らかの悪影響を及ぼし始めているかもしれません。
「ただの癖だから」と軽視していると、繰り返す痛みや不快感だけでなく、顎関節症など、より深刻な問題につながることもあります。次の章では、なぜこのような癖が起きてしまうのか、その原因をさらに詳しく探っていきましょう。
2. 舌を噛む癖の主な原因はストレスだけじゃない
ふとした瞬間に「ガリッ」と舌を噛んでしまうと、痛いだけでなく「何か悪い原因があるのでは?」と不安になりますよね。多くの方が「ストレスが原因」と考えがちですが、実は舌を噛む癖の背景には、精神的なものから身体的なもの、さらには特定の病気のサインまで、さまざまな要因が隠されています。ご自身の状況と照らし合わせながら、本当の原因を探っていきましょう。
2.1 精神的な原因 ストレスや不安
舌を噛む癖の最も代表的な原因として挙げられるのが、精神的なストレスや不安です。仕事や人間関係の悩み、環境の変化などによって強いストレスを感じると、体は無意識に緊張状態になります。この緊張が、就寝中の歯ぎしりや日中の食いしばりとして現れ、その際に舌を巻き込んで噛んでしまうのです。
特に、何かに集中している時や緊張している場面で、気づかないうちに歯をグッと食いしばっていることはありませんか?ストレスや不安による無意識の筋肉の緊張が、顎や舌の正常な動きを妨げ、舌を噛む直接的な引き金になることは少なくありません。まずはご自身の心の状態に目を向けてみることが大切です。
2.2 身体的な原因 歯並びや噛み合わせ
精神的な問題だけでなく、お口の中の物理的な環境、つまり「歯並び」や「噛み合わせ」が原因となっているケースも非常に多く見られます。具体的には、以下のような状態が挙げられます。
- 歯並びがガタガタで、舌が収まるスペースが狭い
- 受け口や出っ歯などで、上下の歯の噛み合わせがずれている
- 加齢により歯がすり減ったり、位置がずれたりしてきた
- 治療した被せ物や入れ歯の高さが合っていない
これらの状態では、顎を動かした際に歯が舌に当たりやすくなります。歯並びや噛み合わせの乱れが、物理的に舌を噛みやすい環境を作り出してしまっているのです。特に、急に舌を噛む頻度が増えた場合は、詰め物や被せ物の不具合も考えられるため、一度歯科医院でチェックしてもらうと良いでしょう。
2.2.1 疲れや肥満による舌の変化
意外に思われるかもしれませんが、体調の変化も舌を噛む原因になります。特に「疲れ」と「肥満」は舌の状態に影響を与えます。
疲労が蓄積すると、全身の筋肉のコントロールが低下します。これは顎や舌の筋肉も例外ではなく、普段通りに動かせたつもりが、わずかなズレを生んで舌を噛んでしまうのです。また、疲労や塩分の摂りすぎによって体がむくむと、舌も同様にむくんで厚みが増し、口腔内で歯に当たりやすくなります。
さらに、体重が増加すると舌にも脂肪がつき、肥大化することがあります。舌が大きくなることで口腔内のスペースが相対的に狭くなり、舌を噛むリスクが高まるのです。
2.2.2 歯列接触癖(TCH)という無意識の癖
「TCH(Tooth Contacting Habit)」という言葉を聞いたことはありますか?これは「歯列接触癖」のことで、リラックスしているべき時に、無意識に上下の歯を接触させ続けてしまう癖を指します。
本来、人の上下の歯が接触するのは、食事や会話の時などごくわずかな時間です。何もしていない時は、唇を閉じていても歯と歯の間にはわずかな隙間(安静空隙)があるのが正常な状態です。しかし、TCHがあると、パソコン作業やスマホ操作中、家事の最中など、何かに集中している時に持続的に歯を接触させてしまいます。これにより顎周りの筋肉が常に緊張し、疲労が蓄積。結果として、食事などの際に顎の精密なコントロールが効かなくなり、舌を噛んでしまうのです。
TCHはご自身では気づきにくい癖ですが、顎のだるさや肩こり、頭痛の原因にもなります。詳しくは、日本顎関節学会のほーむpほーむぺホームページも参考にしてみてください。
2.3 注意すべき病気の可能性
頻繁に舌を噛む場合、背景に何らかの病気が隠れている可能性もゼロではありません。特に、以下のような症状が伴う場合は注意が必要です。自己判断せずに、速やかに専門の医療機関を受診してください。
舌を噛む以外にもろれつが回らない、手足のしびれ、めまいといった症状がある場合は、脳梗塞など緊急を要する病気の可能性も考えられます。迷わず救急車を呼ぶか、脳神経外科を受診しましょう。
| 考えられる病気 | 主な特徴・併発する症状 | 相談すべき診療科 |
|---|---|---|
| 顎関節症 | 口を開けると顎が痛い・音が鳴る、口が大きく開けられない。顎の動きが不規則になり舌を噛みやすい。 | 歯科、口腔外科 |
| 脳梗塞・脳腫瘍など | 突然ろれつが回らなくなる、片側の手足のしびれ・麻痺、激しい頭痛、めまい。舌の動きをうまく制御できなくなる。 | 脳神経外科、神経内科 |
| 睡眠時無呼吸症候群 | 睡眠中の大きないびき、呼吸が止まる。気道を確保しようとして舌の位置が不安定になり、噛んでしまうことがある。 | 呼吸器内科、耳鼻咽喉科、睡眠外来 |
2.4 子どもに多い舌を噛む癖の原因
お子さんが頻繁に舌を噛んでいると、親御さんとしては心配になりますよね。子どもの場合、大人とは少し異なる原因が考えられます。
- 歯の生え変わり: 乳歯から永久歯に生え変わる時期は、歯並びが一時的に不安定になり、噛み合わせが変化するため、舌を噛みやすくなります。
- 顎の成長: 顎の骨が成長途中であるため、歯の生えるスピードとのバランスが取れず、一時的に噛みやすくなることがあります。
- 口腔習癖(こうくうしゅうへき): 指しゃぶりや口呼吸、舌を前に突き出すような癖があると、舌が常に低い位置(低位舌)にあったり、歯並びに影響を与えたりして、結果的に舌を噛む原因になります。
多くは成長過程における一時的なものですが、癖が長期間続いたり、歯並びへの影響が気になったりする場合は、一度かかりつけの小児歯科や矯正歯科に相談すると安心です。
3. 【自分でできる】舌を噛む癖の治し方 セルフケア編
舌を噛んでしまう癖は、多くの場合、日々のちょっとした意識や工夫で改善が期待できます。専門家の治療を受ける前に、まずはご自身でできるセルフケアから始めてみましょう。ここでは、今日から実践できる3つの効果的な治し方をご紹介します。
3.1 まずはストレスを解消する
舌を噛む癖の背景には、精神的なストレスが大きく関わっていることがあります。ストレスを感じると、無意識のうちに歯を食いしばったり、睡眠中に歯ぎしりをしたりすることが増え、その結果として舌を噛んでしまうのです。心と体は密接につながっています。まずは心身をリラックスさせ、緊張をほぐすことから始めましょう。
具体的なストレス解消法には、次のようなものがあります。
- 深呼吸や瞑想: 意識的にゆっくりと深い呼吸をすることで、副交感神経が優位になりリラックスできます。1日数分でも効果的です。
- 適度な運動: ウォーキングやヨガ、ストレッチなど、心地よいと感じる程度の運動は、気分転換になりストレスホルモンを減少させます。
- 趣味に没頭する時間を作る: 読書や音楽鑑賞、映画など、自分の好きなことに集中する時間は、ストレスから意識をそらすのに役立ちます。
- 十分な睡眠: 質の良い睡眠は、心身の疲労回復に不可欠です。寝る前のスマートフォン操作を控える、リラックスできるアロマを焚くなど、睡眠環境を整えましょう。
これらの方法は、自律神経のバランスを整え、無意識の食いしばりを減らす助けとなります。東京都保健医療局でも、こころの健康を保つための情報が提供されていますので、参考にしてみてください。
3.2 舌の正しい位置を意識するトレーニング
舌が本来あるべき位置からずれている「低位舌(ていいぜつ)」の状態だと、歯の間に舌が入り込みやすくなり、噛んでしまう原因になります。舌の正しい位置は「スポットポジション」と呼ばれ、舌先が上の前歯のすぐ後ろにある歯茎の膨らんだ部分に軽く触れている状態です。このとき、舌全体は上顎に自然に吸い付くように収まり、上下の歯はわずかに離れています。
この正しい位置を体に覚えさせるための簡単なトレーニング(口腔筋機能療法:MFT)をご紹介します。継続することで、無意識の状態でも舌が正しい位置に収まるようになります。
| トレーニング名 | やり方 | 回数の目安 |
|---|---|---|
| スポットポジションの確認 | 舌先を「スポットポジション」(上の前歯のすぐ後ろの膨らみ)に置き、そのまま5秒間キープします。歯に舌が触れないように意識しましょう。 | 1日に10回程度 |
| ポッピング(舌打ち) | 舌全体を上顎に吸い付け、口を大きく開けて「ポンッ!」と強く音を鳴らします。舌を持ち上げる筋肉が鍛えられます。 | 1日15回程度 |
| 舌回し運動 | 口を閉じた状態で、舌先で歯茎の外側をゆっくりとなぞるように大きく回します。右回りと左回りを均等に行いましょう。 | 右回り20回、左回り20回を1セットとして1日2セット |
これらのトレーニングは、テレビを見ながら、あるいは仕事の合間など、気づいた時に行う習慣をつけることが大切です。舌の筋肉が鍛えられ、正しい位置が定着することで、舌を噛むリスクを大幅に減らすことができます。
3.3 市販のマウスピースを活用する方法
特に就寝中の歯ぎしりや食いしばりが原因で舌を噛んでしまう場合には、マウスピース(ナイトガード)の使用が有効です。歯科医院で作成するのが最も確実ですが、応急処置として市販のマウスピースを試してみる方法もあります。
市販のマウスピースは、お湯で温めて自分の歯形に合わせて成形するタイプが多く、ドラッグストアやオンラインで手軽に購入できます。歯と歯が直接当たるのを防ぎ、食いしばりの力を緩和することで、舌が巻き込まれるのを防ぐ効果が期待できます。
ただし、市販品を使用する際には注意が必要です。市販のマウスピースはあくまで応急処置的な対策であり、完全にフィットしないとかえって顎関節に負担をかけたり、噛み合わせを悪化させたりするリスクもゼロではありません。もし数日間使用してみて違和感や痛みを感じる場合は、すぐに使用を中止してください。
セルフケアで改善が見られない場合や、市販のマウスピースの使用に不安がある場合は、自己判断で続けずに、次のステップとして専門家へ相談することを強く推奨します。
4. セルフケアで治らないときに頼るべき専門家と治療法
ご自身での対策を続けても、舌を噛む頻度が減らない、あるいは傷が絶えず痛むという場合は、専門家の力を借りるタイミングです。セルフケアには限界があり、背景に専門的な治療が必要な原因が隠れている可能性も考えられます。自己判断で放置せず、専門家に相談することが根本的な解決への第一歩です。
4.1 舌を噛む癖は何科を受診すればいい?
舌を噛む原因は多岐にわたるため、どの診療科を受診すればよいか迷う方も多いでしょう。原因に応じて相談すべき専門家は異なります。まずはご自身の状況から、最も可能性の高い原因を考え、適切な診療科を選びましょう。
一般的には、まず歯科や口腔外科で口の中の物理的な問題がないかを確認するのがスムーズです。そこで原因が見つからなければ、精神的な要因を考えて心療内科などへの受診を検討するという流れがおすすめです。
| 考えられる主な原因 | 受診を検討すべき診療科 | 主な相談内容 |
|---|---|---|
| 歯並び・噛み合わせの問題 | 歯科・矯正歯科 | 歯並びによって舌のスペースが狭くなっていないか、噛み合わせがずれていないかなどを診察してもらいます。 |
| 合わない被せ物・入れ歯 | 歯科 | 古い詰め物や被せ物、入れ歯が合わなくなっていないかを確認し、必要であれば調整・作り直しを相談します。 |
| 顎関節症の疑い | 歯科・口腔外科 | 顎の痛みや口の開けにくさといった症状を伝え、顎の状態を診断してもらいます。 |
| ストレス・不安・うつ | 心療内科・精神科 | 歯科で身体的な原因が見つからなかった場合や、強いストレスを自覚している場合に、心理的なアプローチについて相談します。 |
4.2 歯科や口腔外科での主な治し方
歯科や口腔外科では、問診やレントゲン撮影、噛み合わせのチェックなどを行い、舌を噛む物理的な原因を特定します。その上で、原因に応じた治療法が選択されます。
4.2.1 オーダーメイドのマウスピース(スプリント)
歯科医院で最も一般的に行われる治療法の一つが、患者さん一人ひとりの歯型に合わせて作成するオーダーメイドのマウスピース(ナイトガードやスプリントとも呼ばれます)です。睡眠中や日中の無意識の食いしばりから歯や顎、そして舌を守ることを目的とします。
市販品と異なり、歯科医師の診断のもとで精密に作られるため、適合性が高く、外れにくいのが特徴です。主に次のような効果が期待できます。
- 睡眠中の歯ぎしりや食いしばりから舌を物理的に保護する
- 上下の歯が直接当たらないようにすることで、顎の関節や筋肉への負担を軽減する
- 正しい顎の位置へと誘導し、筋肉の緊張を和らげる
保険適用で作成できる場合も多いですが、症状や目的によっては自費診療となることもあります。費用や作成期間については、事前に歯科医院で確認しましょう。詳しくは日本歯科医師会の解説も参考になります。(参考: 日本歯科医師会 テーマパーク8020「歯ぎしり」)
4.2.2 噛み合わせの調整や歯列矯正
舌を噛む癖の根本的な原因が噛み合わせのズレや歯並びにある場合、それらを改善するための治療が行われます。
噛み合わせの調整
特定の歯が強く当たりすぎている場合や、被せ物の高さが合っていない場合に、歯をわずかに削ったり、被せ物を調整したりして、全体の噛み合わせのバランスを整えます。これにより、顎の動きがスムーズになり、舌を巻き込みにくくします。
歯列矯正
歯並びが乱れていることで舌が収まるスペースが狭くなっている、あるいは歯が内側に傾いていて舌を噛みやすいといったケースでは、歯列矯正が有効な選択肢となります。歯並びを整えることで、舌が本来あるべき正しい位置に自然と収まるようになり、癖の根本的な解決につながります。治療にはワイヤー矯正やマウスピース矯正など様々な方法があり、期間や費用も大きく異なるため、矯正歯科で専門的な診断を受けることが重要です。
4.3 心療内科や精神科でのアプローチ
歯科的な問題が見当たらないにもかかわらず、舌を噛む癖が治らない場合、その原因はストレスや不安といった精神的なものにある可能性が高いと考えられます。その際は、心療内科や精神科への相談が推奨されます。
心療内科などでは、癖そのものを直接治療するというよりは、癖を引き起こしている背景の心理的な問題にアプローチしていきます。主な治療法は以下の通りです。
- カウンセリング:専門のカウンセラーとの対話を通じて、自分では気づいていないストレスの原因を探ったり、ストレスへの対処法を学んだりします。物事の受け取り方や考え方の癖を修正していく「認知行動療法」などが有効な場合があります。
- 薬物療法:不安や緊張が非常に強い場合には、それらを和らげるための抗不安薬や、睡眠の質を改善するための睡眠導入剤などが処方されることがあります。ただし、これはあくまで対症療法であり、カウンセリングと並行して行われるのが一般的です。
- リラクゼーション法の指導:自律訓練法や筋弛緩法など、心身の緊張を自分でほぐすためのリラクゼーション法を学び、日常生活で実践することで、無意識の食いしばりや体の緊張を緩和します。
専門家と協力し、心身両面から原因を探り、適切な治療を受けることが、長年の悩みである舌を噛む癖を克服するための確実な道筋となるでしょう。
5. 舌を噛む癖を放置するリスクとは
「たかが癖だから」と、舌を噛む癖を軽く考えていませんか?しかし、この無意識の行動を放置すると、お口の中だけでなく全身にまで影響を及ぼす、さまざまな健康上のリスクを引き起こす可能性があります。ここでは、舌を噛む癖を放置することで起こりうる具体的な危険性について詳しく解説します。
5.1 繰り返す口内炎や痛み
舌を噛む癖で最も多くの人が悩まされるのが、繰り返す口内炎や傷による痛みです。舌の同じような場所を何度も噛んでしまうと、その部分の粘膜は常に傷ついた状態になります。傷口は口内炎になりやすく、一度できるとなかなか治りません。
この慢性的な口内炎は、食事の際にしみたり、会話の際に痛みを感じたりと、日常生活に直接的な不快感をもたらします。特に、熱いものや辛いもの、酸っぱいものなどを口にすると激痛が走ることもあります。さらに、傷口から細菌が入り込むと、炎症が悪化したり、感染症を引き起こしたりする可能性も否定できません。このような慢性的な痛みや不快感は、生活の質(QOL)を大きく低下させる深刻な問題です。
5.2 顎関節症や頭痛につながる可能性
舌を噛む癖は、顎(あご)の関節やその周辺の筋肉にも大きな負担をかけ、顎関節症の発症や悪化につながることがあります。舌を噛まないように無意識に顎の位置をずらしたり、不自然な噛み方を続けたりすることで、顎の関節や筋肉のバランスが崩れてしまうのです。
また、舌を噛む癖を持つ人は、無意識のうちに上下の歯を接触させる「歯列接触癖(TCH)」を併発しているケースも少なくありません。これにより、顎周りの筋肉(咬筋など)が常に緊張状態となり、顎の痛みや開口障害(口が開きにくい)、関節の雑音(カクカク、ジャリジャリという音)といった顎関節症の典型的な症状が現れます。
さらに、この顎周りの筋肉の緊張は、首や肩の筋肉にも連動して伝わります。その結果、慢性的な肩こりや、締め付けられるような痛みが特徴の緊張型頭痛を引き起こす原因にもなります。口の中の問題が、全身の不調へと発展してしまうのです。
| 症状の種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 顎の痛み | 口を開け閉めするとき、食事をするときに顎関節や頬のあたりが痛む。 |
| 開口障害 | 口がまっすぐ、または大きく開けられない(目安として指が縦に3本入らない)。 |
| 関節雑音 | 口を開け閉めする際に、耳の前あたりで「カクカク」「ジャリジャリ」といった音がする。 |
| 関連症状 | 頭痛、首や肩のこり、耳鳴り、めまいなど。 |
5.3 まれに舌がんの原因になることも
舌を噛む癖を放置する上で、最も注意しなければならないのが「舌がん」のリスクです。頻度は非常にまれですが、同じ場所を長期間にわたって噛み続けることによる慢性的な物理的刺激が、舌の粘膜細胞に異常を引き起こし、がん化する可能性が指摘されています。
これは、合わない入れ歯や尖った歯が舌に当たり続けることが舌がんの一因となるのと同じメカニズムです。傷ができては治り、また同じ場所に傷ができるというサイクルを繰り返すことで、細胞ががん化するリスクが高まるのです。
舌がんは初期段階では痛みがないことも多く、口内炎と見分けがつきにくいことがあります。しかし、進行すると食事や会話が困難になるだけでなく、命に関わる重大な病気です。もし、舌に2週間以上治らない口内炎やただれ、赤や白に変色した部分、硬いしこりなどがある場合は、絶対に放置せず、速やかに口腔外科や耳鼻咽喉科を受診してください。
舌がんの原因については、国立がん研究センターがん情報サービスのウェブサイトでも、慢性的な刺激がリスク要因の一つとして挙げられています。自己判断で「ただの口内炎だろう」と決めつけず、専門医の診断を仰ぐことが極めて重要です。
6. まとめ
舌を噛む癖は、ストレスだけでなく歯並びや無意識の癖など、様々な原因が考えられます。放置すると繰り返す口内炎や顎関節症につながるため注意が必要です。まずは舌の正しい位置を意識するなどのセルフケアを試し、改善しない場合は歯科や心療内科といった専門家へ相談しましょう。原因を正しく突き止め、ご自身に合った適切な対処法を見つけることが改善への第一歩です。
矯正治療のご相談をご希望の方は、下記のボタンよりお気軽にご予約ください。
この記事の監修者

尾立 卓弥(おだち たくや)
医療法人札幌矯正歯科 理事長
宮の沢エミル矯正歯科 院長
北海道札幌市の矯正専門クリニック「宮の沢エミル矯正歯科」院長。
日本矯正歯科学会 認定医。