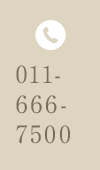歯間ブラシとフロス、どっちを選ぶべき?現役歯科医師が違いを徹底解説!

こんにちは。医療法人 札幌矯正歯科 宮の沢エミル矯正歯科の理事長の尾立卓弥です。札幌で矯正歯科を検討中の方は、ぜひ医療法人 札幌矯正歯科 宮の沢エミル矯正歯科でご相談ください。歯間ブラシとフロス、どちらを使うべきか迷っていませんか?この記事では、現役歯科医師が歯間ブラシとフロスの違い、それぞれのメリット・デメリット、そしてあなたの歯の状態に合わせた最適な選び方を徹底解説します。形状や用途の違いから、正しい使い方、よくある疑問まで詳しく説明。どちらか一方が絶対ではなく、ご自身の口内環境に合ったケアを選ぶことが重要です。この記事を読んで、あなたにぴったりのオーラルケアを見つけましょう。
1. 歯間ブラシとフロス どちらを使うか迷っていませんか?
毎日の歯磨き、しっかり行っていますか? 歯ブラシで丁寧に磨いているつもりでも、歯と歯の間の汚れや、歯と歯茎の境目に残るプラーク(歯垢)までは、なかなか完全には落としきれていないかもしれません。鏡を見て「ちゃんと磨けているかな?」と不安になったり、歯科医院で「歯の間に汚れが溜まっていますね」と指摘されたりした経験はありませんか?
「歯医者さんで歯間ケアを勧められたけど、歯間ブラシとデンタルフロス、一体どっちを選べばいいの?」「種類が多すぎて、自分にはどちらが合っているのか分からない…」そんなお悩みを抱えている方は、決して少なくありません。ドラッグストアやスーパーマーケットのオーラルケアコーナーには、様々な形状やサイズの歯間清掃具がずらりと並んでおり、どれを選ぶべきか迷ってしまうのも無理はないでしょう。
しかし、歯間部のケアは、虫歯や歯周病といったお口の二大トラブルを予防し、生涯にわたってご自身の歯を健康に保つために非常に重要です。歯ブラシだけでは届かない汚れを効果的に除去するためには、歯間ブラシやフロスといった専用のツールを毎日の習慣に取り入れることが不可欠なのです。
この記事では、日々患者さんのお口の健康を守る現役歯科医師の視点から、歯間ブラシとフロスの基本的な違い、それぞれのメリット・デメリット、そしてあなたの歯の状態やライフスタイルに合わせた最適な選び方、さらに効果的な使い方まで、分かりやすく徹底的に解説していきます。正しい知識を身につけ、あなたにぴったりの歯間ケアを見つけ、自信を持ってオーラルケアに取り組みましょう。
1.1 歯間ケアはなぜ重要?歯ブラシだけでは不十分な理由
私たちが毎日使っている歯ブラシは、歯の表面(表側、裏側、噛み合わせの面)の汚れを落とすのには非常に効果的な道具です。しかし、どんなに高性能な歯ブラシを使っても、どんなに時間をかけて丁寧に磨いても、構造的に歯ブラシの毛先が届きにくい場所が存在します。それが、隣り合う歯と歯が接する面(隣接面)や、歯と歯茎の境目にあるわずかな溝(歯周ポケット)です。
様々な研究データがありますが、一般的に歯ブラシだけでの歯磨きでは、お口の中全体のプラーク(歯垢)の約60%程度しか除去できていないと言われています。驚くことに、残りの約40%ものプラークは、主にこの歯ブラシが届きにくい歯間部に溜まっているのです。この磨き残されたプラークこそが、お口のトラブルを引き起こす元凶となります。
プラークは、単なる食べカスではありません。プラークは、細菌とその代謝産物からなるネバネバとした塊であり、わずか1mg(つまようじの先に付く程度)のプラークには、数億から10億個もの細菌が生息していると言われています。このプラーク中の細菌が作り出す酸によって歯のエナメル質が溶かされ、穴が開いてしまうのが虫歯です。また、プラークが歯茎に炎症を引き起こし(歯肉炎)、それが進行すると歯を支える顎の骨(歯槽骨)まで溶かしてしまうのが歯周病です。歯周病は、日本人の成人の約8割がかかっている、またはその予備軍とも言われる国民病であり、歯を失う最大の原因となっています。さらに、プラークは嫌気性細菌(酸素を嫌う細菌)の温床となり、不快な口臭の大きな原因にもなります。
このように、歯ブラシだけのケアでは、虫歯や歯周病のリスクが特に高い歯間部のプラークを十分に除去することができません。お口全体の健康を守り、将来的な歯の喪失を防ぐためには、歯ブラシによるブラッシングに加えて、歯間ブラシやフロスを用いた歯間ケアを毎日の習慣にすることが、歯科医学的に強く推奨されているのです。
1.2 歯間ブラシとフロス、それぞれの役割の概要
歯間ブラシとデンタルフロスは、どちらも歯ブラシではアクセスできない歯間部のプラークを除去するために開発された、いわば「歯間部専用の清掃ツール」です。しかし、その形状、使い方、そして得意とする清掃場所には明確な違いがあります。
それぞれの基本的な役割と特徴を簡単にまとめると、以下のようになります。
- 歯間ブラシ:ワイヤー(金属またはゴム)の周りに短いブラシ毛が付いた形状をしています。主に、歯と歯の間の隙間がある程度広い場所の清掃に適しており、ブラシで効率的にプラークをこすり落とすことができます。歯の根元付近の隙間や、ブリッジ(歯がない部分を補う連結した被せ物)の下などの清掃にも有効です。
- デンタルフロス:ナイロンやPTFE(テフロン)などの化学繊維でできた細い糸です。主に、歯と歯がぴったりと接している狭い隙間や、歯周ポケットの浅い部分の清掃に適しています。糸を歯間に滑り込ませ、歯の側面に沿わせて上下に動かすことで、付着したプラークを絡め取るように除去します。
重要なのは、「どちらか一方が絶対的に優れている」というわけではないということです。ご自身の歯並び、歯と歯の隙間の広さ、歯茎の状態、そして使いやすさなどを考慮して、最適なツールを選択し、正しく使い分けることが、効果的な歯間ケアの鍵となります。まずは、両者の基本的な違いを下記の表で確認してみましょう。
| 項目 | 歯間ブラシ | デンタルフロス |
|---|---|---|
| 主な形状 | ワイヤーまたはゴムの芯にブラシ毛が付いている(ボトルブラシ状) | 細い繊維の束(糸状) |
| 主な材質 | ナイロン毛、ゴム、ワイヤー(金属)、プラスチック | ナイロン、PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、ポリエステルなど |
| 主な用途 | 歯間部のプラーク除去、食べカス除去 | 歯間部(特に接触点付近)のプラーク除去、歯周ポケット内の清掃 |
| 得意な場所 | 比較的隙間が広い歯間部、歯の根元付近、ブリッジの下、矯正装置周辺 | 隙間が狭い歯間部、歯と歯が接している面(コンタクトポイント) |
| 清掃メカニズム | ブラシによる物理的なこすり落とし | 糸によるプラークの絡め取り、拭い取り |
| サイズ・種類 | サイズ展開が非常に豊富(例: 4S, SSS, SS, S, M, L, LLなど)、形状もI字型・L字型など多様 | 太さ(ワックス付き/なし)、形状(ロールタイプ/ホルダータイプ)に種類あり |
この表はあくまで概要です。この後の章では、それぞれの種類、メリット・デメリット、そして具体的な選び方や使い方について、歯科医師の視点からさらに詳しく、そして分かりやすく掘り下げて解説していきます。
1.3 この記事で解決できるあなたの疑問
「歯間ブラシとフロス、結局どっちを使えばいいの?」という最初の疑問はもちろんのこと、この記事を読み進めることで、あなたが歯間ケアに関して抱えているであろう様々な疑問や不安が解消されるはずです。
- 歯間ブラシとフロスの具体的な違いは?形状や材質、清掃できる場所の違いを詳しく知りたい。
- それぞれのメリットとデメリットを比較して、自分に合った方を選びたい。
- 自分の歯の隙間に合ったサイズや種類はどうやって選べばいいの?選び方の基準が知りたい。
- 歯並びが悪いんだけど、どっちが使いやすい?歯茎が腫れているときはどうすればいい?
- 初心者でも簡単に使えるのはどっち?
- 歯間ブラシやフロスの効果的な使い方と、やってはいけないNGな使い方は?歯科医師推奨の方法を知りたい。
- 歯間ケアはいつ、どのタイミングで行うのが最も効果的?歯磨きの前?それとも後?
- 歯間ブラシやフロスを使うと血が出ることがあるけど、続けても大丈夫?歯科医師の見解は?
- 子供にも歯間ブラシやフロスは必要?何歳から始めるべき?
- 歯間ブラシとフロス、両方使った方がいいの?それともどちらか一方で十分?
これらの誰もが一度は疑問に思うであろう点について、現役歯科医師が、科学的根拠と臨床経験に基づき、具体的かつ実践的なアドバイスを提供します。この記事を最後までお読みいただければ、明日からのオーラルケアに対する意識が変わり、自信を持ってご自身に最適な歯間ケアの方法を選び、正しく実践できるようになることをお約束します。さあ、一緒に虫歯や歯周病に負けない、健康で美しいお口を目指しましょう!
2. そもそも歯間ブラシとは?歯科医師が基本を解説
歯ブラシだけでは落としきれない歯と歯の間の汚れ、プラーク(歯垢)。これを効果的に除去するために開発されたのが歯間ブラシです。歯間ブラシは、特に歯と歯の間の隙間がある程度開いている場合に有効な清掃補助用具であり、虫歯や歯周病予防に欠かせないアイテムとして、多くの歯科医師が推奨しています。
歯磨きだけでは、歯全体の約60%程度の汚れしか落とせないと言われています。残りの約40%は、歯と歯の間や歯と歯茎の境目に潜んでいます。この磨き残しが、虫歯や歯周病、口臭の大きな原因となるのです。歯間ブラシは、この歯ブラシが届きにくい部分のプラークを効率的に除去するための専門ツールと言えます。
ここでは、歯間ブラシの基本的な知識について、現役歯科医師の視点から詳しく解説していきます。
2.1 歯間ブラシの形状と主な用途
歯間ブラシは、主に細いワイヤーやゴムの芯に、短い毛(ブラシ)がたくさん付いた構造をしています。持ちやすいように柄(ハンドル)が付いており、様々な形状やサイズが存在します。芯の周りについているブラシ部分は、ナイロン製が一般的ですが、製品によっては特殊な素材が使われていることもあります。
代表的な形状として、以下の2つのタイプがあります。
- I字型(ストレートタイプ): まっすぐな形状で、主に前歯の歯間に挿入しやすいのが特徴です。持ち手が短いものが多いですが、奥歯に使う場合は指で角度を調整する必要があります。
- L字型(アングルタイプ): 柄の部分がL字に曲がっており、奥歯の歯間にも楽に届きやすいように設計されています。特に奥歯の清掃が苦手な方や、お口が開きにくい方におすすめです。
どちらのタイプも、基本的な役割は同じです。歯と歯の間の側面や、歯と歯茎の境目(歯肉溝)に付着したプラークを、ブラシ部分で物理的にこすり落とすことを目的としています。この物理的な除去が、プラークコントロールにおいて非常に重要です。
歯間ブラシの主な用途は、歯ブラシの毛先が届きにくい以下の場所の清掃です。
- 歯と歯の間の、特に少し広めの隙間
- 歯と歯茎の境目(歯肉溝)
- ブリッジ(連結した被せ物)の下の部分(ポンティック基底面)
- インプラントの周り
- 矯正装置(ブラケットやワイヤー)の周り
- 孤立している歯(隣接する歯がない歯)の周り
- 歯並びが悪く、歯が重なっている部分
これらの場所に溜まったプラークは、虫歯や歯周病の主な原因菌の温床となります。特に歯周病は、歯を支える骨(歯槽骨)を溶かしてしまう病気であり、進行すると歯が抜けてしまうこともあります。歯間ブラシを日常的に使用することで、これらの病気のリスクを大幅に低減させることが期待できます。また、プラークが原因となる口臭の予防・改善にも繋がります。
2.2 歯間ブラシの種類 サイズ選びの重要性
歯間ブラシは、芯の材質やブラシの形状によっていくつかの種類に分けられます。また、効果的かつ安全に使用するためには、サイズ選びが極めて重要になります。
2.2.1 歯間ブラシの主な種類
芯の材質によって、大きく「ワイヤータイプ」と「ゴムタイプ」の2種類に分けられます。それぞれの特徴を理解し、ご自身の状態やお好みに合わせて選ぶことが大切です。
| 種類 | 主な材質 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|
| ワイヤータイプ | 芯:金属ワイヤー ブラシ:ナイロン毛など |
芯が金属でできており、その周りにブラシ毛が付いている最も一般的なタイプ。 |
|
|
| ゴムタイプ | 芯・ブラシ:ゴム、エラストマーなど | ワイヤーを使用せず、全体が柔らかいゴムやエラストマー素材でできているタイプ。ブラシ部分も突起状になっていることが多い。 |
|
|
最近では、ワイヤー部分が樹脂でコーティングされていて歯茎への刺激を軽減したものや、ブラシ毛の形状に工夫が凝らされてプラーク除去効果を高めたもの、抗菌加工が施されたものなど、様々な製品が各メーカー(例:ライオン、サンスター、小林製薬、デンタルプロなど)から販売されています。ドラッグストアや歯科医院で、どのような種類があるか確認してみると良いでしょう。
2.2.2 サイズ選びの重要性
歯間ブラシの効果を最大限に引き出し、かつ安全に使用するためには、ご自身の歯間の隙間に合ったサイズを選ぶことが何よりも重要です。歯間ブラシには、メーカーによって「4S(SSSS)」「SSS」「SS」「S」「M」「L」「LL」といったサイズ表記があり、それぞれブラシ部分の最も太い部分の直径(通過径)が異なります。
小さすぎるサイズを選んでしまうと、ブラシがスカスカで歯面に十分に当たらず、プラークを効果的に除去できません。せっかく使っても、清掃効果が半減してしまうのです。
逆に、大きすぎるサイズを無理に挿入しようとすると、強い抵抗を感じ、歯茎を傷つけて出血させたり、痛みを引き起こしたりする原因になります。場合によっては、歯の表面(エナメル質やセメント質)を傷つけたり、被せ物や詰め物を傷めたりする可能性もあります。さらに、長期的に不適切なサイズの歯間ブラシを使用し続けることで、歯茎が下がる(歯肉退縮)リスクも指摘されています。
適切なサイズの目安は、歯間の隙間にスムーズに挿入でき、きついと感じることなく、かつ軽い抵抗を感じる程度です。挿入時にワイヤーが歯に引っかかるような感覚がある場合は、サイズが大きすぎる可能性があります。
しかし、ご自身だけで最適なサイズを見つけるのは難しい場合も少なくありません。特に初めて歯間ブラシを使用する場合や、どのサイズから試せば良いか分からない場合は、自己判断せず、必ずかかりつけの歯科医師や歯科衛生士に相談してください。歯科医院では、専用の器具を使って歯間のサイズを測定し、あなたの歯間の隙間に合った最適な歯間ブラシの種類とサイズを選んでくれます。また、正しい使い方の指導も受けられます。
注意点として、お口の中の歯間の隙間は、場所によって広さが異なることが一般的です。例えば、前歯の隙間は狭く、奥歯の隙間は広い、といった具合です。そのため、1種類のサイズだけでなく、複数のサイズの歯間ブラシを使い分ける必要がある方がほとんどです。面倒に感じるかもしれませんが、それぞれの部位に適したサイズを使うことが、効果的なプラークコントロールと、歯や歯茎の健康を守るために不可欠です。
3. デンタルフロスとは?歯科医師が基本を解説
デンタルフロスは、歯ブラシだけでは届かない歯と歯の間の狭い隙間(歯間部)や、歯と歯茎の境目(歯肉溝)の汚れ、特に歯垢(プラーク)を除去するために設計された清掃用具です。ナイロンやPTFE(テフロン)などの細い繊維を束ねて作られた糸状のツールで、歯間の清掃に特化しています。
毎日の歯磨きで歯ブラシを使っていても、歯全体の汚れの約60%程度しか落とせていないと言われています。残りの約40%は、歯と歯の間や歯と歯茎の境目に溜まった歯垢です。この歯ブラシが届かない部分の歯垢を効果的に除去できるのがデンタルフロスであり、虫歯や歯周病(歯肉炎・歯周炎)の予防に不可欠なオーラルケアアイテムとして、多くの歯科医師が使用を推奨しています。
3.1 フロスの形状と主な用途
デンタルフロスは、その名の通り「糸(フロス)」状の形状をしています。この細い糸が、歯と歯が接している非常に狭い隙間にも入り込み、歯ブラシの毛先では届かない隣接面(歯と歯が隣り合っている面)の歯垢を物理的に掻き出すことができます。
主な用途は以下の通りです。
- 歯間隣接面の歯垢除去: 歯と歯が接触している部分は、虫歯が発生しやすい部位の一つです。フロスはこの部分の歯垢を効果的に取り除き、隣接面う蝕(歯と歯の間の虫歯)のリスクを低減します。
- 歯肉溝内の歯垢除去: 歯と歯茎の境目にある溝(歯肉溝)も、歯垢が溜まりやすく、歯周病の原因となります。フロスを歯肉溝内にわずかに入れることで、この部分の歯垢も除去し、歯肉炎や歯周炎の予防に繋がります。
- 口臭予防: 歯間に溜まった歯垢や食べかすは、細菌の温床となり、口臭の原因物質を産生します。フロスでこれらを除去することは、口臭の予防・改善にも効果的です。
素材には、主にナイロン製とPTFE(ポリテトラフルオロエチレン、テフロンの商標で知られる)製があります。ナイロン製は複数の繊維を束ねており、歯垢を絡め取りやすいですが、引っかかりやすい場合があります。PTFE製は繊維が一本のテープ状になっており、滑りが良く歯間に挿入しやすいですが、ナイロン製より歯垢除去効率がやや劣るとも言われます。どちらが良いかは、歯の状態や好みによります。
3.2 フロスの種類 ホルダータイプとロールタイプ
デンタルフロスには、大きく分けて「ロールタイプ(糸巻きタイプ)」と「ホルダータイプ(フロスピック、糸ようじ)」の2種類があります。それぞれの特徴を理解し、ご自身に合ったものを選ぶことが大切です。
3.2.1 ロールタイプ(糸巻きタイプ)フロス
ケースに入った長い糸を必要な長さ(約40cm程度)だけ引き出して指に巻き付け、使用するタイプです。最も基本的なフロスの形態と言えます。
メリット:
- 経済的: 1つの製品で長期間使用できるため、コストパフォーマンスが高い傾向にあります。
- 衛生的: 清掃する歯間ごとに常に新しい清潔な部分の糸を使用できます。
- 操作性の自由度が高い: 指先の感覚を活かして、歯のカーブに合わせて糸を沿わせたり、微妙な力加減を調整したりしやすいです。
- 種類の豊富さ: ワックス(滑りを良くするため)の有無、太さ(細め、標準、太め、エキスパンディングタイプ:唾液で膨らむ)、フレーバー(ミントなど)付きなど、様々なバリエーションがあります。
デメリット:
- 慣れが必要: 正しい使い方を習得するまでに少し練習が必要です。特に奥歯への使用は難しく感じることがあります。
- 手が汚れることがある: 指を直接口の中に入れるため、唾液などが付着することがあります。
ワックス付きは初心者の方や歯間が狭い方、ワックスなしは歯垢除去効果をより重視する方やワックスの感触が苦手な方におすすめです。太さは歯間の広さに合わせて選びましょう。
3.2.2 ホルダータイプフロス(フロスピック、糸ようじ)
プラスチック製の持ち手(ホルダー)に、あらかじめフロスが張られているタイプです。「糸ようじ」や「フロスピック」といった名称で広く知られています。
メリット:
- 初心者でも簡単: 指に巻き付ける手間がなく、すぐに使えるため、フロス初心者の方でも比較的簡単に扱えます。
- 手が汚れにくい: ホルダーを持つため、直接指を口に入れる必要がありません。
- 奥歯にも届きやすい: 特にY字型のホルダーは、持ち手が長いため奥歯の歯間にも挿入しやすい設計になっています。
- 携帯に便利: 個包装されている製品も多く、外出先での使用にも便利です。
デメリット:
- コストがかかる: ロールタイプに比べて、1回あたりのコストは高くなる傾向があります。
- 衛生面での注意: 基本的に同じフロス部分で複数の歯間を清掃するため、汚れが付着したまま使い続けると細菌を移動させてしまう可能性があります。こまめに洗浄するか、使い捨てタイプを選ぶなどの配慮が必要です。
- 操作性の制限: ホルダーの形状により、ロールタイプほど歯の面に細かく沿わせるのが難しい場合があります。
- フロスの選択肢が少ない: ロールタイプほどフロス自体の種類(太さ、素材など)は多くありません。
ホルダーの形状には、主に前歯部に使いやすいF字型と、奥歯に使いやすいY字型があります。また、ホルダーの反対側にピック(爪楊枝のようなもの)が付いていて、大きな食べかすを取り除くのに便利なタイプもあります。
3.2.3 ロールタイプとホルダータイプの比較
どちらのタイプが優れているということではなく、それぞれの特徴を理解し、ご自身のライフスタイルや使いやすさ、お口の状態に合わせて選ぶことが重要です。以下の表に主な違いをまとめました。
| 項目 | ロールタイプフロス | ホルダータイプフロス |
|---|---|---|
| 主な形状 | 糸巻き状のフロスを指に巻いて使用 | プラスチック製ホルダーにフロスが張られている |
| 使いやすさ | 慣れが必要(特に奥歯) | 初心者でも比較的簡単 |
| 経済性 | 高い | 低い(ロールタイプ比) |
| 衛生面 | 部位ごとに新しい糸を使える | 同じフロス部分を繰り返し使う場合があり、洗浄や交換が必要 |
| 操作の自由度 | 高い(指先で微調整可能) | やや制限される |
| フロスの種類 | 豊富(ワックス有無、太さ、素材など) | 限定的 |
| 携帯性 | ケースはコンパクトだが、使用時に手間がかかる | 個包装タイプは携帯しやすい |
初めてフロスを使う方はホルダータイプから試してみるのも良いでしょう。慣れてきたらロールタイプに挑戦したり、前歯はロールタイプ、奥歯はホルダータイプと使い分けるのも一つの方法です。どちらのタイプを使うにしても、正しい使い方をマスターし、毎日の習慣として継続することが最も重要です。
4. 歯間ブラシとフロスの違いを徹底比較
歯間ブラシとデンタルフロスは、どちらも歯ブラシだけでは届かない歯と歯の間の汚れ(プラーク)を取り除くための大切なオーラルケアグッズです。しかし、形状や得意な場所、使い方には明確な違いがあります。それぞれの特徴を理解し、ご自身の口腔内の状態に合わせて適切に使い分けることが、虫歯や歯周病予防には不可欠です。ここでは、現役歯科医師の視点から、歯間ブラシとフロスの違いを詳しく比較解説していきます。
4.1 清掃できる場所の違い 歯間ブラシとフロスの得意なこと
歯間ブラシとフロスは、得意とする清掃場所が異なります。どちらか一方が優れているというわけではなく、お口の中の場所や状態によって使い分けることが重要です。
| アイテム | 得意な場所 | 主な役割・特徴 |
|---|---|---|
| 歯間ブラシ |
|
ブラシ状の毛で、広い範囲のプラークを効率的に掻き出すことができます。特に歯周病が進行して歯茎が下がり、隙間が広くなった場合に効果を発揮します。 |
| デンタルフロス |
|
糸状の形状で、歯ブラシや歯間ブラシでは届かない、歯と歯が密接している部分のプラークを効果的に除去します。隣り合った歯の接触面の虫歯予防に特に重要です。 |
このように、歯間ブラシは「面」で汚れを落とすイメージ、フロスは「線」で汚れを掻き出すイメージと捉えると分かりやすいかもしれません。歯科医師としては、ご自身の歯の隙間の広さや歯並び、歯茎の状態を考慮して、適切なアイテムを選ぶことを推奨します。
4.2 形状と使い方の違い
清掃場所の違いは、それぞれの形状と使い方の違いから生まれます。それぞれの基本的な特徴を見ていきましょう。
| アイテム | 主な形状 | 基本的な使い方 |
|---|---|---|
| 歯間ブラシ |
|
|
| デンタルフロス |
|
|
歯間ブラシは比較的シンプルな動きで使えますが、サイズ選びが重要です。一方、フロス、特にロールタイプは正しい使い方を習得するのに少し練習が必要ですが、狭い隙間への対応力は抜群です。ホルダータイプは初心者でも比較的扱いやすいでしょう。
4.3 歯間ブラシのメリット デメリット
歯間ブラシが持つ利点と注意点を理解しておきましょう。
4.3.1 メリット
- 広い歯間のプラーク除去効率が非常に高い点です。ブラシが隙間全体に行き渡り、効率的に汚れを掻き出せます。
- 歯周病などで歯茎が下がり、歯の根元が見えている場合の根面のくぼみの清掃に適しています。フロスでは届きにくい部分もケアできます。
- ブリッジの下やインプラント周囲など、特殊な形状の部分の清掃にも有効です。
- 特にL字型やハンドル付きのものは奥歯にも挿入しやすく、操作が比較的簡単です。
- 様々なサイズ展開があり、自分の歯間の広さに合ったものを選べます。
4.3.2 デメリット
- 狭い歯間には物理的に挿入できません。無理に入れようとすると歯や歯茎を傷つける原因になります。
- 適切なサイズを選ばないと清掃効果が低下したり、逆に歯茎を傷つけたりする可能性があります。サイズ選びが非常に重要です。
- ワイヤー部分が剥き出しになっているタイプの場合、誤って歯茎に刺してしまうリスクがあります。
- 基本的に使い捨てのため、フロス(特にロールタイプ)に比べてランニングコストが高くなる傾向があります。
- ブラシ部分が消耗するため、定期的な交換が必要です(毛先が乱れたり、ワイヤーが曲がったら交換)。
4.4 フロスのメリット デメリット
次に、デンタルフロスの利点と注意点を見ていきましょう。
4.4.1 メリット
- 歯ブラシや歯間ブラシでは届かない、歯と歯が強く接している面(コンタクトポイント)のプラーク除去に唯一効果的なツールと言えます。隣接面の虫歯予防に不可欠です。
- 狭い歯間にもスムーズに挿入できます。歯間ブラシが入らないほとんどの隙間に使用可能です。
- 歯と歯茎の境目、歯周ポケットの浅い部分(1~2mm程度)の清掃が可能で、歯肉炎の予防・改善に役立ちます。
- ロールタイプの場合、コストパフォーマンスが高く経済的です。
- コンパクトで持ち運びに便利なので、外出先でもケアしやすいです。
4.4.2 デメリット
- 特にロールタイプは、正しい使い方をマスターするのに慣れが必要です。指先の感覚が重要になります。
- 広い歯間や歯の根元のくぼみなど、凹凸のある部分のプラーク除去効率は歯間ブラシに劣ります。
- 力を入れすぎたり、使い方を誤ると歯茎を傷つけてしまう(フロスが歯茎に食い込むなど)可能性があります。
- 詰め物や被せ物の縁(マージン)に引っかかったり、フロスが切れたりすることがあります。不適合な修復物がある場合は特に注意が必要です。
- ホルダータイプは手軽ですが、ロールタイプに比べて歯面に沿わせる操作がやや難しい場合があります。また、コストはロールタイプより高くなります。
歯間ブラシとフロス、それぞれの違いとメリット・デメリットを理解することで、ご自身の口腔ケアをより効果的に行うことができます。次の章では、これらの違いを踏まえ、具体的にどちらを選ぶべきかの基準について、歯科医師の視点から解説します。
5. 歯科医師が教える 歯間ブラシとフロスどっちを選ぶべきかの基準
歯間ブラシとデンタルフロス、どちらも歯と歯の間のプラーク(歯垢)を除去するための重要なオーラルケアグッズですが、それぞれ得意なことや適した状況が異なります。ご自身の口内環境に合わせて最適なツールを選ぶことが、効果的な歯間清掃には不可欠です。ここでは、現役歯科医師の視点から、歯間ブラシとフロスのどちらを選ぶべきか、具体的な基準を詳しく解説します。
5.1 歯と歯の隙間の広さによる選び方
最も基本的で重要な選択基準は、歯と歯の間の隙間(歯間空隙)の広さです。 歯ブラシの毛先が届かない歯間のプラークを効率的に除去するためには、隙間のサイズに合ったツールを選ぶ必要があります。
5.1.1 隙間が広い場合は歯間ブラシ
歯と歯の間に比較的広い隙間がある場合、特に奥歯の歯間などには、歯間ブラシの使用が推奨されます。 歯間ブラシは、フロスよりも太いブラシ部分が歯の側面や歯と歯茎の境目の溝(歯周ポケット)にしっかりと接触し、効率的にプラークを掻き出すことができます。歯茎が下がってきて歯の根元が見えているような場合(歯肉退縮)も、歯間ブラシが適しています。ただし、隙間に対して細すぎる歯間ブラシでは清掃効果が低く、太すぎるものは歯や歯茎を傷つける原因になります。適切なサイズを選ぶことが非常に重要です。
5.1.2 隙間が狭い場合はフロス
歯と歯がぴったりと接している、または隙間が非常に狭い場合には、デンタルフロスが適しています。 細い糸であるフロスは、狭い隙間にもスムーズに挿入することができます。歯間ブラシが入らないような狭い隙間に無理に歯間ブラシを挿入しようとすると、歯茎を傷つけたり、歯を痛めたりする可能性があります。特に前歯の歯間など、隙間が目立たない箇所にはフロスが第一選択となることが多いです。
隙間の広さに応じた基本的な選び方を以下の表にまとめました。
| 歯と歯の隙間の広さ | 推奨される清掃ツール | 主な理由 |
|---|---|---|
| 広い(歯間ブラシが無理なく通る) | 歯間ブラシ | 広い面積のプラークを効率的に除去できる |
| 狭い(歯間ブラシが入らない、またはきつい) | デンタルフロス | 狭い隙間にもスムーズに挿入でき、歯や歯茎への負担が少ない |
| 非常に狭い(フロスも通りにくい場合がある) | デンタルフロス(ワックス付きなど滑りやすいタイプ) | 挿入時の摩擦を軽減できる |
5.2 歯並びや歯の状態に合わせた選び方
歯と歯の隙間の広さだけでなく、歯並びや歯、修復物の状態によっても適切なツールは異なります。
- 歯並びが悪い(叢生): 歯が重なり合っている部分は、隙間の大きさや形が複雑になっていることが多いです。フロスは角度を変えながら挿入しやすく、このような複雑な部分の清掃に適している場合があります。一方で、部分的に隙間が広い箇所には歯間ブラシが有効なこともあります。場所によって使い分けるのが理想的です。
- ブリッジ: ブリッジの下(ポンティック基底部)は、歯ブラシが届かずプラークが溜まりやすい場所です。スーパーフロス(フロスの一部がスポンジ状になっているもの)や、歯間ブラシを使って清掃する必要があります。ブリッジ専用のフロススレッダー(糸通し)を使うと、通常のフロスも通しやすくなります。
- インプラント: インプラント周囲は天然歯よりもデリケートで、炎症(インプラント周囲炎)を起こしやすいため、丁寧な清掃が不可欠です。インプラント専用のフロスや、柔らかめの歯間ブラシを使用し、インプラント体や周囲の組織を傷つけないように優しく清掃します。太めの歯間ブラシが必要な場合もあります。
- 矯正装置(ブラケットやワイヤー): 矯正治療中は、装置の周りにプラークが溜まりやすくなります。フロススレッダーを使ってワイヤーの下にフロスを通したり、矯正用のフロス、あるいは非常に細い歯間ブラシ(SSSサイズ以下など)を使用して、装置周辺や歯間を清掃します。
歯の状態に合わせた選び方の例を以下に示します。
| 歯の状態 | 推奨される清掃ツール(例) | ポイント |
|---|---|---|
| 歯並びが悪い(叢生) | フロス、歯間ブラシ(部分的に) | 複雑な形状に合わせて使い分ける |
| ブリッジ | スーパーフロス、歯間ブラシ、フロススレッダー+フロス | ブリッジ下の清掃が重要 |
| インプラント | インプラント用フロス、柔らかい歯間ブラシ | インプラント周囲組織を傷つけないように優しく |
| 矯正装置装着中 | フロススレッダー+フロス、矯正用フロス、極細歯間ブラシ | 装置周りのプラークを丁寧に除去 |
5.3 歯茎の状態と選び方のポイント
歯茎の状態も、歯間清掃具を選ぶ上で重要な要素です。
- 健康な歯茎: 歯茎が引き締まっており、出血などがない場合は、前述の「歯と歯の隙間の広さ」を主な基準として選びます。隙間が狭ければフロス、広ければ歯間ブラシが基本です。
- 歯肉炎(歯茎の腫れ・出血): 歯肉炎で歯茎が腫れている場合、最初はフロスや歯間ブラシを使うと出血しやすいですが、これは汚れ(プラーク)が原因で炎症を起こしているサインです。怖がらずに、むしろ丁寧にプラークを除去することが改善への第一歩です。ただし、痛みが強い場合は無理せず、柔らかめの歯間ブラシを選んだり、フロスを優しく挿入したりするようにしましょう。適切な清掃を続けることで、炎症が治まり出血しにくくなります。
- 歯周病(歯茎下がり・歯周ポケット): 歯周病が進行して歯茎が下がったり、歯周ポケットが深くなったりしている場合は、歯と歯の間の隙間が大きくなっていることが多いです。このような場合は、歯間ブラシがプラーク除去に効果的です。歯周ポケット内部の清掃も意識して、適切なサイズの歯間ブラシを選びましょう。歯科医師や歯科衛生士に相談し、ポケットの深さに合った清掃方法の指導を受けることが重要です。
- 知覚過敏: 歯茎が下がるなどして歯の根元(象牙質)が露出し、知覚過敏がある場合は、歯間ブラシやフロスがしみる原因になることがあります。力を入れすぎず、優しく操作することを心がけましょう。冷水でうがいするのを避ける、知覚過敏用の歯磨き粉を使うなどの対策も有効です。
歯茎の状態に合わせて、無理なく、かつ効果的にプラークを除去できるツールを選ぶことが大切です。出血が続く、痛みが強いなどの場合は、自己判断せずに必ず歯科医師に相談してください。
5.4 初心者向け 使いやすさで選ぶなら
初めて歯間清掃を行う方にとっては、使いやすさも重要な選択基準になります。
- ホルダー付きフロス(糸ようじ): 持ち手が付いているため、比較的簡単に操作でき、初心者の方でも手軽に始めやすいというメリットがあります。特に奥歯の清掃が難しいと感じる方におすすめです。F字型やY字型など、形状にも種類があります。
- 歯間ブラシ: 適切なサイズを選び、まっすぐ挿入して数回往復させるという基本的な操作は、慣れれば比較的簡単です。ただし、前述の通りサイズ選びが重要であり、最初はどのサイズを選べばよいか迷うかもしれません。最初は一番細いサイズから試してみるか、歯科医院でサイズを確認してもらうのが良いでしょう。
- ロールタイプフロス: 指に巻き付けて使用するため、最初は少し練習が必要で、慣れるまで操作が難しく感じるかもしれません。しかし、使いこなせれば、歯の側面に沿わせて汚れを効率的に絡め取ることができ、コストパフォーマンスも高いというメリットがあります。
どちらのツールも、正しい使い方をマスターするには少し練習が必要です。最初は鏡を見ながら、ゆっくり丁寧に行うことをお勧めします。もし「どちらも難しそう」と感じる場合は、まずはホルダー付きフロスから試してみて、歯間清掃の習慣をつけることから始めてみてはいかがでしょうか。継続することが最も重要ですので、自分が使いやすいと感じる、続けやすいツールを選ぶことが大切です。
5.5 歯科医師に相談して決めるのが最も確実
ここまで様々な選び方の基準を解説してきましたが、最終的にご自身の口内環境に最も適したツールとサイズ、そして正しい使い方を知るためには、歯科医師や歯科衛生士に相談するのが最も確実で安全な方法です。
自己判断で不適切なサイズの歯間ブラシを使用したり、間違った方法でフロスを使ったりすると、歯や歯茎を傷つけてしまうリスクがあります。特に、歯周病が進行している場合や、特殊な修復物(ブリッジ、インプラントなど)がある場合は、専門家による指導が不可欠です。
歯科医院では、定期検診やクリーニングの際に、以下のようなアドバイスを受けることができます。
- 患者さん一人ひとりの歯間の隙間や歯並び、歯茎の状態をチェック
- 最適な清掃ツール(歯間ブラシかフロスか、あるいは併用か)の提案
- 歯間ブラシを使用する場合の適切なサイズの選定
- 模型や実際の口を使って、正しい使い方や力加減のデモンストレーションと指導
- 清掃が難しい箇所へのアプローチ方法のアドバイス
歯科医師や歯科衛生士は、あなたの口の状態を最もよく理解している専門家です。遠慮なく質問し、自分に合った歯間清掃の方法を身につけましょう。正しいツール選びと使い方をマスターすることが、虫歯や歯周病を予防し、長期的に歯の健康を維持するための鍵となります。
6. 歯科医師推奨 歯間ブラシの正しい使い方
歯間ブラシは、歯ブラシだけでは届かない歯と歯の間のプラーク(歯垢)を効果的に除去するための重要なオーラルケアグッズです。しかし、その効果を最大限に引き出すためには、正しい使い方をマスターすることが不可欠です。ここでは、現役歯科医師が推奨する歯間ブラシの正しい使い方について、サイズ選びから動かし方、注意点まで詳しく解説します。
6.1 歯間ブラシのサイズ選び
歯間ブラシの効果を左右する最も重要なポイントが「サイズの選択」です。歯と歯の隙間の広さは、場所によって、また人によって大きく異なります。適切なサイズを選ばないと、清掃効果が得られないばかりか、歯や歯茎を傷つけてしまう可能性があります。
サイズの目安と種類
歯間ブラシのサイズは、一般的に「最小通過径(ブラシ部分が通過できる最も狭い隙間の直径)」で示され、SSS、SS、S、M、L、LLといった表記や、数字(0〜6など)で表されます。国際規格(ISO規格)に基づいたサイズ表示がされている製品もあります。
| サイズ表記例 | 最小通過径 (目安) | 主な対象 |
|---|---|---|
| SSSS (0) | 〜0.6mm | 非常に狭い歯間 |
| SSS (1) | 0.7mm〜 | 狭い歯間、歯茎が健康な方 |
| SS (2) | 0.8mm〜 | やや狭い歯間 |
| S (3) | 1.0mm〜 | 一般的な歯間 |
| M (4) | 1.2mm〜 | やや広い歯間、ブリッジ装着部位 |
| L (5) | 1.5mm〜 | 広い歯間、歯周病で歯茎が下がった方 |
| LL (6) | 1.8mm〜 | 非常に広い歯間 |
サイズの選び方のポイント
- 歯科医師・歯科衛生士に相談する: 最も確実なのは、歯科医院で自分の歯間の状態をチェックしてもらい、最適なサイズを教えてもらうことです。
- 最小サイズから試す: 自己判断で選ぶ場合は、まず最も細いサイズ(SSSやSSSS)から試しましょう。
- 無理なく挿入できる一番太いサイズを選ぶ: スカスカすぎず、抵抗なくスムーズに挿入できる中で、最も太いサイズが適しています。
- 複数のサイズを使い分ける: 前歯と奥歯、あるいは場所によって歯間の広さは異なります。1つのサイズだけでなく、複数のサイズを使い分ける必要がある場合が多いです。
間違ったサイズのリスク
- 小さすぎる場合: プラーク除去効果が低くなります。
- 大きすぎる場合: 歯や歯茎を傷つけ、痛みや出血、歯肉退縮(歯茎が下がること)の原因となります。無理に挿入するのは絶対にやめましょう。
6.2 歯間ブラシの挿入方法と動かし方
正しいサイズを選んだら、次は挿入方法と動かし方です。以下の手順を参考に、丁寧に行いましょう。
- 鏡を見る: 慣れるまでは鏡を見ながら、ブラシの先端の位置を確認して行いましょう。
- 歯間ブラシを持つ: 鉛筆を持つように軽く持ちます。
- 挿入角度:
- 前歯部: 歯と歯の隙間に対して、歯茎を傷つけないように少し歯の方向(斜め上または斜め下)から、水平に挿入します。
- 臼歯部 (奥歯): 頬側からだけでなく、舌側(内側)からも挿入するとより効果的です。L字型の歯間ブラシを使うか、I字型の場合はワイヤー部分を指で軽く曲げて角度をつけると挿入しやすくなります。
- 挿入する: 歯茎に突き刺さないよう、ゆっくりと歯面に沿わせるように挿入します。抵抗を感じたら無理に入れないでください。
- 動かす: ブラシが歯間を通過したら、数ミリ程度の幅で、水平に2〜3回、優しく往復させます。ゴシゴシと強くこすったり、回転させたりする必要はありません。
- 取り出す: ゆっくりと引き抜きます。
- 次の歯間へ: 使用した部分を軽く水でゆすぐかティッシュで拭き取り、次の歯間に移ります。全ての歯間に行いましょう。
特に奥歯は、頬側だけでなく舌側(内側)からもアプローチすることで、磨き残しを減らすことができます。L字型の歯間ブラシは奥歯に届きやすく便利です。
6.3 歯間ブラシ使用時の注意点
歯間ブラシを安全かつ効果的に使用するために、以下の点に注意しましょう。
- 使用頻度: 最低でも1日1回、就寝前の歯磨きの際に行うのが理想的です。毎食後に行う必要はありませんが、食べ物が詰まった時などは使用しましょう。
- 使用タイミング: 歯磨きの前か後かについては様々な意見がありますが、どちらでも構いません。歯磨き前に使用すると、歯間のプラークを先に取り除き、歯磨き粉のフッ素などが歯間部に行き渡りやすくなるというメリットがあります。まずは継続しやすいタイミングで行うことが大切です。
- 力加減: 絶対に力を入れすぎないこと。無理な挿入や強いブラッシングは歯茎を傷つけます。
- 出血について: 使い始めや歯茎に炎症がある場合、軽い出血が見られることがあります。これは、それまで除去できていなかったプラークによって歯茎が腫れていたためです。通常、正しいケアを続けることで1〜2週間程度で出血は収まってきます。しかし、痛みが強い場合や、出血が長く続く場合は、歯周病が進行している可能性がありますので、必ず歯科医師に相談してください。
- 交換時期:
- ワイヤータイプ: ブラシの毛先が乱れたり、ワイヤーが曲がったりしたら交換のサインです。衛生面も考慮し、1週間〜10日程度での交換が推奨されますが、製品の指示に従ってください。一度曲がったワイヤーを元に戻して使うのは、金属疲労で折れる危険があるため避けましょう。
- ゴムタイプ: 軸が折れたり、ブラシ部分が摩耗したら交換します。多くは使い捨てタイプです。
- 使用後のケア: 使用後は流水でよく洗い、ブラシ部分の汚れや水分をしっかり取り除き、風通しの良い場所で乾燥させて保管してください。キャップ付きの場合は、乾燥させてからキャップをしましょう。
- 歯間ブラシが入らない場合: 無理に挿入しようとせず、より細いサイズを試すか、デンタルフロスの使用を検討しましょう。歯科医師に相談するのが最も確実です。
歯間ブラシの正しい使い方をマスターし、毎日のセルフケアに取り入れることで、歯周病や虫歯のリスクを大幅に減らすことができます。もし使い方に不安がある場合は、かかりつけの歯科医師や歯科衛生士に遠慮なく質問し、指導を受けてください。
7. 歯科医師推奨 フロスの正しい使い方
歯ブラシだけでは届きにくい、歯と歯の間の狭い隙間。実は、むし歯や歯周病の原因となるプラーク(歯垢)が最も溜まりやすい場所の一つです。このプラークを効果的に除去するために欠かせないのがデンタルフロスです。しかし、自己流で使っていると、歯茎を傷つけたり、十分な清掃効果が得られなかったりすることも。ここでは、歯科医師が推奨する正しいフロスの使い方を、タイプ別に詳しく解説します。
7.1 ロールタイプのフロスの使い方
ロールタイプは、自分で必要な長さを切り出して指に巻き付けて使う、最も基本的なフロスです。慣れるまで少し練習が必要かもしれませんが、指で直接操作するため、微妙な力加減や角度の調整がしやすく、歯面にしっかりフィットさせやすいというメリットがあります。正しい使い方をマスターして、効果的な歯間清掃を行いましょう。
-
フロスを適切な長さに切る:まず、フロスを約40cm~50cm(肘から指先程度)の長さに切り取ります。十分な長さを確保することで、清潔な部分を常に使えるようにします。
-
指に巻き付ける:切り取ったフロスの大部分を片方の中指に、数回ゆるめに巻き付けます。もう片方の中指にも、フロスがピンと張るように残りを軽く巻き付けます。操作するのは、両手の親指と人差し指です。
-
フロスを歯間に挿入する:親指と人差し指でフロスをつまみ、指の間隔が1~2cmになるようにピンと張ります。鏡を見ながら、歯と歯の間にフロスをゆっくり当て、のこぎりを引くように小さく前後(または左右)に動かしながら、歯茎を傷つけないようにゆっくり挿入します。
-
歯の側面を清掃する:フロスが歯茎の少し下(歯周ポケットの浅い部分)まで入ったら、片方の歯の側面にフロスを「C」の字のように沿わせます。そのままフロスを歯面に密着させ、上下にゆっくりと数回動かしてプラークをこすり取ります。ゴシゴシと強く動かすのではなく、汚れをかき出すイメージで行いましょう。
-
隣接する歯の側面も清掃する:同じ歯間の、隣り合ったもう一方の歯の側面も同様に、フロスを「C」の字に沿わせて上下に動かし、清掃します。
-
フロスを引き抜く:清掃が終わったら、挿入時と同様に、ゆっくりと小さく動かしながらフロスを引き抜きます。
-
次の歯間へ:使用済みの汚れた部分は、フロスを巻き取っていた中指に巻き取り、清潔な部分を指先に送り出して、次の歯間を清掃します。全ての歯間を清掃するまで、この作業を繰り返します。
特に奥歯は、人差し指同士、または親指と人差し指をうまく使ってフロスを操作しましょう。最初は難しいかもしれませんが、焦らず丁寧に行うことが大切です。
7.2 ホルダータイプのフロス(糸ようじ)の使い方
ホルダータイプは、プラスチック製の持ち手にフロスが取り付けられているタイプで、「糸ようじ」とも呼ばれます。指に巻き付ける手間がなく、初心者でも比較的簡単に扱えるのが特徴です。特に、手が小さい方や、指先での細かい操作が苦手な方、奥歯にフロスを通すのが難しいと感じる方におすすめです。
ホルダータイプには、主に前歯に使いやすい「F字型」と、奥歯に届きやすい「Y字型」があります。ご自身の使いやすいタイプを選びましょう。
-
フロスを歯間に挿入する:ホルダーを持ち、フロス部分を歯と歯の間にゆっくり当てます。ロールタイプと同様に、のこぎりを引くように小さく動かしながら、歯茎を傷つけないように注意して挿入します。
-
歯の側面を清掃する:フロスが歯間に入ったら、片方の歯の側面にフロスを押し当て、歯面に沿わせながら上下に数回動かしてプラークを除去します。隣接するもう一方の歯の側面も同様に行います。
-
フロスを引き抜く:清掃が終わったら、ゆっくりと引き抜きます。
-
次の歯間へ:フロス部分についた汚れは、水で洗い流すかティッシュなどで拭き取ってから、次の歯間を清掃します。ただし、衛生面を考慮すると、使い捨てタイプが推奨されます。
ホルダータイプの多くには、持ち手の反対側にピック(つまようじのような部分)が付いているものがありますが、ピック部分で歯茎を強く突くと傷つける恐れがあるため、使用には注意が必要です。歯間の大きな食べカスを取る程度にとどめ、プラーク除去は必ずフロス部分で行いましょう。
7.3 フロス使用時の注意点
フロスを安全かつ効果的に使用するためには、いくつかの注意点があります。誤った使い方は、かえって歯や歯茎を傷つけてしまう可能性があるため、以下の点を必ず守りましょう。
| 注意点 | 理由 | 対処法・ポイント |
|---|---|---|
| 力を入れすぎない | 歯茎を傷つけ、歯肉退縮(歯茎が下がること)の原因になることがあります。 | フロスを挿入・操作する際は、優しい力で、ゆっくりと動かすことを心がけましょう。特に歯茎付近は慎重に。 |
| 無理に挿入しない | 歯茎に突き刺さったり、詰め物や被せ物が取れたりする可能性があります。 | フロスが入りにくい場合は、ワックス付きのフロスや、滑りの良いテープタイプのフロスを試すか、歯科医師・歯科衛生士に相談しましょう。 |
| のこぎりのようにゴシゴシ動かさない | 歯の側面や歯茎を傷つける可能性があります。清掃効果も低くなります。 | 歯面に「C」の字に沿わせ、上下に動かすのが基本です。プラークをかき出すイメージで行いましょう。 |
| 清潔なフロスを使う | 汚れたフロスを使い回すと、細菌を他の歯間に広げてしまう可能性があります。 | ロールタイプの場合、歯間ごとに必ず清潔な部分を使うようにしましょう。ホルダータイプは、可能であれば使い捨てタイプを選ぶか、使用ごとに丁寧に洗浄しましょう。 |
| 出血を恐れない(ただし注意は必要) | 使い始めや、歯茎に炎症がある場合(歯肉炎)、出血することがあります。これは、溜まっていたプラークが除去され、炎症部分に触れるために起こることが多いです。 | 正しい使い方を続けていれば、通常1~2週間で出血は収まってきます。もし出血が長く続く場合や、痛みが強い場合は、歯周病が進行している可能性もあるため、必ず歯科医師に相談してください。 |
| フロスが引っかかる・切れる場合 | 歯と歯の間に虫歯ができている、詰め物や被せ物の縁が合っていない、歯石が付いているなどの可能性があります。 | 無理にフロスを通そうとせず、早めに歯科医院を受診し、原因を確認してもらいましょう。 |
| 使用頻度とタイミング | プラークは時間とともに蓄積し、硬化(歯石化)したり、細菌が繁殖したりします。 | 最低でも1日1回、就寝前の歯磨きの際に行うのが最も効果的です。タイミングは歯磨きの前でも後でも構いませんが、歯磨き前にフロスで歯間の汚れを取り除いておくと、歯磨き粉の薬用成分が歯間部にも行き渡りやすくなるという考え方もあります。ご自身の続けやすいタイミングで行いましょう。 |
正しいフロスの使い方を習慣にすることで、歯ブラシだけでは落としきれないプラークを効果的に除去し、虫歯や歯周病のリスクを大幅に減らすことができます。もし使い方に不安がある場合や、どのフロスを選べば良いか分からない場合は、遠慮なくかかりつけの歯科医師や歯科衛生士にご相談ください。あなたのお口の状態に合った最適な方法を指導してくれます。
8. 歯間ブラシとフロスに関するよくある質問 歯科医師が回答
歯間ブラシとフロスの使い方について、患者さんからよくいただくご質問とその回答を、現役歯科医師の視点からまとめました。日々のオーラルケアにお役立てください。
8.1 歯間ブラシとフロス どっちかだけで良い?併用は必要?
結論から申し上げますと、歯間ブラシとフロスの両方を併用するのが最も理想的です。なぜなら、それぞれ得意な清掃範囲が異なるため、両方を使うことで歯と歯の間の歯垢(プラーク)をより効果的に除去できるからです。
歯ブラシだけでは、歯と歯の間の汚れの約60%しか落とせないと言われています。残りの約40%の汚れを除去するために、歯間清掃具の使用が不可欠なのです。
- 歯間ブラシが得意な場所: 歯と歯の間の隙間がある程度広い部分、ブリッジの下、歯列矯正装置の周りなど。根元部分のプラーク除去に効果的です。
- フロスが得意な場所: 歯と歯が接している狭い隙間、歯と歯茎の境目の溝(歯周ポケット)の浅い部分など。接触面のプラーク除去に適しています。
このように、歯間ブラシとフロスは互いに補完し合う関係にあります。併用することで、歯ブラシでは届かない箇所のプラーク除去率を大幅に向上させ、虫歯や歯周病のリスクを効果的に低減できます。
もちろん、お口の状態やライフスタイルによっては、どちらか一方の使用を優先する場合もあります。例えば、歯間の隙間が全体的に非常に狭い方はフロス中心、逆に全体的に広い方は歯間ブラシ中心となるでしょう。しかし、多くの方のお口の中には、歯間ブラシが適した場所とフロスが適した場所が混在しています。そのため、歯科医師としては、可能な限り併用をおすすめしています。
どちらか一方しか使えないという場合は、ご自身の歯の状態に合わせてより効果的な方を選ぶことになりますが、最適なケアのためには、定期的な歯科検診で歯科医師や歯科衛生士に相談し、ご自身のお口に合った清掃方法や道具の指導を受けることが重要です。
8.2 使う最適なタイミングは歯磨きの前?後?
歯間ブラシやフロスを使うタイミングについて、「歯磨きの前が良いのか、後が良いのか」というご質問もよく受けます。これについては様々な見解がありますが、一般的には「歯磨きの前」に使用することが推奨されることが多いです。
理由は、先に歯間ブラシやフロスで歯と歯の間の大きな汚れやプラークを取り除いておくことで、その後の歯磨きで使う歯磨き粉に含まれるフッ素などの薬用成分が、歯間部や歯と歯茎の境目まで行き渡りやすくなるためです。これにより、虫歯や歯周病の予防効果を高めることが期待できます。
一方で、「歯磨きの後」に使うことにもメリットはあります。歯磨きで落としきれなかった汚れを、歯間ブラシやフロスで確認しながら除去することができます。
どちらのタイミングが良いか、メリット・デメリットを簡単にまとめると以下のようになります。
| タイミング | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 歯磨きの前 |
|
|
| 歯磨きの後 |
|
|
日本歯科医師会などでも、歯磨きの前に歯間清掃を行うことを推奨する見解が見られます。しかし、最も重要なのは、順番にこだわりすぎることよりも、毎日欠かさず歯間清掃を行う習慣をつけることです。ご自身のライフスタイルや好みに合わせて、続けやすいタイミングで行うのが一番良いでしょう。もし迷うようでしたら、まずは「歯磨きの前」から試してみてはいかがでしょうか。
8.3 歯間ブラシやフロスで出血するけど大丈夫?歯科医師の見解
歯間ブラシやフロスを使い始めたばかりの頃や、時々使うと出血することがあり、心配になられる方も多いと思います。多くの場合、この出血は歯茎に炎症が起きているサイン(歯肉炎)です。
歯と歯の間や歯と歯茎の境目にプラークが溜まると、細菌が原因で歯茎が炎症を起こし、赤く腫れたり、少しの刺激で出血しやすい状態になります。このような状態で歯間ブラシやフロスを使用すると、炎症を起こしている部分に触れるため出血するのです。
「出血するから怖い」と歯間清掃をやめてしまうと、プラークがさらに蓄積し、炎症が悪化して歯周病へと進行してしまう可能性があります。実は、出血がある場合でも、正しい方法で丁寧に歯間清掃を続けることが重要です。適切なケアによってプラークが除去され、歯茎の炎症が改善してくると、徐々に出血は治まってきます。通常、1~2週間程度で改善が見られることが多いです。
ただし、以下のような場合は注意が必要です。自己判断せず、必ず歯科医師に相談してください。
- 強い痛みを伴う出血がある場合
- 正しいケアを続けていても、2週間以上出血が続く、または出血量が増える場合
- 歯間ブラシのサイズが明らかに大きすぎる、または無理やり挿入している場合
- フロスを力任せに歯茎に押し付けている場合
これらの場合は、歯肉炎が進行していたり、歯周病の可能性があったり、あるいは歯間ブラシのサイズや使い方が間違っていて歯茎を傷つけている可能性があります。歯科医院で診察を受け、原因を特定し、適切な治療や指導を受けるようにしましょう。
出血は、歯茎からの「助けて!」のサインと捉え、オーラルケアを見直すきっかけにしてください。
8.4 子供にも歯間ブラシやフロスは必要?
お子さんにも歯間ブラシやフロスによるケアは必要です。特に、乳歯の奥歯が生え揃い、歯と歯の間が接するようになると、歯ブラシだけでは汚れを落としきれなくなり、虫歯のリスクが高まります。
乳歯の虫歯は、痛みだけでなく、後に生えてくる永久歯の歯並びや歯質にも悪影響を与える可能性があるため、しっかりと予防することが大切です。
歯間ケアを開始する具体的な時期の目安としては、
- 乳歯の奥歯(第一乳臼歯や第二乳臼歯)が生えてきて、歯と歯が隣り合うようになったら
が一般的です。個人差がありますので、かかりつけの歯科医院で定期検診を受け、お子さんのお口の状態に合わせた開始時期やケア方法について相談するのが最も確実です。
子供向けの歯間清掃具としては、以下のようなものがあります。
- 子供用フロス(ホルダータイプ): 持ち手が付いていて、保護者の方が操作しやすい形状になっています。様々なフレーバー付きのものもあり、お子さんが楽しくケアを受け入れられるような工夫がされています。
- 細いサイズの歯間ブラシ: 永久歯が生え始め、歯と歯の間に少し隙間が出てきた場合などに使用することがあります。ただし、乳歯の隙間は狭いことが多いため、フロスが主体となることが多いです。
小さなお子さんが自分で歯間ケアを完璧に行うのは難しいため、保護者の方が仕上げ磨きの一環として、毎日行ってあげることが基本となります。嫌がるお子さんもいますが、無理強いせず、楽しい雰囲気を作ったり、上手にできたら褒めてあげたりしながら、少しずつ習慣づけていくことが大切です。
子供のうちから正しいオーラルケアの習慣を身につけることは、将来の健康な歯を維持するために非常に重要です。歯科医院での定期的なフッ素塗布やシーラントなどと併せて、ご家庭での歯間ケアもぜひ取り入れてください。
9. まとめ
歯間ブラシとフロスは、歯ブラシだけでは届かない歯と歯の間の汚れを落とすための重要なオーラルケア用品です。歯間ブラシは歯間の隙間が広い箇所に、フロスは狭い箇所に適しています。どちらか一方が優れているわけではなく、ご自身の歯並びや歯茎の状態、歯間の広さに合わせて最適なものを選ぶことが大切です。正しい使い方をマスターし、毎日の歯磨きにプラスすることで、虫歯や歯周病のリスクを効果的に減らすことができます。どちらを選ぶべきか迷う場合や、使い方に不安がある場合は、かかりつけの歯科医師に相談するのが最も確実です。小林製薬のこちらのホームページもあわせてお読みください。
矯正治療のご相談をご希望の方は、下記のボタンよりお気軽にご予約ください。
この記事の監修者

尾立 卓弥(おだち たくや)
医療法人札幌矯正歯科 理事長
宮の沢エミル矯正歯科 院長
北海道札幌市の矯正専門クリニック「宮の沢エミル矯正歯科」院長。
日本矯正歯科学会 認定医。