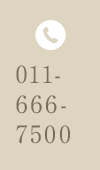矯正歯科で保険適用が認められる条件とは?対象疾患と費用を解説
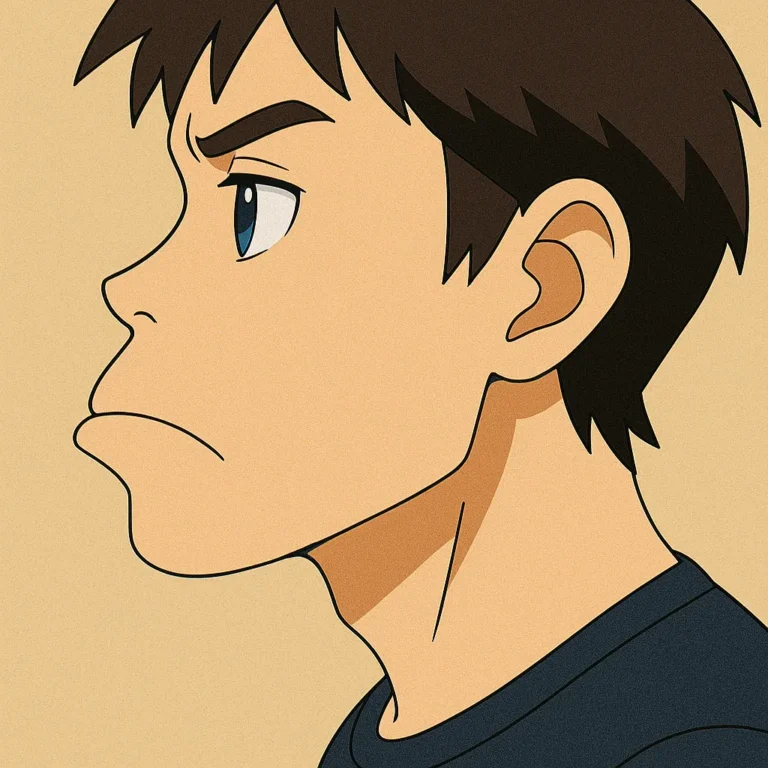
こんにちは。医療法人 札幌矯正歯科 宮の沢エミル矯正歯科、理事長の尾立卓弥です。矯正歯科治療は、基本的に健康保険が適用されず自費診療となります。しかし、国が定める特定の疾患や、顎の外科手術が必要な顎変形症と診断され、指定医療機関で治療を受ける場合は保険適用が可能です。この記事では、矯正歯科で保険適用が認められる詳しい条件、対象となる疾患、治療費の目安、注意点などを分かりやすく解説します。
1. 矯正歯科治療は原則として保険適用外
歯並びや噛み合わせを整える矯正歯科治療は、多くの方が関心を持つ治療ですが、原則として健康保険が適用されない「自由診療(自費診療)」となります。これは、日本の公的医療保険制度が、主に病気やケガといった医学的な必要性が高い治療を保障の対象としているためです。
矯正歯科治療は、虫歯や歯周病といった一般的な歯科疾患の治療とは異なり、多くの場合、審美的な改善(見た目を良くすること)を主目的とする側面が強いと判断されます。もちろん、噛み合わせの改善による咀嚼機能の回復や、歯並びの乱れが原因で起こる清掃不良の改善といった機能的な側面も重要ですが、現行の保険制度においては、「緊急性の高い病気の治療」とはみなされにくいのが現状です。
公的医療保険が適用される「保険診療」と、適用されない「自由診療」では、患者様の費用負担や受けられる治療内容に大きな違いがあります。矯正歯科治療を検討する上で、この違いを理解しておくことは非常に重要です。以下の表で、保険診療と自由診療の主な違いを整理してみましょう。
| 項目 | 保険診療 | 自由診療(自費診療) |
|---|---|---|
| 費用負担 | 医療費の一部(原則1割〜3割)を負担 | 医療費の全額(10割)を自己負担 |
| 治療内容・使用材料 | 国が定めた治療法・材料の範囲内に限定される | 制限がなく、新しい治療法や多様な材料・装置を選択可能 |
| 矯正歯科治療への適用 | 厚生労働省が定める特定の先天性疾患や、顎の外科手術が必要な顎変形症など、ごく限られた例外的なケースのみ | 一般的な矯正歯科治療(審美目的、機能改善目的を含む) |
このように、ほとんどの矯正歯科治療は自由診療に分類されるため、治療にかかる費用は高額になる傾向があります。治療を開始する前には、治療内容だけでなく、費用総額や支払い方法についてもしっかりと歯科医師に確認し、納得した上で進めることが大切です。
ただし、繰り返しになりますが、すべての矯正歯科治療が保険適用外というわけではありません。特定の条件を満たす場合には、例外的に健康保険が適用され、治療費の自己負担を軽減できる可能性があります。具体的にどのような疾患や状態が保険適用の対象となるのか、また、どのような手続きが必要なのかについては、この後の章で詳しく解説していきます。
2. 矯正歯科で保険適用が認められる条件
多くの方がご存知のように、一般的な歯並びの改善や審美目的の矯正歯科治療は、原則として公的医療保険の適用対象外(自費診療)となります。しかし、特定の条件を満たす場合には、例外的に保険が適用され、治療費の自己負担を軽減できる可能性があります。保険適用を受けるためには、非常に厳格な基準が設けられており、誰でも利用できるわけではありません。ここでは、矯正歯科治療で保険適用が認められるための具体的な3つの条件について詳しく解説します。
2.1 厚生労働省が定める特定の疾患であること
保険適用の最も重要な条件の一つは、厚生労働省が定めた特定の先天性疾患が原因で咬合異常(かみ合わせの異常)が生じていると診断されることです。「先天性」とは、生まれつき持っている疾患を指します。これらの疾患は、単に歯並びが悪いというだけでなく、顎骨の発育不全や形態異常を伴い、咀嚼(そしゃく)、嚥下(えんげ)、発音、呼吸といった口腔機能に深刻な支障をきたしている、または将来的にきたす可能性が高い場合に該当します。
対象となる疾患は多岐にわたりますが、代表的なものとしては唇顎口蓋裂(しんがくこうがいれつ)などが挙げられます。これらの疾患に起因する咬合異常の治療は、機能回復を主目的とするため、医療上の必要性が高いと判断され、保険適用の対象となります。ただし、最終的な診断と保険適用の判断は、専門医による精密な検査と診察に基づいて行われます。
どのような疾患が対象となるかについては、後の章「保険適用となる矯正歯科治療の対象疾患」で詳しくリストアップして解説します。
2.2 顎の外科手術が必要な顎変形症であること
もう一つの保険適用条件は、顎骨の大きさや形、位置関係に著しい不調和がある「顎変形症(がくへんけいしょう)」と診断され、かつ、その治療のために顎骨を切るなどの外科手術(顎矯正手術)が必要不可欠であると判断された場合です。顎変形症は、例えば上顎が極端に小さい、下顎が過度に大きい、または左右非対称であるなど、骨格的な問題が原因で重度の咬合異常や顔貌の変形を引き起こしている状態を指します。
この場合、歯を動かす矯正治療だけでは根本的な改善が難しく、顎骨の位置や形を修正する外科手術と、術前・術後の矯正治療を組み合わせた「外科的矯正治療」が必要となります。この一連の治療プロセス全体が、医療上の必要性が高いと認められ、保険適用の対象となります。
重要なのは、「顎変形症」と診断されても、外科手術を伴わない矯正治療のみで対応可能な場合は保険適用外となる点です。保険適用となるのは、あくまで矯正歯科医と口腔外科医が連携し、外科手術を前提とした治療計画が立てられた場合に限られます。顎変形症の診断基準や外科的矯正治療の流れについては、後の章で詳しく解説します。
2.3 指定された医療機関で治療を受けること
上記の疾患や顎変形症の条件を満たしていても、どの歯科医院でも保険適用で治療を受けられるわけではありません。保険適用となる矯正歯科治療は、厚生労働省地方厚生(支)局に届け出て認可された特定の医療機関でのみ実施可能です。これらの医療機関は、保険診療を行うための施設基準(設備、人員配置など)を満たしている必要があります。
具体的には、以下のいずれかの指定を受けている医療機関で治療を受ける必要があります。
2.3.1 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)
指定自立支援医療機関は、身体に障害のある方や特定の疾患を持つ方に対して、その障害を除去・軽減するための医療費の自己負担を軽減する「自立支援医療」を提供できる機関として、都道府県知事または指定都市の市長が指定した医療機関です。矯正歯科治療においては、主に厚生労働省が定める先天性疾患を持つ患者さん(主に18歳未満の「育成医療」対象者、または18歳以上の「更生医療」対象者)の矯正治療が対象となります。これらの機関は、先天性疾患に伴う複雑な咬合異常に対応できる専門性と設備を備えています。
2.3.2 顎口腔機能診断施設
顎口腔機能診断施設(がくこうくうきのうしんだんしせつ)は、顎変形症など、顎口腔系の機能異常に関する精密な診断や、外科的矯正治療を含む高度な治療計画の立案・実施を行う能力があると認められ、地方厚生(支)局長に届け出た医療機関です。主に、外科手術を伴う顎変形症の保険適用による矯正治療を行う際には、この指定を受けている医療機関(または連携する医療機関)での受診が必要となります。口腔外科との緊密な連携体制が整っていることが特徴です。
2.3.3 当院(医療法人 札幌矯正歯科)は指定された医療機関ではない
ここで重要な点をお伝えします。当院(医療法人 札幌矯正歯科)は、上記の「指定自立支援医療機関」および「顎口腔機能診断施設」のいずれの指定も受けておりません。したがって、当院で矯正歯科治療を受けられる場合、たとえ厚生労働省の定める疾患や顎変形症に該当する可能性があったとしても、保険適用による治療を行うことはできません。当院での矯正治療は、すべて自費診療となります。
もし、ご自身の症状が保険適用に該当する可能性があるとお考えの場合や、保険適用での治療を強く希望される場合は、必ず治療を開始する前に、受診を検討している医療機関が上記の指定を受けているかどうかをご確認ください。指定医療機関であるかどうかは、各医療機関に直接お問い合わせいただくか、お住まいの地域の地方厚生(支)局のウェブサイトなどで確認することができます。当院では、保険適用に関する一般的なご相談や、必要に応じて指定医療機関に関する情報提供は可能ですので、お気軽にご相談ください。
3. 保険適用となる矯正歯科治療の対象疾患
矯正歯科治療が保険適用となるのは、特定の条件を満たす場合に限られます。その中心となるのが、治療対象となる「疾患」です。具体的には、「厚生労働大臣が定める先天性疾患等」と「顎変形症(外科的矯正治療が必要な場合)」の2つのカテゴリーに大別されます。
3.1 厚生労働大臣が定める先天性疾患等
保険適用の対象となる第一のケースは、生まれつき(先天性)の特定の病気が原因で、咬合異常(かみ合わせの異常)が生じている場合です。これらの疾患は、厚生労働大臣によって定められており、多岐にわたります。単に歯並びが悪いというだけでは対象にならず、あくまで指定された先天性疾患に起因する咬合異常であることが必要です。治療を受けるためには、医師による該当疾患の診断が前提となります。
対象となる疾患は非常に多く、定期的に見直しも行われています。以下に、厚生労働省が定めている疾患の一部を例として挙げますが、これらが全てではありません。ご自身の状況が該当するかどうかは、専門の医療機関で相談することが重要です。
3.1.1 代表的な対象疾患の例
保険適用対象となる先天性疾患の中でも、比較的知られている、あるいは矯正歯科との関連が深い疾患の例をいくつかご紹介します。
- 唇顎口蓋裂(しんがくこうがいれつ):唇や上顎、口蓋(口の中の天井部分)が裂けた状態で生まれる疾患です。歯並びや顎の成長に大きな影響を与えることが多く、矯正治療が必要となる代表的な例です。
- ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む):片側の顔面や耳、顎骨の発育不全を特徴とする疾患群です。顔の非対称や咬合異常を引き起こします。
- 鎖骨頭蓋異骨症(さこつとうがいいこつしょう):鎖骨の低形成または無形成、頭蓋骨の縫合閉鎖遅延などを特徴とし、多数の過剰歯や萌出遅延など、歯や顎に特有の問題を伴うことがあります。
- ダウン症候群(21トリソミー):染色体異常による疾患で、低身長、特徴的な顔貌に加え、反対咬合(受け口)や開咬(前歯が噛み合わない)などの咬合異常を高頻度で伴います。
これらはあくまで一部であり、他にも多くの疾患が対象となります。厚生労働省が定める疾患リストは以下の通りです(令和6年4月1日現在)。
| 疾患名 |
|---|
| 唇顎口蓋裂 |
| ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。) |
| 鎖骨・頭蓋異骨症 |
| クルーゾン症候群 |
| トリチャーコリンズ症候群 |
| ピエールロバン症候群 |
| ダウン症候群 |
| ラッセルシルバー症候群 |
| ターナー症候群 |
| ベックウィズ・ヴィードマン症候群 |
| 尖頭合指症 |
| ロンベルグ症候群 |
| 先天性ミオパチー |
| 顔面半側肥大症 |
| エリス・ヴァン・クレベルト症候群 |
| 軟骨形成不全症 |
| 外胚葉異形成症 |
| 神経線維腫症 |
| 基底細胞母斑症候群 |
| ヌーナン症候群 |
| マルファン症候群 |
| プラダーウィリー症候群 |
| 顔面裂 |
| 大理石骨病 |
| 線維性骨異形成症 |
| CHARGE症候群 |
| 他、多数の先天性疾患 |
これらの疾患に該当し、かつ、それに起因する咬合異常が認められる場合に、矯正歯科治療が保険適用の対象となります。診断には専門的な知識が必要ですので、必ず指定医療機関でご相談ください。
3.2 顎変形症(外科的矯正治療が必要な場合)
保険適用の対象となるもう一つの大きなカテゴリーが「顎変形症(がくへんけいしょう)」です。これは、上顎骨または下顎骨、あるいはその両方の大きさや形、位置関係に著しい異常があり、顔貌(顔の形やバランス)の問題や、重度の咬合異常(受け口、出っ歯、開咬、顔の非対称など)を引き起こしている状態を指します。
重要な点は、顎変形症と診断されただけでは保険適用にはならず、その治療のために顎骨を切るなどの外科手術(顎矯正手術)を併用した矯正歯科治療(外科的矯正治療)が必要であると判断された場合に限り、手術前後の矯正歯科治療も含めて保険適用となるということです。つまり、手術を伴わない矯正治療のみで改善が見込めると判断された場合は、たとえ顎変形症の診断があったとしても保険適用外(自費診療)となります。
3.2.1 顎変形症の診断基準
顎変形症の診断は、単に見た目の印象だけで決まるものではありません。保険適用を前提とした診断には、「顎口腔機能診断施設」として指定された医療機関での精密な検査と評価が不可欠です。
具体的には、以下のような検査が行われ、総合的に判断されます。
- 問診:患者さんの主訴(最も困っていること)、既往歴、家族歴などを詳しく伺います。
- 口腔内診査:歯並び、かみ合わせの状態、歯周組織の状態などを詳細に確認します。
- 顔面写真・口腔内写真撮影:顔貌のバランスや口元の状態、歯並びを客観的に記録・評価します。
- 歯列模型検査:歯型を採取し、石膏模型を作成して、かみ合わせや歯の大きさ、顎のアーチ形態などを精密に分析します。
- レントゲン検査:
- パノラマレントゲン:顎全体や歯の状態を把握します。
- セファログラム(頭部X線規格写真):顔面や頭部の骨格的な形態、上下顎骨の位置関係、歯の傾斜角度などを計測・分析するための特殊なレントゲン写真です。顎変形症の診断において非常に重要な検査です。
- CT検査:必要に応じて、顎骨の形態や神経・血管の位置などを三次元的に詳しく調べるために行われます。
これらの検査結果をもとに、骨格的な不調和の程度、咬合異常の重症度、外科手術の必要性などを専門医が総合的に判断し、顎変形症であり、かつ外科的矯正治療が必要であると診断された場合に、保険適用の対象となります。
3.2.2 外科手術を伴う矯正治療の流れ
顎変形症で保険適用となる外科的矯正治療は、一般的な矯正治療とは異なり、外科手術を組み込んだ計画的な治療プロセスが必要です。治療期間も長くなる傾向があります。一般的な流れは以下の通りです。
- 術前矯正(じゅつぜんきょうせい):
まず、手術後に安定した良好なかみ合わせが得られるように、矯正装置(主にマルチブラケット装置)を用いて歯並びを整えます。手術で顎骨を動かした際に、上下の歯がしっかりと噛み合うように準備する期間です。この段階では一時的にかみ合わせが悪化するように見えることもありますが、手術後の良好な結果を得るためには重要なステップです。期間は通常1年~1年半程度です。
- 顎矯正手術(がくきょうせいしゅじゅつ):
術前矯正で歯並びがある程度整ったら、連携している口腔外科や形成外科で顎骨の手術を受けます。全身麻酔下で行われ、入院が必要です。手術では、計画に基づいて上顎骨や下顎骨、あるいはその両方を切って、正しい位置に移動させ、チタン製のプレートやネジなどで固定します。手術内容や術後の経過によりますが、入院期間は1~2週間程度が一般的です。
- 術後矯正(じゅつごきょうせい):
手術後、顎の骨が安定し、腫れがある程度引いてから、最終的なかみ合わせの調整と仕上げのための矯正治療を行います。手術によって大きく変化した骨格に合わせて、歯を微調整し、機能的にも審美的にも最適な状態を目指します。期間は通常半年~1年程度です。
- 保定(ほてい):
矯正装置を外した後、歯並びや顎の位置が後戻りするのを防ぐために、保定装置(リテーナー)を使用します。術後矯正が完了しても、骨や歯周組織が完全に安定するには時間がかかります。良好な治療結果を維持するために、医師の指示に従って長期間(通常2~3年以上)使用することが非常に重要です。
このように、外科的矯正治療は、矯正歯科医と口腔外科医(または形成外科医)との緊密な連携のもと、術前・術中・術後の管理を含めた長期的な治療計画が必要となります。
4. 保険適用された場合の矯正歯科治療の費用目安
矯正歯科治療は一般的に高額なイメージがありますが、厚生労働省が定める特定の疾患や顎変形症と診断され、指定医療機関で治療を受ける場合には健康保険が適用されます。保険適用となった場合、治療にかかる費用は自費診療と比較して大幅に抑えることが可能です。ただし、保険が適用されても自己負担がゼロになるわけではありません。ここでは、保険適用された場合の具体的な費用負担の仕組みや、負担をさらに軽減できる制度について詳しく解説します。
4.1 自己負担割合(原則3割)
日本の公的医療保険制度では、医療機関で保険診療を受けた場合、窓口での自己負担割合は原則として3割と定められています。これは、保険適用となる矯正歯科治療においても同様です。例えば、治療にかかった総医療費が100万円だった場合、窓口で支払う自己負担額は30万円となります。残りの7割は、加入している健康保険(協会けんぽ、組合健保、国民健康保険、共済組合など)から医療機関へ支払われます。
年齢によって自己負担割合が異なる場合があります(例:70歳以上75歳未満は2割、75歳以上は1割 ※現役並み所得者を除く)が、保険適用の矯正歯科治療を受ける患者さんの多くは、この原則3割負担が適用されるケースが一般的です。ご自身の正確な自己負担割合については、加入している健康保険組合や市区町村の窓口にご確認ください。
4.2 高額療養費制度の活用
保険適用の矯正歯科治療、特に外科手術を伴う顎変形症の治療などは、治療期間が長くなったり、入院が必要になったりすることで、月々の医療費が高額になる可能性があります。そのような場合に備えて、医療費の自己負担額が一定の上限額を超えた際に、その超えた分が払い戻される「高額療養費制度」があります。この制度を活用することで、家計への負担をさらに軽減できます。
4.2.1 高額療養費制度とは
高額療養費制度は、1ヶ月(月の初めから終わりまで)にかかった医療費の自己負担額(保険診療分のみ、入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外)が、年齢や所得区分に応じて定められた自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額が後から支給される制度です。矯正歯科の保険適用治療もこの制度の対象となります。
自己負担限度額は、年齢(70歳未満か、70歳以上か)と、被保険者の所得水準によって区分されています。以下は、一般的な70歳未満の方の所得区分と自己負担限度額の例です。
| 所得区分 | 適用区分 | 自己負担限度額(月額) | 多数回該当(※) |
|---|---|---|---|
| 年収約1,160万円~ 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 |
ア | 252,600円 + (総医療費 – 842,000円) × 1% | 140,100円 |
| 年収約770万円~約1,160万円 健保:標準報酬月額53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 |
イ | 167,400円 + (総医療費 – 558,000円) × 1% | 93,000円 |
| 年収約370万円~約770万円 健保:標準報酬月額28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 |
ウ | 80,100円 + (総医療費 – 267,000円) × 1% | 44,400円 |
| ~年収約370万円 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 |
エ | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税者 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※ 多数回該当とは、過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した月があった場合の4回目以降の限度額です。
※ 上記は一例であり、ご自身の正確な区分や限度額は、加入している公的医療保険にお問い合わせください。
この制度により、例えば区分「ウ」の方が1ヶ月に総医療費100万円(自己負担30万円)かかった場合でも、実際の負担額は「80,100円 + (1,000,000円 – 267,000円) × 1% = 87,430円」となり、差額の約21万円が払い戻されます(多数回該当でない場合)。
また、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示すれば、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることも可能です(マイナ保険証を利用し、情報提供に同意すれば認定証の提示は不要な場合があります)。
4.2.2 申請手続きについて
高額療養費の支給を受けるためには、原則としてご自身が加入している公的医療保険(健康保険組合、協会けんぽ、市区町村の国民健康保険窓口、共済組合など)への申請が必要です。多くの場合、診療月から数ヶ月後に加入保険者から申請書が送られてくるか、案内の通知があります。
申請には、医療機関から発行された領収書が必要になる場合がありますので、大切に保管しておきましょう。申請期限は、診療を受けた月の翌月初日から2年間です。手続きの詳細は、加入している保険者にご確認ください。
「限度額適用認定証」の交付を希望する場合も、同様に加入している保険者への事前申請が必要です。
4.3 医療費控除の対象について
年間の医療費負担が一定額を超えた場合、確定申告を行うことで所得税や住民税の還付・軽減を受けられる「医療費控除」という制度があります。保険適用で受けた矯正歯科治療の費用も、この医療費控除の対象となる可能性が高いです。
4.3.1 医療費控除の仕組み
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間に、自分自身や生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けられる制度です。
控除額の計算方法は以下の通りです。
医療費控除額 = (実際に支払った医療費の合計額 – 保険金などで補填される金額) – 10万円
※ その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%の金額となります。
※ 控除額の上限は200万円です。
この計算で算出された控除額を所得から差し引くことで、所得税が再計算され、納めすぎた税金が還付されたり、翌年の住民税が軽減されたりします。医療費控除を受けるためには、ご自身で確定申告を行う必要があります。
4.3.2 矯正歯科治療における医療費控除
保険適用となる矯正歯科治療は、「容貌を美化するための費用」ではなく、「病気の治療に必要な費用」とみなされるため、原則として医療費控除の対象となります。具体的には、厚生労働省が定める先天性疾患や、顎変形症の治療に伴う矯正歯科治療費が該当します。
医療費控除を申請する際には、支払った医療費の領収書が必要となります。また、税務署から求められた場合に提示できるよう、治療が医学的に必要であることを証明する医師の診断書を用意しておくと安心です(特に高額な場合)。診断書の発行については、治療を受けている歯科医師にご相談ください。
さらに、治療のために公共交通機関(電車、バスなど)を利用した場合の交通費も、医療費控除の対象に含めることができます(自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外)。いつ、誰が、どの医療機関へ、いくらかかったかを記録しておきましょう。
医療費控除は、生計を一にする家族の医療費を合算して申告できます。ご家族で他にも医療費がかかっている場合は、まとめて申告することで控除額が大きくなる可能性があります。
確定申告の時期は、例年2月16日から3月15日までです。申告方法など詳細は、国税庁のウェブサイトや最寄りの税務署でご確認ください。
5. 保険適用外(自費診療)の矯正歯科費用との比較
矯正歯科治療は、特定の疾患や顎変形症を除き、原則として自由診療(自費診療)となります。そのため、治療にかかる費用は全額自己負担となり、医療機関によって費用設定も異なります。ここでは、一般的な自費診療の矯正歯科費用と、保険適用の場合との違いについて詳しく解説します。
5.1 一般的な自費の矯正歯科費用相場
自費診療の矯正歯科費用は、いくつかの項目に分かれており、治療の段階ごと、あるいは月ごとに支払いが発生することが一般的です。近年では、治療開始から完了までの総額を提示する「トータルフィー制度(総額固定制)」を採用する歯科医院も増えています。トータルフィー制度の場合、治療期間が延びたり、追加の調整が必要になったりしても、原則として追加費用が発生しないため、費用計画が立てやすいというメリットがあります。
以下に、自費診療における一般的な費用の内訳と、おおよその相場を示します。ただし、これらはあくまで目安であり、地域や歯科医院、治療の難易度によって大きく変動します。
| 費用項目 | 内容 | 費用相場(目安) |
|---|---|---|
| 相談料(カウンセリング料) | 治療に関する相談、簡単な口腔内のチェック | 無料~1万円程度 |
| 検査・診断料 | レントゲン撮影、歯型採取、口腔内写真撮影、セファロ分析など精密検査と治療計画立案 | 3万円~7万円程度 |
| 矯正装置料 | ブラケット、ワイヤー、マウスピースなど、使用する矯正装置自体の費用 | 装置の種類により大きく異なる(下記参照) |
| 調整料(処置料) | 月1回程度の通院時にかかる、ワイヤー交換や装置の調整、クリーニングなどの費用 | 5千円~1万円程度(1回あたり) ※トータルフィー制度の場合は総額に含まれることが多い |
| 保定装置料(リテーナー料) | 治療完了後、歯並びの後戻りを防ぐための装置(リテーナー)の費用 | 3万円~6万円程度(上下) ※トータルフィー制度の場合は総額に含まれることが多い |
| 保定観察料 | 保定期間中の定期的なチェックにかかる費用 | 3千円~5千円程度(1回あたり) ※トータルフィー制度の場合は総額に含まれることが多い |
矯正装置料は、選択する装置の種類によって費用が大きく異なります。代表的な矯正装置とその費用相場は以下の通りです。
| 矯正装置の種類 | 特徴 | 費用相場(目安・全体矯正の場合) |
|---|---|---|
| ワイヤー矯正(表側・メタルブラケット) | 歯の表面に金属製のブラケットとワイヤーを装着する最も一般的な方法。 | 60万円~100万円程度 |
| ワイヤー矯正(表側・審美ブラケット) | 歯の表面に装着するが、ブラケットがセラミックやプラスチック製で目立ちにくい。 | 70万円~110万円程度 |
| ワイヤー矯正(裏側・舌側矯正) | 歯の裏側に装置を装着するため、外からはほとんど見えない。 | 100万円~150万円程度 |
| マウスピース矯正 | 透明なマウスピースを定期的に交換して歯を動かす。目立ちにくく、取り外し可能。 | 80万円~120万円程度 |
| 部分矯正 | 前歯など、気になる部分だけを対象とする矯正。治療期間が短く、費用も抑えられる傾向がある。 | 20万円~60万円程度(範囲による) |
これらの費用は、あくまで一般的な目安であり、個々の症例や歯科医院の方針によって大きく異なります。特に、抜歯の有無、治療期間、使用する補助的な装置(アンカースクリューなど)によっても費用は変動します。正確な費用については、必ず事前に歯科医院で見積もりを確認するようにしましょう。
5.2 保険適用と自費診療の費用の違い
保険適用となる矯正歯科治療と自費診療では、費用負担の仕組みが根本的に異なります。
保険適用の場合、医療費の原則3割が自己負担となり、さらに高額療養費制度を利用することで、月々の自己負担額に上限が設けられます。例えば、年収約370~約770万円の方の場合、1ヶ月の自己負担限度額は約8万円強(※)となります。外科手術を伴う顎変形症の治療などでは、入院費や手術費も保険適用となります。 (※所得区分や医療費総額によって変動します。詳しくはご加入の公的医療保険にお問い合わせください。)
一方、自費診療の場合は、治療費の全額が自己負担となります。前述の通り、治療方法や装置によって費用は大きく異なり、総額で数十万円から百数十万円になることが一般的です。ただし、自費診療では、最新の装置や目立ちにくい装置など、治療方法や装置の選択肢が広いというメリットがあります。また、支払い方法に関しても、デンタルローンやクレジットカード払い、院内分割払いなど、多様な選択肢が用意されていることが多いです。
| 項目 | 保険適用 | 自費診療 |
|---|---|---|
| 対象 | 厚生労働省が定める特定の疾患、顎変形症(外科手術併用)など | 審美目的の歯列矯正、保険適用対象外の症例全般 |
| 自己負担割合 | 原則3割(年齢・所得による) | 10割(全額自己負担) |
| 高額療養費制度 | 適用対象 | 適用対象外 |
| 医療費控除 | 適用対象 | 治療目的と認められれば適用対象(審美目的のみは対象外) |
| 治療方法・装置の選択肢 | 保険診療のルール内で制限あり(主にメタルブラケットのワイヤー矯正) | 制限が少なく、多様な選択肢(審美ブラケット、裏側矯正、マウスピース矯正など) |
| 費用の目安(総額) | 外科手術含む場合:50万円~80万円程度(3割負担) ※高額療養費制度適用前の概算 |
60万円~150万円程度(装置・範囲による) |
| 支払い方法 | 主に窓口での都度払い | 現金、クレジットカード、デンタルローン、院内分割など多様 |
このように、保険適用と自費診療では、費用負担だけでなく、治療の選択肢や支払い方法にも違いがあります。ご自身の症状が保険適用の対象となるか、どのような治療法を選択したいか、費用負担をどのように考えるかなどを総合的に考慮し、最適な治療法を選択することが重要です。
なお、自費診療であっても、治療目的(咀嚼機能の改善など)と診断されれば医療費控除の対象となる場合があります。詳しくは、次章以降の医療費控除に関する説明や、税務署、税理士にご確認ください。
6. 保険適用で矯正歯科治療が受けられる病院の探し方
矯正歯科治療で保険適用を受けるためには、厚生労働省が定める特定の疾患や顎変形症の診断に加え、治療を受ける医療機関が指定された施設である必要があります。ここでは、保険適用が可能な矯正歯科治療を提供している病院(指定医療機関)の探し方について、具体的な方法を解説します。
6.1 地方厚生局のウェブサイトを確認する
保険適用となる矯正歯科治療を行うことができるのは、「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)」または「顎口腔機能診断施設」として地方厚生(支)局に届け出を行い、認可された医療機関に限られます。これらの指定医療機関のリストは、各地方厚生(支)局のウェブサイトで公開されています。日本矯正歯科学会のホームページも確認方法が記載されていますので、そちらもご覧ください。
お住まいの地域を管轄する地方厚生(支)局のウェブサイトにアクセスし、「保険医療機関・保険薬局の指定等一覧」や「施設基準の届出受理状況一覧」といった項目の中から、該当する指定医療機関のリストを探します。リストには、医療機関名、所在地、電話番号などが記載されていることが一般的です。
ウェブサイトでの確認手順は以下の通りです。
- ご自身の住所地を管轄する地方厚生(支)局を特定します。(例:北海道厚生局、東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局、四国厚生支局、九州厚生局)
- 特定した地方厚生(支)局の公式ウェブサイトにアクセスします。検索エンジンで「(地域名)厚生局」と検索すると見つけやすいでしょう。
- ウェブサイト内で「保険医療機関」や「施設基準」に関連するメニューを探します。サイト構成は各厚生局で異なりますが、「指導監査・届出関係」や「保険医療機関・保険薬局の方へ」といったセクションに含まれていることが多いです。
- 「指定自立支援医療機関(育成・更生医療)」および「顎口腔機能診断施設」のリスト(一覧)を探し、PDFやExcelファイルなどでダウンロードまたは閲覧します。
- リストの中から、通院可能な範囲にある医療機関を探します。
以下に、各地方厚生(支)局の管轄地域を示します。ウェブサイトを検索する際の参考にしてください。
| 地方厚生(支)局名 | 管轄都道府県 |
|---|---|
| 北海道厚生局 | 北海道 |
| 東北厚生局 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
| 関東信越厚生局 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 |
| 東海北陸厚生局 | 富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
| 近畿厚生局 | 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
| 中国四国厚生局 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
| 四国厚生支局 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
| 九州厚生局 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
注意点として、ウェブサイトの情報は常に最新とは限りません。指定状況が変更されている可能性もあるため、リストで見つけた医療機関を受診する前には、必ず電話などで直接問い合わせを行い、現在も保険適用の矯正歯科治療を行っているか、また、ご自身の症状が受け入れ可能かを確認するようにしましょう。
6.2 かかりつけ医や地域歯科医師会に相談する
地方厚生局のウェブサイトでの検索が難しい場合や、より身近な情報源を活用したい場合は、現在通院しているかかりつけの歯科医師に相談するのも有効な方法です。
かかりつけの歯科医師が矯正歯科治療の保険適用について詳しい知識を持っている場合や、地域の指定医療機関に関する情報を持っている可能性があります。また、信頼できる専門医を紹介してもらえることも期待できます。ご自身の症状や保険適用を希望している旨を具体的に伝え、相談してみましょう。
さらに、お住まいの地域の「歯科医師会」に問い合わせるという方法もあります。各都道府県や市区町村には歯科医師会があり、地域の歯科医療に関する情報提供や相談窓口を設けている場合があります。歯科医師会のウェブサイトを確認したり、電話で問い合わせたりすることで、保険適用可能な矯正歯科治療を行っている医療機関の情報が得られるかもしれません。
相談する際のポイントとしては、以下の点が挙げられます。
- ご自身の症状(先天性疾患の診断名や、顎変形症の疑いなど)を可能な限り正確に伝える。
- 保険適用での矯正歯科治療を希望していることを明確に伝える。
- 通院可能なエリアを伝える。
これらの方法を組み合わせることで、ご自身の状況に合った、保険適用で矯正歯科治療が受けられる医療機関を見つけやすくなります。指定医療機関は限られているため、根気強く探すことが重要です。
7. 矯正歯科の保険適用に関する注意点
矯正歯科治療が保険適用となるケースは、患者さんにとって費用負担が軽減される大きなメリットがあります。しかし、保険適用で治療を受ける際には、事前に知っておくべきいくつかの注意点が存在します。これらの点を理解しておかないと、期待していた治療内容と異なったり、手続きに戸惑ったりする可能性があります。ここでは、保険適用で矯正歯科治療を受ける際の主な注意点を解説します。
7.1 治療方法や装置の選択肢
保険適用の矯正歯科治療では、使用できる治療方法や矯正装置の種類に制限があることが最も大きな注意点の一つです。自費診療(自由診療)では、患者さんの希望やライフスタイルに合わせて、目立ちにくい装置や最新の治療法を選択できますが、保険診療の場合は異なります。
具体的には、保険適用で主に使用されるのは、金属製のマルチブラケット装置(ワイヤー矯正)です。これは、歯の表面に金属製のブラケットを取り付け、ワイヤーを通して歯を動かす、最も標準的な矯正装置です。
一方で、以下のような審美性の高い装置や特定の治療法は、原則として保険適用外となります。
- セラミックブラケットやプラスチックブラケット(歯の色に近い、目立ちにくいブラケット)
- マウスピース型矯正装置(インビザラインなど)
- 舌側矯正(歯の裏側に装置をつける矯正)
- 部分矯正(気になる部分だけを治療する矯正)
- アンカースクリュー(歯科矯正用アンカースクリュー)を用いた複雑な歯の移動(一部、顎変形症治療で併用される場合はありますが、単独では適用外となることが多い)
このように、保険適用の範囲内で治療を進める場合、見た目の審美性に関する選択肢は限られることを理解しておく必要があります。もし、目立ちにくい装置を希望される場合は、自費診療を選択するか、担当医とよく相談することが重要です。また、治療計画の自由度も自費診療に比べて低い場合があります。
7.2 治療期間について
保険適用となる矯正歯科治療、特に顎変形症で外科手術を伴う場合、治療期間が長くなる傾向があります。これは、単に歯並びを整えるだけでなく、顎の骨格的な問題を外科手術によって改善し、その前後で矯正治療を行う必要があるためです。
一般的な自費診療による矯正治療の期間は、症例にもよりますが、おおむね1年半から3年程度です。しかし、顎変形症の保険適用治療では、以下のステップを踏むため、トータルで3年以上、場合によっては4年、5年とかかるケースも少なくありません。
- 術前矯正:外科手術で顎の骨を正しい位置に動かした際に、上下の歯が適切に噛み合うように、手術前に歯並びを整える期間です。通常1年~2年程度かかります。
- 外科手術:顎の骨を切って移動させ、プレートなどで固定する手術です。入院が必要となります(通常1~2週間程度)。
- 術後矯正:手術後の顎の位置に合わせて、最終的な噛み合わせを調整する期間です。通常半年~1年半程度かかります。
- 保定期間:治療によって動かした歯や顎の位置が後戻りしないように、リテーナー(保定装置)を使用する期間です。
先天性疾患の場合も、顎の成長や他の疾患との兼ね合いを見ながら治療を進めるため、治療期間が長くなることがあります。治療が長期にわたる可能性を考慮し、通院の継続やモチベーションの維持について、事前に心構えをしておくことが大切です。
7.3 診断書や必要な書類
矯正歯科治療で保険適用を受けるためには、定められた手続きに従い、必要な書類を準備・提出する必要があります。単に治療を受けたいと希望するだけでは保険は適用されません。
まず、保険適用対象となる厚生労働省指定の先天性疾患や顎変形症であるという正式な診断書が不可欠です。この診断は、どの歯科医師でも行えるわけではなく、「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)」や「顎口腔機能診断施設」として認定された医療機関の担当医が行う必要があります。
以下に、保険適用の手続きや関連制度の利用において、一般的に必要となる可能性のある書類の例を挙げます。
| 目的 | 必要となる可能性のある主な書類 | 入手・提出先(例) |
|---|---|---|
| 保険適用の診断 | 診断書(指定疾患・顎変形症) | 指定医療機関、顎口腔機能診断施設 |
| 外科手術(顎変形症) | 紹介状、検査結果、手術同意書など | 矯正歯科、口腔外科 |
| 高額療養費制度の申請 | 保険証、領収書、申請書、マイナンバー関連書類、振込先口座情報など | 加入している健康保険組合、協会けんぽ、市区町村の国民健康保険窓口 |
| 医療費控除の申請 | 医療費控除の明細書(領収書に基づき作成)、確定申告書、源泉徴収票、マイナンバー関連書類など | 税務署(確定申告) |
| 自立支援医療(育成医療・更生医療)の申請 | 申請書、診断書(指定様式)、世帯の所得状況がわかる書類、保険証、マイナンバー関連書類など | お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口 |
これらの書類は、治療内容や利用する制度によって異なります。また、申請手続きは複雑に感じられる場合もあります。どの書類がいつ、どこで必要なのかについては、治療を受ける医療機関の担当医やスタッフ、または各制度の窓口に必ず確認するようにしましょう。スムーズに手続きを進めるためには、事前の情報収集と準備が重要です。
特に、高額療養費制度や医療費控除は、保険適用であっても自己負担額が高額になった場合に活用できる重要な制度です。領収書などは必ず保管し、申請方法を確認しておきましょう。
8. まとめ
矯正歯科治療は、基本的に自由診療となり健康保険は適用されません。しかし、厚生労働省が定める特定の先天性疾患をお持ちの場合や、顎の外科手術が必要となる顎変形症と診断され、指定自立支援医療機関などの指定された医療機関で治療を受ける場合には、例外的に保険適用が認められます。保険適用となれば、治療費の自己負担は原則3割となり、高額療養費制度や医療費控除の対象にもなり得ます。ご自身の症状が保険適用の条件に該当するかどうか、まずは専門の歯科医師に相談し、正確な診断を受けることが重要です。
矯正治療のご相談をご希望の方は、下記のボタンよりお気軽にご予約ください。
この記事の監修者

尾立 卓弥(おだち たくや)
医療法人札幌矯正歯科 理事長
宮の沢エミル矯正歯科 院長
北海道札幌市の矯正専門クリニック「宮の沢エミル矯正歯科」院長。
日本矯正歯科学会 認定医。