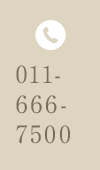歯並びがいいに共通する7つの特徴とは?生まれつき綺麗なメリットは?
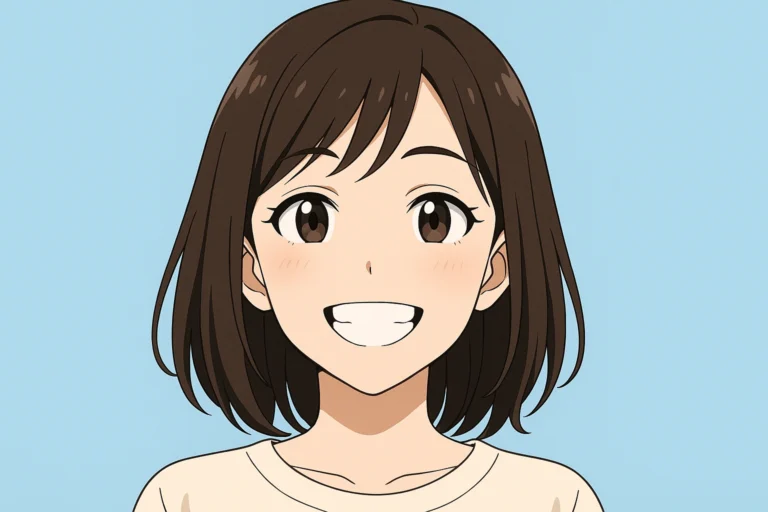
こんにちは。医療法人 札幌矯正歯科 宮の沢エミル矯正歯科の理事長の尾立卓弥です。札幌で矯正歯科を検討中の方は、ぜひ医療法人 札幌矯正歯科 宮の沢エミル矯正歯科でご相談ください。「歯並びがいい人」に憧れはありませんか?この記事では、美しい歯並びに共通する7つの特徴から、生まれつき綺麗なことによる虫歯予防などのメリット、ご自身でできるセルフチェック方法までを専門家が解説します。歯並びは遺伝だけでなく、口呼吸などの生活習慣も大きく影響しますが、今からでも歯科矯正などで整えることは可能です。理想の笑顔と健康を手に入れるための知識を深め、あなたの口元への自信につなげましょう。
1. 歯並びがいい人に共通する7つの特徴
「歯並びがいい」と一言で言っても、具体的にどのような状態を指すのかご存知でしょうか。単に歯がまっすぐ並んでいるだけでなく、専門的な観点から見るといくつかの明確な基準が存在します。ここでは、歯科医師も認める「歯並びがいい人」に共通する7つの特徴を詳しく解説します。ご自身の歯並びと比較しながらチェックしてみてください。
1.1 特徴1 上下の歯が正しく噛み合っている
歯並びの良し悪しを判断する上で最も重要なのが「正しい噛み合わせ(正常咬合)」です。 見た目が綺麗でも、噛み合わせが悪いと食事や健康に影響を及ぼす可能性があります。理想的な噛み合わせには、いくつかのポイントがあります。
| チェック項目 | 詳細な説明 |
|---|---|
| 前歯の重なり | 奥歯で噛んだとき、上の前歯が下の前歯に2~3mm程度かぶさっている状態が理想的です。 この重なりが深すぎる「過蓋咬合」や、逆に前歯が噛み合わない「開咬」は不正咬合に分類されます。 |
| 前歯の前後関係 | 上の前歯が下の前歯より2~3mmほど前に出ているのが正常な状態です。 これ以上出ていると「上顎前突(出っ歯)」、下の歯が前に出ていると「下顎前突(受け口)」となります。 |
| 奥歯の関係 | 上下の奥歯の山と谷が、ジグザグとしっかり噛み合っていることが重要です。 通常、上の歯1本に対して下の歯2本が噛み合う「1歯対2歯咬合」という状態が理想とされています。 |
これらの条件を満たすことで、食べ物を効率よく噛み砕けるだけでなく、特定の歯に過度な負担がかかるのを防ぎ、顎関節への負担も軽減します。
1.2 特徴2 歯のアーチが綺麗なU字型
歯並びを上から見たとき、歯は弓なりのカーブを描いており、これを「歯のアーチ(歯列弓)」と呼びます。このアーチが、きれいで滑らかな「U字型」を描いていることが理想的な歯並びの条件です。 U字型のアーチは、歯が並ぶための十分なスペースがあり、噛み合わせが安定しやすいという特徴があります。
一方で、アーチがV字型に尖っていたり、狭くなっていたりする「狭窄歯列弓」の場合、歯が並ぶスペースが不足し、歯が重なり合う「叢生(そうせい)」や出っ歯の原因となりやすいです。
1.3 特徴3 顔の中心と歯の中心線が揃っている
顔全体のバランスを見る上で重要なのが「正中線(せいちゅうせん)」の一致です。正中線とは、顔の真ん中を通る線のことで、「顔の中心線」「上の前歯の中心」「下の前歯の中心」の3つが一直線に揃っている状態が理想的です。
鏡を見て「イー」と口を横に広げたときに、ご自身の正中線が揃っているか確認してみてください。多少のズレは多くの人に見られますが、2mm以上ずれていると、顔が歪んでいるような印象を与えてしまうことがあります。 このズレは、噛み合わせのバランスの乱れや、顎への負担につながる可能性もあります。
1.4 特徴4 横顔のEラインが整っている
横顔の美しさを評価する基準として「Eライン(エステティックライン)」があります。これは、鼻の先端と顎の先端を直線で結んだラインのことで、理想的な横顔では、唇がこのラインに触れるか、少し内側にある状態とされています。
Eラインはもともと欧米人の骨格を基準に提唱されたものですが、日本人の場合でも、下唇がEライン上、上唇が少し内側にあるのが美しいとされています。 出っ歯や口ゴボ(上下の顎が前に出ている状態)の場合、唇がEラインから大きくはみ出してしまい、バランスが崩れて見えがちです。整ったEラインは、美しい歯並びとバランスの取れた骨格の証と言えるでしょう。
1.5 特徴5 歯と歯の間に隙間や重なりがない
全ての永久歯(親知らずを除く28本)が、ねじれたり重なったりすることなく、歯と歯の間に適切な隙間なくきれいに並んでいる状態も、良い歯並びの重要な特徴です。 歯が重なり合っている「叢生(八重歯など)」や、歯と歯の間に隙間がある「空隙歯列(すきっ歯)」は、見た目の問題だけでなく、機能的なデメリットも多くあります。
例えば、歯が重なっている部分は歯ブラシが届きにくく、食べかすや歯垢が溜まりやすいため、虫歯や歯周病のリスクが高まります。 また、すきっ歯は食べ物が挟まりやすいだけでなく、空気が漏れて発音がしにくくなる原因にもなります。
1.6 特徴6 唇が自然に閉じられる
意識的に力を入れなくても、リラックスした状態で上下の唇が自然に閉じられることは、歯並びが良い証拠の一つです。出っ歯などで前歯が前方に突出していると、唇を閉じる際に下顎の先に力が入ってしまい、「梅干しジワ」と呼ばれるシワができることがあります。
口が自然に閉じられないと、無意識のうちに口呼吸になりがちです。 口呼吸は、口腔内を乾燥させ、唾液の持つ殺菌作用や自浄作用を低下させるため、虫歯や歯周病、口臭の悪化といった様々なトラブルを引き起こす原因となります。
1.7 特徴7 笑った時に上の歯茎が見えすぎない
笑顔の美しさを左右する要素として、笑ったときの歯茎の見え方があります。一般的に、笑った際に上の歯茎が見える量が3mm未満である状態が、審美的にバランスが良いとされています。
これ以上歯茎が見える状態は「ガミースマイル」と呼ばれます。 ガミースマイルは病気ではありませんが、骨格や歯の生え方、上唇の筋肉の発達などが原因で起こり、コンプレックスに感じる方も少なくありません。 歯茎の見え方が適度であることは、上品で魅力的な笑顔の条件と言えるでしょう。
2. 歯並びが生まれつき綺麗なことによる5つのメリット
歯並びが整っていることは、単に見た目が美しいだけでなく、心身の健康において数多くの恩恵をもたらします。生まれつき歯並びが綺麗な人は、日々の生活の中で意識せずとも、これから挙げるようなメリットを享受しているのです。ここでは、整った歯並びがもたらす5つの具体的なメリットについて、詳しく解説していきます。
2.1 メリット1 虫歯や歯周病のリスクが低い
綺麗な歯並びの最大のメリットの一つは、虫歯や歯周病といった口腔トラブルのリスクを大幅に低減できることです。 歯が重なり合っていたり、不規則に生えていたりすると、歯ブラシの毛先が届きにくい場所ができてしまいます。 そうした箇所には食べ物のカスや歯垢(プラーク)が溜まりやすく、虫歯菌や歯周病菌の温床となってしまうのです。 一方で、歯並びが整っていると、歯と歯の間や歯と歯茎の境目まで、隅々までしっかりと歯ブラシが届きます。 そのため、毎日のセルフケアで効率的に汚れを除去でき、口腔内を清潔に保ちやすいのです。 結果として、虫歯や歯周病の発症リスクを根本的に抑えることができます。
2.2 メリット2 食べ物をしっかり噛めて消化を助ける
正しい歯並びは、上下の歯が正しく噛み合うことを意味します。これにより、食事の際に食べ物を効率的に噛み砕き、消化を助けるという非常に重要な役割を果たします。 私たちの消化活動は、口の中で食べ物を咀嚼することから始まります。 食べ物を細かく噛み砕くことで、唾液に含まれる消化酵素(アミラーゼ)と混ざり合い、胃腸での分解や吸収がスムーズになるのです。 歯並びが悪いと、うまく噛み切れない、すり潰せないといった問題が生じ、食べ物が大きな塊のまま食道を通って胃に送られてしまいます。 これは胃腸に大きな負担をかけるだけでなく、栄養素の吸収効率を低下させる原因にもなりかねません。
| 項目 | 綺麗な歯並び(良い噛み合わせ) | 悪い歯並び(悪い噛み合わせ) |
|---|---|---|
| 咀嚼効率 | 食べ物を効率良く細かく砕ける | 食べ物を十分に砕けず、大きな塊で飲み込みがちになる |
| 唾液の分泌 | 咀嚼回数が増え、唾液の分泌が促進される | 咀嚼回数が少なく、唾液の分泌が不十分になりがち |
| 消化器官への負担 | 消化しやすく、胃腸への負担が少ない | 未消化の食べ物が胃腸に負担をかけ、消化不良の原因となることがある |
| 栄養吸収 | 栄養素が効率的に吸収される | 栄養素の吸収効率が低下する可能性がある |
2.3 メリット3 発音がはっきりして滑舌が良くなる
言葉を明瞭に発音するためには、歯、舌、唇の連携が不可欠であり、整った歯並びは滑舌の良さに大きく貢献します。 例えば、「サ行」や「タ行」などの特定の音は、舌を上の前歯の裏側に正しく当てることや、歯と歯の間から息が漏れないようにすることで発音されます。 しかし、すきっ歯(空隙歯列)の場合は息が漏れやすく、出っ歯(上顎前突)や受け口(下顎前突)の場合は舌の動きが制限されてしまい、発音が不明瞭になることがあります。 歯並びが整っていると、舌や唇をスムーズに動かすことができるため、はっきりとした聞き取りやすい発音が可能になり、円滑なコミュニケーションをサポートします。
2.4 メリット4 顔全体のバランスが整う
歯並びは口元だけでなく、顔全体の印象やバランスにも影響を与えます。 正しい噛み合わせは、顎の骨や顔周りの筋肉の正常な発達を促し、左右対称で均整の取れた顔立ちにつながります。 特に、横顔の美しさを評価する指標として「Eライン(エステティックライン)」があります。 これは鼻の先端と顎の先端を結んだ直線のことで、理想的な横顔では、唇がこのライン上、もしくは少し内側に収まるとされています。 出っ歯などで口元が前に突出していると、唇がEラインを大きくはみ出してしまい、バランスが崩れた印象を与えることがあります。 歯並びが整うことで、このEラインが美しくなり、知的で洗練された横顔の印象を与えます。
2.5 メリット5 笑顔に自信が持てて第一印象が良くなる
整った白い歯が見える美しい笑顔は、清潔感や健康的なイメージを与え、第一印象を格段に良くします。 歯並びにコンプレックスがあると、人前で話すことや笑うことに躊躇してしまい、口元を手で隠すなどの仕草につながることがあります。 このような心理的なブレーキは、コミュニケーションにおいて消極的な印象を与えかねません。 一方で、生まれつき歯並びが綺麗だと、口元を気にすることなく自然で美しい笑顔を見せることができます。 自信に満ちた笑顔は、周囲に明るくポジティブな印象を与え、プライベートやビジネスシーンにおける人間関係の構築にも良い影響をもたらすでしょう。
3. あなたの歯並-びは良い?簡単なセルフチェック方法
ご自身の歯並びが良いのか悪いのか、気になったことはありませんか?ここでは、鏡やご自身の指などを使って、ご自宅で簡単にできる歯並びのセルフチェック方法をご紹介します。いくつかのポイントを確認することで、ご自身の歯並びの状態を大まかに把握することができます。ただし、これはあくまで簡易的なチェックであり、正確な診断は歯科医師にしかできません。気になる点があれば、ぜひ一度、矯正歯科などの専門医に相談してみましょう。
3.1 鏡で確認!見た目のバランスをチェックする5項目
まずは鏡の前に立ち、リラックスした状態で口元や歯の状態を観察してみましょう。「イー」と口を横に開くと確認しやすくなります。
| チェック項目 | チェック方法 | 理想的な状態 |
|---|---|---|
| 1. 顔と歯の中心線(正中線) | 顔の中心(眉間から鼻先を通る線)と、上下の前歯の真ん中の線が一直線に並んでいるかを確認します。 | 顔の中心線と上下の歯の中心線が、ほぼ一直線に揃っている状態です。[8, 20] |
| 2. 歯の重なりと隙間 | 歯と歯が重なってガタガタしている部分や、逆に歯と歯の間に隙間(すきっ歯)がないかを確認します。 | 歯が重なったり隙間が空いたりすることなく、綺麗なアーチ状に隣り合って並んでいる状態です。[1] |
| 3. 噛み合わせの深さ | 軽く噛んだ時に、上の前歯が下の前歯にどのくらい覆いかぶさっているかを確認します。 | 上の前歯が下の前歯の先端から2〜3mm程度覆っている状態が理想的です。[18, 23] 深すぎたり(過蓋咬合)、全く噛み合っていなかったり(開咬)するのは注意が必要です。[6, 18] |
| 4. 笑った時の歯茎の見え方 | 笑顔を作った時に、上の歯茎がどれくらい見えるかを確認します。 | 笑った時に上の歯茎がわずかに見える、またはほとんど見えない状態が一般的です。3mm以上見える場合は「ガミースマイル」の可能性があります。 |
| 5. 歯並びのアーチ | 口を大きく開けて、上と下の歯並び全体の形を確認します。 | 歯並び全体が、綺麗なU字型のアーチ(歯列弓)を描いているのが理想です。[6] V字型や台形になっている場合は注意が必要です。[6] |
3.2 横顔でわかるEラインのチェック
Eライン(エステティックライン)は、横顔の美しさの基準の一つです。[7] ご自身の横顔をチェックしてみましょう。
3.2.1 チェック方法
人差し指や定規などのまっすぐなものを、鼻先と顎の先端に軽く当てます。[3, 7] 鏡で横から見るか、スマートフォンで横顔の写真を撮ると確認しやすくなります。
3.2.2 理想的な状態
指や定規に上下の唇が軽く触れるか、少し内側にある状態が理想的なEラインとされています。[3, 9] もし唇が強く押し付けられたり、大きく前に出ていたりする場合(口ゴボ)、歯並びが原因である可能性があります。[9]
3.3 機能面から見る3つのチェックポイント
見た目だけでなく、歯が持つ「機能」が正しく果たせているかも重要なチェックポイントです。日常生活の中で、以下のような点に心当たりがないか確認してみましょう。
3.3.1 1. 噛み合わせのチェック
食べ物を正しく噛み砕けているか、顎に負担がかかっていないかを確認します。割り箸を1本用意し、左右の奥歯で同時に噛んでみてください。[16] 割り箸が水平にならずに傾いたり、片方だけが先に当たってガタガタしたりする場合は、噛み合わせがズレている可能性があります。[19]
3.3.2 2. 滑舌・発音のチェック
歯並びは発音にも影響を与えます。特に「サ行」「タ行」「ラ行」などが言いにくい、発音の際に息が漏れる感じがするといった場合、歯の隙間や噛み合わせが原因となっていることがあります。
3.3.3 3. 咀嚼(そしゃく)のチェック
食事の際に、無意識に片方の歯ばかりで噛んでいないでしょうか。[4] また、硬いものが噛みにくい、食べ物が歯によく挟まるといったことも、歯並びや噛み合わせの問題を示唆するサインです。
3.4 セルフチェックの結果、気になる点があれば専門家へ
これらのセルフチェックで一つでも当てはまる項目があったからといって、必ずしもすぐに治療が必要というわけではありません。しかし、複数の項目に当てはまる場合や、ご自身で少しでも気になる点がある場合は、一度矯正歯科の専門医に相談することをおすすめします。専門家による精密な検査と診断を受けることで、ご自身の歯並びの現状を正確に把握し、必要であれば適切な治療法について知ることができます。
4. 歯並びは生まれつきで決まる?遺伝と生活習慣の関係
「自分の歯並びが悪いのは、親からの遺伝だから仕方ない」と諦めていませんか?確かに、歯並びの形成には遺伝的な要因が関係していますが、歯並びの良し悪しがすべて遺伝だけで決まるわけではありません。 実は、子どもの頃の何気ない癖や日々の生活習慣が、歯並びに大きな影響を与えているケースが非常に多いのです。 ここでは、歯並びに影響する遺伝的な要因と、特に注意したい後天的な生活習慣について詳しく解説します。
4.1 歯並びに影響する遺伝的な要因
親から子へ顔つきや体格が似るように、歯並びに関連する骨格的な特徴も遺伝します。 具体的には、以下のような要素が遺伝によって影響を受けやすいと言われています。
- 顎の骨の大きさや形: 歯が並ぶ土台となる顎の骨の大きさや形は、遺伝の影響を強く受けます。 例えば、顎が小さい骨格が遺伝した場合、歯が並ぶためのスペースが不足し、歯が重なり合って生える「叢生(そうせい)」、いわゆるガタガタの歯並びになる可能性が高まります。
- 歯の大きさや形、数: 歯そのものの大きさや形も遺伝的要因の一つです。顎の大きさと歯の大きさのバランスが取れていないと、歯並びが乱れる原因となります。 例えば、顎は小さいのに歯が大きい場合や、その逆の場合も歯並びに影響します。
- 骨格的な噛み合わせ: 上顎が前に出ている「上顎前突(出っ歯)」や、下顎が前に出ている「下顎前突(受け口)」といった骨格的な特徴も遺伝しやすい傾向にあります。
ただし、これらの遺伝的要因を持っていたとしても、必ずしも歯並びが悪くなるとは限りません。後天的な要因が加わることで、初めて歯並びの乱れとして現れることが多いのです。
4.2 歯並びを悪くする後天的な癖や習慣
歯並びは、唇や頬、舌といった口周りの筋肉の力のバランスによって保たれています。 しかし、日常の些細な癖によってそのバランスが崩れると、歯が少しずつ動いてしまい、歯並びの乱れにつながります。 特に、骨や筋肉がまだ柔らかい成長期の子どもは、癖の影響を受けやすいため注意が必要です。 以下に挙げる癖は無意識に行っていることが多く、長期間続くことで歯並びや顎の成長に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
4.2.1 口呼吸
本来、呼吸は鼻で行うのが正常ですが、アレルギー性鼻炎などで鼻が詰まっていたり、口をぽかんと開ける癖があったりすると口呼吸になりがちです。 口呼吸が習慣になると、以下のような影響で歯並びが悪くなるリスクが高まります。
- 口周りの筋肉の緩み: 口が常に開いている状態だと、口の周りを囲む筋肉(口輪筋)が緩み、歯を外側から支える力が弱まります。 その結果、舌が歯を内側から押す力に負けて、出っ歯(上顎前突)などを引き起こしやすくなります。
- 舌の位置の低下(低位舌): 鼻呼吸の場合、舌は上顎の定位置(スポット)に収まっていますが、口呼吸では舌の位置が下がりやすくなります(低位舌)。 舌が上顎を内側から押し広げる役割を果たせなくなるため、上顎の歯列が狭くなる「狭窄歯列弓」や、奥歯で噛んでも前歯が閉じない「開咬(かいこう)」の原因となります。
- 顔の骨格への影響: 長期的な口呼吸は、顎の成長にも影響を与え、「アデノイド顔貌」と呼ばれる面長な顔つきになる可能性も指摘されています。
4.2.2 指しゃぶり
指しゃぶりは乳幼児期に見られる自然な行為ですが、4歳や5歳を過ぎても続いている場合は注意が必要です。 指を吸う力が継続的に前歯にかかることで、以下のような歯並びの問題を引き起こす可能性があります。
- 出っ歯(上顎前突): 指で上の前歯を前方に押し出し、下の前歯を内側に倒す力がかかるため、出っ歯になりやすくなります。
- 開咬(オープンバイト): 指が上下の前歯の間にあることで、奥歯を噛み合わせても前歯が閉じない状態になることがあります。
一般的に3歳頃までには自然に落ち着くことが多いですが、長引く場合は小児歯科などで相談することも一つの方法です。歯並びについては日本矯正歯科学会のホームページもご覧ください。
4.2.3 舌で歯を押す癖
無意識に舌で前歯の裏側を押したり、食べ物を飲み込むときに舌を突き出したりする癖を「舌癖(ぜつへき)」と呼びます。 人は1日に約1500回も飲み込み動作(嚥下)を行っているとされ、その度に舌で歯を押していると、歯並びに大きな影響を及ぼします。
- すきっ歯(空隙歯列): 舌で前歯を押し続けることで、歯と歯の間に隙間ができてしまうことがあります。
- 出っ歯(上顎前突): 上の前歯を押す癖があると、出っ歯の原因になります。
- 開咬(オープンバイト): 飲み込むときに舌を上下の歯の間に挟む癖があると、前歯が噛み合わなくなります。
舌癖は自分では気づきにくいことが多く、滑舌が悪くなる原因にもなります。
4.2.4 頬杖
テレビを見ている時や勉強中に、無意識に頬杖をついていませんか? 頬杖は、片側の顎や歯に持続的に強い力を加えるため、顔の歪みや歯並びの乱れを引き起こす非常に悪い癖です。 人間の頭の重さは体重の約10%もあり、その重みが一点に集中することで、以下のような問題が生じます。
- 歯列の歪み: 頬杖をついている側の歯が内側に倒れ込み、歯のアーチが歪んでしまいます。
- 噛み合わせのズレ: 左右の顎のバランスが崩れ、噛み合わせが深くなったり、中心がズレたりする原因となります。
- 顔の非対称: 特に成長期の子どもが頬杖を続けると、顎の骨の成長が妨げられ、顔全体が歪んでしまうこともあります。
これらの癖は、一つだけでなく複数が関連していることもあります。以下の表で、ご自身やお子さまに当てはまるものがないかチェックしてみましょう。
| 癖・習慣 | 引き起こされる可能性のある歯並びの問題 |
|---|---|
| 口呼吸 | 出っ歯、開咬、歯列の狭窄、ガタガタの歯並び |
| 指しゃぶり(4歳以降) | 出っ歯、開咬 |
| 舌で歯を押す癖 | 出っ歯、すきっ歯、開咬 |
| 頬杖 | 歯列の歪み、噛み合わせのズレ、顔の非対称 |
| その他(爪を噛む、唇を噛む、うつぶせ寝など) | 出っ歯、受け口、歯の摩耗 |
このように、歯並びは遺伝だけで決まるものではなく、日々の生活習慣が大きく影響しています。気になる癖がある場合は、それが歯並びに影響を及ぼす前になるべく早く改善することが、将来の綺麗な歯並びにつながります。
5. 今からでも間に合う 綺麗な歯並びを目指す方法
「歯並びは子供のうちにしか治せない」と思っていませんか?そんなことはありません。歯を支える骨や歯茎が健康であれば、大人になってからでも綺麗な歯並びを目指すことは十分に可能です。 大人の歯並びのお悩みは、歯科医院での専門的な矯正治療と、日々の生活習慣の見直しを組み合わせることで、効果的に改善できます。ここでは、具体的な方法について詳しく解説します。
5.1 歯科医院で行う歯列矯正
自己流での歯並び改善は、歯や顎にダメージを与えてしまうリスクがあるため、絶対に避けるべきです。 最も安全かつ確実な方法は、矯正歯科の専門知識を持つ歯科医師に相談し、ご自身の歯並びの状態やライフスタイルに合った治療法を選択することです。 主な歯列矯正には、以下のような種類があります。
5.1.1 ワイヤー矯正(表側矯正)
歯の表側に「ブラケット」という装置を取り付け、そこにワイヤーを通して歯を動かす、最も歴史があり一般的な矯正方法です。 さまざまな歯並びの乱れ(不正咬合)に対応できる適用範囲の広さが特徴です。 近年では、従来の金属製の装置だけでなく、白や透明で目立ちにくいセラミック製やプラスチック製のブラケットも選択できます。
5.1.2 裏側矯正(舌側矯正)
歯の裏側(舌側)に矯正装置を取り付ける方法です。 外からは装置がほとんど見えないため、治療中の見た目を気にされる方や、人と接する機会の多い職業の方に特に人気があります。 ただし、表側矯正に比べて費用が高くなる傾向があり、専門的な技術を要するため対応できる歯科医院が限られます。
5.1.3 マウスピース矯正
患者様一人ひとりの歯型に合わせて作製された、透明なマウスピース型の装置を定期的に交換しながら歯を動かしていく方法です。 目立ちにくいだけでなく、食事や歯磨きの際に自分で取り外せるため、日常生活への影響が少なく、口腔内を清潔に保ちやすいという大きなメリットがあります。 一方で、1日20時間以上の装着時間を守る必要があり、自己管理が重要になります。 また、歯並びの状態によっては適用できない場合もあります。
| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット | 費用の目安(全体矯正) | 治療期間の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワイヤー矯正(表側) | 歯の表面に装置を装着する最も一般的な方法。 | ・幅広い症例に対応可能 ・比較的費用を抑えられる ・歴史が長く実績が豊富 |
・装置が目立ちやすい ・食事や歯磨きがしにくい ・口内炎ができやすい |
60万円~100万円 | 1年~3年程度 |
| 裏側矯正(舌側) | 歯の裏側に装置を装着する方法。 | ・外から装置が見えず、目立たない | ・費用が高額になりやすい ・発音しにくいことがある ・対応できる歯科医院が限られる |
100万円~150万円 | 2年~3年程度 |
| マウスピース矯正 | 透明なマウスピース型の装置を交換していく方法。 | ・装置が目立たない ・取り外し可能で衛生的 ・痛みが比較的少ない |
・自己管理が必要(装着時間を守る) ・重度の症例には対応できない場合がある ・紛失のリスクがある |
50万円~120万円 | 1年~3年程度 |
※費用や期間は、歯並びの状態、治療範囲(全体矯正か部分矯正か)、選択する装置、歯科医院によって大きく異なります。 上記はあくまで目安とし、詳細は必ずカウンセリングでご確認ください。
5.2 日常生活で気をつけたいこと
歯科医院での矯正治療と並行して、日々の何気ない癖や習慣を見直すことも、綺麗な歯並びを維持し、治療をスムーズに進める上で非常に重要です。 特に、矯正治療後の「後戻り」を防ぐためにも、以下の点を意識してみましょう。
5.2.1 正しい舌の位置を意識する(スポットポジション)
舌の正しい位置は、上顎の前歯の少し後ろにある「スポット」と呼ばれる膨らみに舌先が触れ、舌全体が上顎に吸い付いている状態です。 舌で歯を押す癖があると、出っ歯やすきっ歯の原因になります。 常に舌が正しい位置にあるよう意識することで、口周りの筋肉のバランスが整い、歯並びの安定につながります。
5.2.2 口を閉じて鼻呼吸を徹底する
口呼吸が習慣化すると、口周りの筋肉(口輪筋)が緩み、前歯が前方に傾きやすくなります。 また、舌の位置が下がりやすくなるため、歯並びに悪影響を及ぼします。 意識的に口を閉じ、鼻で呼吸することで、口元の筋肉が引き締まり、歯を正しい位置に保つ助けになります。
5.2.3 食事の際は左右均等に噛む
いつも同じ側ばかりで噛む癖があると、片方の顎や筋肉だけに負担がかかり、顔の歪みや歯並びの乱れにつながる可能性があります。 食事の際は、左右の歯でバランス良く、しっかりと噛むことを心がけましょう。 よく噛むことは、顎の正常な発達を促し、歯並びの安定にも貢献します。
5.2.4 姿勢を正し、頬杖をやめる
猫背や頬杖は、一見歯並びとは関係ないように思えますが、顎の位置に影響を与え、噛み合わせや歯並びに悪影響を及ぼすことがあります。 特に頬杖は、片側の顎や歯に持続的な圧力をかけることになるため、避けるべき習慣です。 背筋を伸ばして正しい姿勢を保つことを意識し、無意識の癖を改善していきましょう。
6. まとめ
本記事では、歯並びが良い人に共通する7つの特徴と、それがもたらす5つのメリットを解説しました。整った歯並びは、美しい笑顔だけでなく、虫歯や歯周病のリスク軽減、正しい発音など、心身の健康に深く関わっています。歯並びは遺伝だけでなく、口呼吸や頬杖といった後天的な生活習慣も大きく影響するため、日頃の意識が大切です。もしご自身の歯並びが気になる場合、専門家への相談を通じて歯列矯正で改善を目指すことが可能です。
矯正治療のご相談をご希望の方は、下記のボタンよりお気軽にご予約ください。
この記事の監修者

尾立 卓弥(おだち たくや)
医療法人札幌矯正歯科 理事長
宮の沢エミル矯正歯科 院長
北海道札幌市の矯正専門クリニック「宮の沢エミル矯正歯科」院長。
日本矯正歯科学会 認定医。