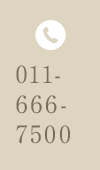歯が動かないアンキローシスの原因と矯正治療の全て

こんにちは。医療法人 札幌矯正歯科 宮の沢エミル矯正歯科の理事長の尾立卓弥です。札幌で矯正歯科を検討中の方は、ぜひ医療法人 札幌矯正歯科 宮の沢エミル矯正歯科でご相談ください。歯科矯正で歯が動かない場合、歯と骨が癒着する「アンキローシス」が原因かもしれません。本記事では、アンキローシスが起こる原因、見分けるサイン、歯科医院での精密な診断方法を解説します。さらに、矯正治療中に判明した場合の外科処置や抜歯などの対処法、治療可能な歯科医院の選び方まで詳しくお伝えします。諦める前に、この記事でご自身の状況と治療の選択肢を正しく理解しましょう。
1. アンキローシスとは 歯が骨と癒着する状態
アンキローシス(Ankylosis)とは、日本語で「骨性癒着(こつせいゆちゃく)」とも呼ばれ、歯の根(歯根)と、歯を支える顎の骨(歯槽骨)が直接くっついてしまう状態を指します。通常、歯と骨の間には「歯根膜(しこんまく)」という薄いクッションのような組織が存在しますが、この歯根膜が失われることで癒着が起こります。一度アンキローシスを起こした歯は、骨と一体化してしまうため、生理的な歯の移動はもちろん、矯正治療で力を加えても動かすことができなくなります。
特に、これから矯正治療を考えている方や、現在矯正治療中の方にとって、アンキローシスは治療計画に大きな影響を与える可能性があるため、正しく理解しておくことが重要です。乳歯にも永久歯にも起こる可能性があり、放置すると歯並びや噛み合わせに問題を引き起こすこともあります。
1.1 歯根膜の消失が引き起こす現象
アンキローシスを理解する上で最も重要なのが「歯根膜」の存在です。歯根膜は、歯根の表面と歯槽骨の間にある厚さ0.15mm〜0.35mm程度の非常に薄い結合組織ですが、以下のような多くの重要な役割を担っています。
- 衝撃吸収(クッション機能): 噛んだ時の硬いものや強い力が直接骨に伝わらないように、衝撃を和らげます。
- 歯の固定と支持: 歯を顎の骨にしっかりと固定し、支えます。
- 感覚の伝達: 食べ物の硬さや食感を脳に伝えるセンサーの役割を果たします。
- 歯の移動の司令塔: 骨を溶かす細胞(破骨細胞)と骨を作る細胞(骨芽細胞)の働きをコントロールし、歯の正常な移動(骨のリモデリング)を可能にします。
しかし、強い打撲などの外傷や長期間の炎症など、何らかの原因で歯根膜が部分的に、あるいは完全に失われてしまうことがあります。すると、歯根と歯槽骨が直接触れ合うことになり、傷が治る過程で骨同士がくっつくように修復されてしまいます。これがアンキローシス(骨性癒着)のメカニズムです。歯根膜というクッション兼司令塔を失った歯は、もはや独立した組織ではなく、顎の骨の一部と化してしまうのです。
1.2 歯科矯正で歯が動く仕組みとの違い
アンキローシスがなぜ矯正治療において大きな問題となるのかは、歯が動く仕組みと比較すると明確に理解できます。通常の矯正治療とアンキローシスの歯の状態を比べてみましょう。
通常の矯正治療では、ブラケットやワイヤーなどの装置を使って歯に持続的な力を加えます。この力が歯根膜に伝わると、歯が動く方向の骨では「破骨細胞」が骨を溶かし(骨吸収)、反対側の骨では「骨芽細胞」が新しい骨を作る(骨添加)という新陳代謝(リモデリング)が起こります。この絶え間ない骨の吸収と添加の繰り返しによって、歯は少しずつ移動していくのです。
一方、アンキローシスの歯には、この骨のリモデリングを司る最も重要な組織である「歯根膜」が存在しません。そのため、矯正装置でいくら力を加えても、骨の吸収と添加が起こらず、歯は全く動かないのです。無理に動かそうとすると、隣の健康な歯が意図しない方向に動いてしまったり、歯根や骨に過度な負担がかかったりするリスクがあります。
この違いを以下の表にまとめました。
| 比較項目 | 正常な歯(矯正治療時) | アンキローシスの歯 |
|---|---|---|
| 歯根膜の有無 | 存在する | 存在しない(消失している) |
| 矯正力の伝達 | 歯根膜が力を感知し、骨に信号を送る | 歯根膜がないため、骨のリモデリング信号が伝わらない |
| 骨の反応 | 骨の吸収と添加(リモデリング)が起こる | 骨の反応が全く起こらない |
| 歯の移動 | 力を加えた方向に少しずつ移動する | 全く移動しない |
このように、アンキローシスは矯正治療の基本的なメカニズムを根底から覆してしまう状態であり、もし矯正治療中に発見された場合は、治療計画の大幅な見直しが必要となります。
2. 歯のアンキローシスが起こる主な原因
歯が動かなくなるアンキローシスは、なぜ起こってしまうのでしょうか。その根本的な原因は、歯と歯槽骨(歯を支える顎の骨)の間にある「歯根膜(しこんまく)」という薄い組織が、何らかの理由で失われてしまうことにあります。歯根膜がなくなると、歯の根(歯根)と骨が直接くっついてしまい、まるで骨の一部のように固まってしまうのです。ここでは、アンキローシスを引き起こす代表的な原因について詳しく解説します。
| 原因の種類 | アンキローシスが起こる主なメカニズム |
|---|---|
| 歯の外傷・強い打撲 | 強い衝撃によって歯根膜が断裂・損傷し、修復過程で歯根と骨が直接癒着する。 |
| 歯の再植・移植治療 | 一度抜けた歯を戻す際に、歯根膜が物理的に損傷したり、乾燥して機能しなくなったりする。 |
| 乳歯の虫歯・炎症の放置 | 歯の根の先にできた膿袋などの慢性的な炎症が、歯根膜組織を破壊してしまう。 |
| 原因不明(特発性) | 明確な原因が特定できず、遺伝的要因や過去の軽微な外傷などが関与していると考えられている。 |
2.1 歯の外傷や強い打撲が原因のケース
アンキローシスの原因として最も多いのが、歯への外傷です。例えば、転倒して顔をぶつけたり、スポーツや事故で歯に強い衝撃が加わったりした場合がこれにあたります。
強い力が加わると、歯と骨の間でクッションの役割を果たしている歯根膜が部分的に、あるいは完全に断裂してしまうことがあります。特に、歯がグラグラになる「亜脱臼」、歯が歯ぐきの中にめり込んでしまう「陥入(かんにゅう)」、一度完全に抜けてしまう「脱臼」といった重度の外傷では、歯根膜が広範囲にわたって深刻なダメージを受けます。
歯根膜が失われた部分では、傷を治そうとする体の働き(治癒過程)の中で、歯のセメント質と歯槽骨が直接触れ合い、骨同士がくっつくのと同じように修復されてしまいます。これが「骨性癒着」、すなわちアンキローシスです。外傷後すぐには癒着せず、数ヶ月から数年かけてゆっくりと進行することもあります。
2.2 歯の再植や移植治療
外傷によって完全に抜けてしまった歯を元の場所に戻す「歯の再植」や、親知らずなどを抜歯して機能していない部分に植え替える「自家歯牙移植」といった歯科治療が、アンキローシスのきっかけになることもあります。
これらの治療は、一度歯を歯槽骨から抜くため、歯根膜へのダメージを完全に避けることは困難です。特に、抜けた歯の取り扱いがアンキローシスの発生率に大きく影響します。歯根膜の細胞は非常にデリケートで、乾燥に弱いため、抜けてから再植するまでの時間が長引いたり、歯の根を手で触ってしまったりすると、歯根膜の細胞が死んでしまいます。
機能する歯根膜が失われた状態で歯を戻すと、体はそれを異物ではなく骨の一部と認識し、骨と直接結合させてしまうのです。そのため、歯が抜けてしまった際は、歯を乾燥させないように牛乳や専用の保存液に浸し、できるだけ早く歯科医院を受診することが重要です。公益社団法人 日本口腔外科学会も、脱臼歯の適切な保存方法について注意喚起しています。(参考: 公益社団法人 日本口腔外科学会「歯をケガしたら(歯の外傷)」)
2.3 乳歯の虫歯や炎症の放置
大人の永久歯だけでなく、子どもの乳歯でもアンキローシスは起こります。その主な原因となるのが、重度の虫歯やそれを放置したことによる歯の根の先の炎症です。
乳歯の虫歯が神経まで達し、さらに進行して根の先に膿の袋(根尖病巣)ができると、その慢性的な炎症が周囲の組織に悪影響を及ぼします。この炎症が長期間続くと、歯根膜の組織が破壊され、結果として乳歯の根と顎の骨が癒着してしまうことがあります。
乳歯がアンキローシスを起こすと、正常な時期に抜け落ちず、後から生えてくる永久歯の行く手を阻んでしまうことがあります。これにより、永久歯が正しい位置に生えてこられず、歯並びが大きく乱れる原因となるため、注意が必要です。「乳歯はいずれ生え変わるから」と安易に考えず、虫歯は早期に治療することが大切です。
2.4 原因が特定できない場合もある
上記で挙げたようなはっきりとした原因が見当たらないにもかかわらず、アンキローシスが起こるケースも存在します。これを「特発性(とくはつせい)アンキローシス」と呼びます。
患者様ご自身が覚えていないような、幼少期の軽微な打撲が影響している可能性や、遺伝的な要因、体の代謝疾患などが関わっているという説もありますが、現在のところ明確な原因は解明されていません。
特に目立った原因の心当たりがないまま、矯正治療を開始し、特定の歯だけが全く動かないことで初めてアンキローシスが判明することも少なくありません。原因がわからないと不安に感じられるかもしれませんが、重要なのはアンキローシスが起きているという事実を正確に診断し、適切な治療方針を立てることです。
3. もしかしてアンキローシス?自分で気づくためのサイン
歯のアンキローシスは、レントゲン撮影など歯科医院での精密な検査によってはじめて確定診断が下されるものです。しかし、日常生活の中や矯正治療の過程で「もしかして?」と気づくことができるいくつかのサインが存在します。ここでは、ご自身でアンキローシスの可能性を疑うことができる代表的な兆候について詳しく解説します。これらのサインに心当たりがある場合は、早めに専門家へ相談しましょう。
3.1 矯正中に特定の歯だけ動かない
矯正治療を受けている方にとって最も気づきやすい兆候が、特定の歯だけが動かないという現象です。通常、矯正装置によって力を加えられた歯は、歯と顎の骨の間にある「歯根膜(しこんまく)」という組織の働きによって少しずつ移動します。しかし、アンキローシスを起こしている歯は、歯根と顎の骨(歯槽骨)が直接癒着してしまっているため、この歯根膜が存在しません。そのため、いくら矯正装置で引っ張ったり押したりしても、まるで岩のように頑固に動かないのです。
周りの歯は計画通りに動いて歯並びが整ってきているのに、一本だけが取り残されたように元の位置から動かない場合、アンキローシスの可能性が考えられます。治療の進捗を定期的にチェックする中で、担当の歯科医師から指摘されることも多いですが、ご自身でも鏡を見て「この歯だけ動いていないな」と感じたら、すぐに相談することが重要です。
3.2 歯を叩いた時の音(打診音)の違い
歯科医師が診断の際に用いる方法の一つに「打診」があります。これは、器具で歯を軽くコンコンと叩き、その時の音や響き方で歯の状態を確認するものです。アンキローシスの場合、この打診音が健康な歯と明らかに異なります。
ご自身で確認する場合は、指の先などで隣の歯と問題の歯を優しくトントンと叩き比べてみてください。ただし、強く叩くと歯や歯茎を傷つける可能性があるため、あくまで軽く触れる程度にしましょう。
| 健康な歯 | アンキローシスの疑いがある歯 | |
|---|---|---|
| 叩いた時の音(打診音) | クッション性のある鈍い音(例:「コンコン」) | 硬く響く金属的な高い音(例:「キンキン」「カンカン」) |
| 音の違いの理由 | 歯根と骨の間にある歯根膜がクッションの役割を果たし、振動を吸収するため。 | 歯根と骨が直接くっついているため、振動が骨に直接伝わり硬い音がする。 |
この金属音は、アンキローシスを疑う非常に特徴的なサインです。もし明らかな音の違いを感じた場合は、専門的な診断を受けることをお勧めします。
3.3 周りの歯より高さが低い(埋入)
アンキローシスを起こした歯は、周りの歯や顎の成長から取り残され、相対的に低い位置に見えることがあります。この状態を「埋入(まいにゅう)」や「インフラオクルージョン」と呼びます。
特に乳歯や、永久歯に生え変わる成長期のお子様において顕著に見られる現象です。周りの歯は正常に萌出(ほうしゅつ:歯が生えること)し、顎の成長とともに上へ移動していきます。しかし、骨と癒着したアンキローシスの歯は、その場に固定されたまま成長できません。結果として、その歯だけが歯ぐきに埋もれたように、あるいは周りの歯よりも一段低く沈んだような見た目になります。
成人になってからアンキローシスが進行した場合でも、隣の歯が傾いてきたり、噛み合う相手の歯が伸びてきたり(挺出)することで、相対的にその歯の位置が低くなることがあります。歯並びのアーチがその部分だけへこんでいるように見える場合は、注意が必要です。
3.4 自己判断は危険 必ず歯科医院で診断を
これまでにご紹介したサインは、あくまでアンキローシスの可能性に気づくためのセルフチェックの目安です。これらの症状が一つでも当てはまったからといって、ご自身で「アンキローシスに違いない」と断定することは非常に危険です。
歯が動かない、位置が低いといった症状は、他の原因(例えば、歯根の形態異常や極端な骨の硬さなど)によって引き起こされている可能性もゼロではありません。正確な原因を特定するには、歯科医師による専門的な診察と、レントゲンや歯科用CTを用いた精密検査が不可欠です。
これらのサインに気づいたら、決して放置したり自分で解決しようとしたりせず、速やかにかかりつけの歯科医師や矯正専門医に相談することが不可欠です。早期に相談することで、適切な診断のもと、最善の治療計画を立てることが可能になります。不安な気持ちを抱え込まず、まずは専門家の意見を聞きましょう。
4. 歯科医院で行うアンキローシスの精密な診断方法
「もしかしてアンキローシスかも?」と感じても、自己判断は非常に危険です。アンキローシスの確定診断は、歯科医師による専門的な診察と精密な検査によってはじめて可能になります。診断の精度が、その後の適切な治療方針を決定づけるため、非常に重要なプロセスです。ここでは、歯科医院で実際に行われるアンキローシスの精密な診断方法を、ステップに沿って詳しく解説します。
4.1 問診と視診による確認
まず基本となるのが、問診と視診です。患者様からのお話と、お口の中を直接見ることで、アンキローシスの可能性を探ります。
問診で確認する主な内容
- 過去の外傷歴: いつ、どの歯を、どのようにぶつけたかなど、歯に強い衝撃が加わった経験の有無を確認します。
- 過去の歯科治療歴: 歯の移植や再植、重度の虫歯治療の経験などを伺います。
- 矯正治療の状況: 矯正治療中であれば、いつから、どの歯の動きが止まっていると感じるかなどを詳しくヒアリングします。
- 自覚症状: 痛みや違和感の有無、歯の高さが低いと感じるかなどを確認します。
視診・触診で確認する主な内容
- 歯の高さ(挺出度): アンキローシスを起こしている歯は、成長や矯正治療によって動く周囲の歯から取り残され、相対的に低く見える「埋入(infraocclusion)」という状態になることがあります。隣の歯や、反対側の同じ位置にある歯と高さを比較します。
- 歯の動揺度テスト: ピンセットのような器具で歯を軽く揺らし、生理的な範囲の動きがあるかを確認します。アンキローシスの歯は骨と直接結合しているため、健康な歯に比べて動揺がほとんどありません。
- 打診音の確認: 器具で歯をコンコンと軽く叩き、その音を聞き分けます。健康な歯は歯根膜がクッションとなり「コツコツ」という鈍い音がしますが、アンキローシスの歯は骨に直接響くため「キーン」「カチカチ」といった金属様(metallic sound)の高い音がするのが特徴です。
4.2 レントゲン検査で歯根の状態を把握
問診や視診でアンキローシスが疑われた場合、次にレントゲン撮影による画像診断を行います。レントゲンでは、歯とそれを支える歯槽骨の状態を二次元的に確認することができます。
レントゲン検査における最大の診断ポイントは、「歯根膜腔(しこんまくくう)」の有無です。健康な歯では、歯根と歯槽骨の間に「歯根膜」という薄い靭帯組織が存在し、これがレントゲン画像上では黒い線(透過像)として写ります。これが歯根膜腔です。
しかし、アンキローシスを起こしている歯では、この歯根膜が失われ、歯根と歯槽骨が直接くっついてしまいます。そのため、レントゲン画像では歯根膜腔にあたる黒い線が部分的に、あるいは完全に消失して見えます。これが、アンキローシスを診断する上で非常に重要な所見となります。また、歯根の形が丸みを帯びて吸収されている様子(歯根吸収)が確認できることもあります。
4.3 CT撮影による三次元的な精密検査
レントゲン検査だけでは、癒着が歯根のどの部分で、どの程度の範囲に及んでいるかを正確に把握するのが難しい場合があります。なぜなら、レントゲンはあくまで二次元の平面的な画像だからです。そこで、より確実な診断と治療計画の立案のために行われるのが、歯科用CT(CBCT)による精密検査です。
歯科用CTを用いると、歯と顎の骨を三次元の立体画像として、あらゆる角度から詳細に観察することができます。これにより、以下のようなレントゲンでは分からなかった情報まで正確に把握できます。
- 歯根と歯槽骨が癒着している正確な位置(唇側、舌側、歯根の先端など)
- 癒着している範囲の広さと深さ
- 歯根吸収の具体的な進行度合い
- 周囲の骨の状態
この三次元的な情報は、その後の治療方針を決定する上で決定的に重要です。例えば、癒着がごく一部であれば外科的に癒着を剥がして歯を動かせる可能性がありますが、広範囲に及んでいる場合は抜歯を選択せざるを得ないこともあります。CTによる精密検査は、治療の成功率を高め、リスクを最小限に抑えるために不可欠な検査と言えるでしょう。
| 検査方法 | 確認する主な内容 | 特徴とわかること |
|---|---|---|
| 問診・視診 | 外傷歴、治療歴、歯の高さ、動揺度、打診音 | 基本的な診察。アンキローシスの可能性をスクリーニングする。金属様の打診音や動揺の欠如が特徴的なサイン。 |
| レントゲン検査 | 歯根膜腔の有無、歯根吸収の状態 | 二次元の画像診断。歯根膜腔の消失が確認できれば、アンキローシスの可能性が非常に高まる。 |
| 歯科用CT(CBCT)検査 | 癒着の正確な位置・範囲・深さ | 三次元の精密な画像診断。癒着の状態を立体的に把握し、確実な診断と治療計画の立案に不可欠。 |
5. 矯正治療中にアンキローシスが判明した場合の対処法と治療の選択肢
順調に進んでいたはずの矯正治療。しかし、ある日「特定の歯だけが全く動いていない」という事実に直面し、歯科医師から「アンキローシス(歯根癒着)の可能性があります」と告げられたら、誰でも不安になることでしょう。治療計画が白紙に戻ってしまうのではないか、理想の歯並びは手に入らないのではないかと、様々な心配が頭をよぎるかもしれません。
しかし、アンキローシスが判明したからといって、矯正治療そのものを諦める必要はありません。現代の歯科医療には、状況に応じて様々な対処法や治療の選択肢が存在します。大切なのは、現状を正確に把握し、歯科医師と十分に話し合った上で、ご自身にとって最適な治療方針を再設定することです。ここでは、矯正治療中にアンキローシスが判明した場合の具体的な対処法と治療の選択肢について詳しく解説します。
5.1 治療計画の見直しとゴールの再設定
アンキローシスが確定診断された場合、まず最初に行うべきことは、当初の治療計画を根本から見直すことです。アンキローシスの歯は、通常の矯正力では動かすことができないため、その歯を動かすことを前提とした元の計画は達成困難となります。
そこで、担当の矯正歯科医は、アンキローシスの歯の位置、本数、そして患者様が何を最も優先したいか(審美性、機能性、治療期間、費用など)を改めてヒアリングし、現実的に達成可能な新しい治療ゴールを一緒に設定していきます。最新のシミュレーションソフトなどを用いて、変更後の歯の動きや最終的な歯並びのイメージを共有しながら、納得のいくゴールを見つけることが、治療を成功に導くための重要な第一歩となります。
5.1.1 アンキローシスの歯を避けた部分的な矯正治療
選択肢の一つとして、アンキローシスの歯を「動かさない」ことを前提とした治療計画が考えられます。このアプローチでは、癒着した歯を現在の位置で受け入れ、その周囲の歯だけを動かして歯並びを整えていきます。
場合によっては、アンキローシスの歯を強固な「固定源(アンカー)」として積極的に利用することもあります。動かない歯を支えにして他の歯を効率的に動かすことができるため、治療の精度向上に繋がるケースもあります。この方法は、外科的な処置を伴わないため身体への負担が少なく、アンキローシスの歯の位置が審美的・機能的に大きな問題とならない場合に有効な選択肢です。
ただし、理想の咬み合わせや完璧な歯列アーチの実現には限界があることも理解しておく必要があります。
5.1.2 アンキローシスの歯を動かす外科的アプローチ
「どうしてもこの歯を動かして理想の歯並びに近づけたい」という強い希望がある場合や、アンキローシスの歯の位置が咬み合わせに深刻な影響を与えている場合には、外科的なアプローチを検討することがあります。これらの処置は、口腔外科医との連携が必要となる専門性の高い治療です。
5.1.2.1 ラグジュエーション(意図的脱臼)
ラグジュエーションとは、癒着している歯に対して意図的に力を加え、歯根と骨との癒着を剥がす処置です。局所麻酔下で、専用の器具を使って歯をわずかに動かし(亜脱臼させ)、癒着部分に微小な隙間を作ります。これにより、失われていた歯根膜が再生するきっかけを与え、再び歯が動くようになる可能性を狙います。処置後は一定期間をおいて、再度矯正力をかけて歯の動きを確認します。比較的侵襲の少ない外科処置ですが、歯根や歯の神経にダメージを与えるリスクや、再癒着する可能性もゼロではありません。
5.1.2.2 コルチコトミー(歯槽骨皮質骨切除術)
コルチコトミーは、歯を支えている骨(歯槽骨)の表面にある硬い層(皮質骨)に意図的に切れ込みを入れる外科手術です。骨に切れ込みを入れることで、骨の治癒メカニズムが働き、一時的に骨代謝が活発になります。この生物学的な反応を利用して、骨の抵抗を減らし、アンキローシスの歯を含めた歯全体の移動を促進させます。ラグジュエーションで効果が見られない場合や、より確実な歯の移動が求められる場合に選択されることがあります。歯周組織の再生療法と組み合わせて行われることもあり、専門的な知識と技術が要求される治療法です。
5.2 抜歯してインプラントやブリッジで補う方法
外科的アプローチを試みても歯が動かない場合や、アンキローシスの歯が著しく低位にある(埋まっている)など、残しておくことが全体の歯並びや機能にとってマイナスになると判断された場合は、抜歯が選択肢となります。歯を抜いた後のスペースは、そのままにすると隣の歯が倒れ込んできたり、対合する歯が伸びてきたりするため、何らかの方法で補う必要があります。
抜歯後の治療法には、主にインプラント、ブリッジ、部分入れ歯があり、それぞれの特徴は以下の通りです。
| 治療法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| インプラント |
|
|
| ブリッジ |
|
|
| 部分入れ歯 |
|
|
どの方法を選択するかは、欠損部の状態、残っている歯の状態、費用、患者様のライフスタイルなどを総合的に考慮して決定します。
5.3 治療方針は歯科医師との相談が不可欠
ここまで様々な治療の選択肢をご紹介しましたが、どの方法が最適かは一人ひとりの患者様で全く異なります。アンキローシスの状態、口腔内全体のバランス、年齢、全身の健康状態、そして何よりも「ご自身がどのようなゴールを目指したいか」という希望が、治療方針を決定する上で最も重要です。
決してご自身だけで判断せず、必ず担当の矯正歯科医と納得がいくまで話し合ってください。それぞれの治療法のメリット・デメリット、リスク、期間、費用について詳細な説明を受け、全ての選択肢を理解した上で、最終的な治療方針を一緒に決定していくことが大切です。場合によっては、セカンドオピニオンを求めて他の歯科医師の意見を聞くことも、後悔のない選択をするために有効な手段です。
6. アンキローシス治療に対応できる矯正歯科の選び方
歯のアンキローシスは、一般的な歯科矯正とは異なる専門的な知識と技術、そして高度な設備が求められる難しい治療です。そのため、どの歯科医院を選ぶかが、治療の成功を大きく左右すると言っても過言ではありません。ここでは、アンキローシスの治療を安心して任せられる矯正歯科を選ぶための重要なポイントを解説します。
まずは、これから解説する選び方のポイントを一覧で確認しましょう。
| チェック項目 | 確認するべき具体的なポイント |
|---|---|
| 精密な診断設備 | 歯科用CT(コーンビームCT)が院内に完備されているか。または、連携施設で迅速に撮影できる体制が整っているか。 |
| 専門分野の連携体制 | 矯正歯科医だけでなく、外科的処置を行う口腔外科医との緊密な連携が取れているか。院内に在籍、または信頼できる提携病院があるか。 |
| 治療経験と実績 | 歯科医院のウェブサイトなどで、アンキローシスの治療症例が公開されているか。担当医が同様のケースを扱った経験が豊富か。 |
| カウンセリングの質 | 治療のメリット・デメリット、リスク、費用について、患者が納得できるまで丁寧に説明してくれるか。複数の選択肢を提示してくれるか。 |
6.1 CTなど精密な診断設備が整っている
アンキローシスの診断において、最も重要なのが歯と顎の骨の状態を正確に把握することです。アンキローシスは歯根と歯槽骨が直接癒着している状態であり、その境目にあるはずの歯根膜が消失しています。この微細な状態を二次元的なレントゲン写真だけで完全に診断するのは困難な場合があります。
そこで不可欠となるのが、三次元的な画像情報を得られる歯科用CT(コーンビームCT)です。CT撮影を行うことで、歯根の形状、癒着が疑われる範囲、周囲の骨の状態を立体的に詳細に分析できます。これにより、診断の精度が格段に向上し、後の治療計画をより安全かつ的確に立案することが可能になります。
歯科医院を選ぶ際には、院内にCT設備が整っているか、あるいはCT撮影が可能な医療機関とスムーズに連携できる体制が構築されているかを確認しましょう。
6.2 矯正歯科と口腔外科の連携体制がある
アンキローシスの治療では、歯を動かすために外科的なアプローチが必要になるケースが少なくありません。具体的には、意図的に歯を脱臼させて歯根膜の再生を促す「ラグジュエーション」や、歯の周囲の骨に切れ込みを入れる「コルチコトミー」、場合によっては癒着した歯を抜歯するといった外科処置が選択肢となります。
これらの処置は、高度な技術を要する口腔外科の領域です。そのため、矯正治療を専門とする「矯正歯科医」と、外科処置を専門とする「口腔外科医」との緊密な連携が、質の高い治療を実現するための鍵となります。
同じ院内に両方の専門医が在籍している、あるいは大学病院や総合病院の口腔外科と密に連携している歯科医院であれば、診断から治療計画の策定、外科処置、その後の矯正管理まで、一貫した流れでスムーズに進めることができます。情報共有も円滑に行われるため、患者さんにとっても安心材料となるでしょう。
6.3 アンキローシスの治療経験や症例が豊富
アンキローシスは、矯正治療を受ける患者さん全体から見ると、発生頻度はそれほど高くありません。したがって、すべての矯正歯科医がアンキローシスの治療経験を豊富に持っているわけではないのが実情です。
経験豊富な医師は、癒着の程度や位置、患者さんの年齢や口内全体の状況を総合的に判断し、ラグジュエーション、コルチコトミー、部分矯正、抜歯してインプラントで補うなど、多様な選択肢の中から最適な治療法を提案できます。また、治療中に起こりうる予期せぬトラブルにも的確に対応できる能力を持っています。
歯科医院のウェブサイトで、アンキローシスに関する治療実績や症例写真が公開されているかを確認するのは非常に有効です。また、カウンセリングの際に、直接医師に同様のケースを扱った経験について質問してみるのも良いでしょう。日本矯正歯科学会が認定する「認定医」や「臨床指導医(旧専門医)」であるかどうかも、医師の専門性を判断する一つの目安になります。
6.4 医療法人札幌矯正歯科ではカウンセリングを行っています
ここまでご説明してきたように、アンキローシスの治療には、精密な診断力、外科と連携した総合的な治療計画、そして豊富な経験が不可欠です。もし、ご自身の歯がアンキローシスではないかとご不安な方や、他の医院でそう診断されてお悩みの方は、一度専門家にご相談ください。
例えば、私たち医療法人札幌矯正歯科では、アンキローシスが疑われる患者様のために、無料のカウンセリングを実施しております。当院では、精密な診断を可能にする歯科用CTを完備し、経験豊富な矯正歯科医が口腔外科専門医と連携しながら治療計画を立案します。
カウンセリングでは、まず患者様のお悩みやご希望を丁寧にお伺いし、お口の中の状態を拝見します。その上で、アンキローシスの可能性や考えられる治療の選択肢、それぞれのメリット・デメリット、期間や費用について、分かりやすくご説明いたします。治療を受けるかどうかを決めるのは、すべての情報に納得されてからで構いません。まずはお一人で悩まず、専門家の客観的な意見を聞くことから始めてみてはいかがでしょうか。
7. アンキローシスの矯正治療にかかる費用
アンキローシス(歯根癒着)の治療は、通常の歯科矯正とは異なり、外科的な処置を伴うことが多いため、費用体系も特殊になります。基本的な矯正治療費に加えて、アンキローシスの状態や選択する治療法に応じた追加費用が発生することを理解しておく必要があります。ここでは、具体的な費用の内訳や、保険適用の可能性について詳しく解説します。
7.1 外科処置など追加治療の費用について
アンキローシスの治療費用は、症状の程度や治療を行う歯科医院の方針によって大きく変動します。以下に示すのはあくまで一般的な目安であり、実際の費用は必ず治療を受ける歯科医院での精密検査とカウンセリングを経て確認してください。これらの費用は、全体の矯正治療費とは別に発生する追加料金となることがほとんどです。
| 治療法 | 費用の目安(1歯あたり) | 内容 |
|---|---|---|
| ラグジュエーション(意図的脱臼) | 3万円 ~ 10万円程度 | 癒着した歯を器具で意図的にわずかに動かし、再癒着を防ぎながら矯正力で移動させるための処置です。比較的軽度な癒着に適用されます。 |
| コルチコトミー(歯槽骨皮質骨切除術) | 10万円 ~ 30万円程度 | 歯の周囲の硬い骨(皮質骨)に切れ込みを入れ、歯を骨ごと移動させる外科手術です。骨の代謝を活性化させ、歯の移動を促します。 |
| 外科的挺出術 | 5万円 ~ 20万円程度 | 埋まっている(埋入している)アンキローシスの歯を、外科的に引っ張り上げて高さを揃える処置です。 |
| 抜歯 | 5,000円 ~ 2万円程度(自由診療の場合) | アンキローシスの歯を動かすことが困難と判断された場合に選択されます。抜歯自体の費用です。 |
| 抜歯後の補綴治療(インプラント) | 30万円 ~ 50万円程度 | 抜歯したスペースを補うための治療です。人工歯根を顎の骨に埋め込み、その上に人工の歯を装着します。 |
| 抜歯後の補綴治療(ブリッジ) | 15万円 ~ 40万円程度(素材による) | 抜歯した歯の両隣の歯を支えにして、連結した人工歯を被せる治療法です。 |
これらの外科処置には、別途CT撮影などの精密検査費用(3万円~5万円程度)が必要になる場合があります。治療計画を立てる段階で、総額でどのくらいの費用が見込まれるのか、詳細な見積もりを提示してもらうことが重要です。
7.2 保険適用になるケースとならないケース
原則として、歯並びや噛み合わせの改善を目的とするアンキローシスの矯正治療は「審美目的」と見なされ、公的医療保険が適用されない自由診療(自費診療)となります。そのため、治療にかかる費用は全額自己負担となるのが基本です。
しかし、ごく稀に保険適用が認められるケースも存在します。
- 外傷による場合:交通事故や転倒などで歯を強く打ち、その後の治療過程でアンキローシスと診断され、かつ噛み合わせに深刻な機能障害が生じていると医師が判断した場合など、特定の条件下で保険適用となる可能性があります。ただし、これは個別の判断に委ねられるため、必ず適用されるわけではありません。
- 先天性の疾患に起因する場合:厚生労働省が定める特定の先天性疾患(唇顎口蓋裂など)が原因で咬合異常があり、その治療の一環として矯正治療が必要な場合は、アンキローシスの処置を含めて保険適用となることがあります。
上記はあくまで例外的なケースです。ほとんどの場合は自由診療となりますが、治療費の負担を軽減する方法として「医療費控除」の活用が考えられます。
医療費控除とは、一年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の合計が10万円(または総所得金額の5%)を超えた場合に、確定申告を行うことで所得控除を受けられ、結果的に所得税や住民税が還付・減額される制度です。審美目的の矯正は対象外ですが、歯科医師が「噛み合わせの改善など、機能的な問題の解消に必要」と診断した場合の矯正治療費は、医療費控除の対象となります。アンキローシスの治療は機能改善の側面が強いため、対象となる可能性が高いです。治療を受ける際は、歯科医師に医療費控除の対象になるかを確認し、領収書や診断書を必ず保管しておきましょう。
詳しくは国税庁のウェブサイトをご確認ください。
No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例(国税庁)
8. まとめ
アンキローシスは、歯根膜が失われ歯と骨が癒着することで、矯正治療をしても歯が動かなくなる状態です。主な原因は外傷や炎症ですが、特定できない場合もあります。矯正中に一部の歯だけ動かない、歯を叩いた音が違うなどのサインがあれば疑われますが、自己判断はせず、CTなどによる精密な診断が不可欠です。治療法は外科処置で動かす、抜歯してインプラントで補うなど様々です。信頼できる歯科医師と相談し、ご自身の状況に合った最適な治療計画を立てることが重要です。
矯正治療のご相談をご希望の方は、下記のボタンよりお気軽にご予約ください。
この記事の監修者

尾立 卓弥(おだち たくや)
医療法人札幌矯正歯科 理事長
宮の沢エミル矯正歯科 院長
北海道札幌市の矯正専門クリニック「宮の沢エミル矯正歯科」院長。
日本矯正歯科学会 認定医。