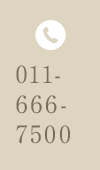歯並びがガタガタになった原因は?【歯科医監修】大人になってからの変化と治し方を解説

こんにちは。医療法人 札幌矯正歯科 宮の沢エミル矯正歯科の理事長の尾立卓弥です。札幌で矯正歯科を検討中の方は、ぜひ医療法人 札幌矯正歯科 宮の沢エミル矯正歯科でご相談ください。大人になって歯並びがガタガタになったと感じる主な原因は、親知らずや歯周病、無意識の癖など様々です。この記事を読めば、歯並びが悪化する7つの原因と、放置するリスク、そしてワイヤー矯正やマウスピース矯正といった具体的な治し方から予防策まで全てが分かります。ご自身の状況と照らし合わせ、最適な解決策を見つけるためにお役立てください。
1. 大人になってから歯並びがガタガタになったと感じていませんか
「昔は歯並びが良かったはずなのに、最近鏡を見ると前歯が重なって見える」「写真を撮ると、以前より歯がガタガタしている気がする…」
このように、大人になってから歯並びの変化に気づき、不安を感じている方は少なくありません。子どもの頃の歯並びの問題とは異なり、成人後の歯並びの乱れは、生活習慣や加齢など、さまざまな後天的な要因が複雑に絡み合って起こります。
実は、歯というものは骨に固定されているように見えて、生涯を通じて少しずつ動く可能性のある組織です。そのため、以前は整っていた歯並びが、何らかのきっかけで崩れてしまうことは、誰にでも起こり得るのです。
1.1 「昔は綺麗だったのに…」その悩み、あなただけではありません
厚生労働省の調査によると、不正咬合(ふせいこうごう)、つまり良くない歯並びを持つ人の割合は、年齢とともに変化する傾向が見られます。特に成人期以降に歯並びの乱れを自覚し、歯科医院に相談に訪れる方は年々増加しています。
参照: 平成28年歯科疾患実態調査 結果の概要(厚生労働省)
かつては「歯の矯正は子どものうちにするもの」というイメージが強かったかもしれませんが、現在では30代、40代、さらには50代以上で矯正治療を始める方も珍しくありません。それは、多くの方があなたと同じように、大人になってからの歯並びの変化に悩み、改善したいと考えていることの表れと言えるでしょう。
1.2 こんなサインに要注意!歯並び変化のチェックリスト
歯並びの変化は、ごくわずかなものから始まるため、毎日見ていると気づきにくいことがあります。以下のようなサインに心当たりがないか、セルフチェックしてみましょう。一つでも当てはまる場合は、歯並びが変化し始めているサインかもしれません。
| 変化のサイン(チェック項目) | 具体的な症状の例 |
|---|---|
| 前歯の重なり・ねじれ | 特に下の前歯が重なり合ってガタガタしてきた。以前はまっすぐだった歯が少しねじれてきたように感じる。 |
| 歯と歯の間の隙間 | 以前はなかった場所に隙間ができた(すきっ歯)。特に前歯の間に隙間が目立つようになった。 |
| 出っ歯になった気がする | 上の前歯が以前よりも前に出てきたように感じる。口が閉じにくくなった。 |
| 食べ物が挟まりやすくなった | 特定の歯と歯の間に、頻繁に食べ物の繊維などが挟まるようになった。フロスが通りにくくなった箇所がある。 |
| 噛み合わせの変化 | 以前と噛み合う場所が変わった気がする。食事の際に違和感がある。 |
これらの変化は、見た目の問題だけでなく、お口の健康全体に関わる重要なサインです。なぜなら、歯並びの乱れは、単に審美的な問題に留まらないからです。
この記事では、なぜ大人になってから歯並びがガタガタになってしまうのか、その原因を詳しく掘り下げ、放置するリスクや具体的な治療法、そして今後のための予防策まで、専門的な知見を交えて分かりやすく解説していきます。
2. 歯並びがガタガタになった考えられる7つの原因
子どもの頃は気にならなかったのに、大人になってから「あれ?なんだか歯並びがガタガタしてきたかも?」と感じる方は少なくありません。歯は一生同じ場所にあるわけではなく、様々な要因で動いてしまうことがあります。ここでは、大人になってから歯並びが乱れる主な原因を7つ、詳しく解説します。
2.1 原因1 親知らずの生え方による影響
親知らずは、永久歯の中で最も遅く、一般的に10代後半から20代前半にかけて生えてくる歯です。現代人は顎が小さくなっている傾向があり、親知らずがまっすぐ生えるための十分なスペースがないことが多くあります。
スペースが足りない状態で親知らずが生えようとすると、横向きや斜めに生えてきて、手前の奥歯をぐいぐいと押し始めます。この力がドミノ倒しのように前方の歯へと伝わり、結果として前歯がガタガタになったり、重なり合ったりする原因となるのです。特に自覚症状がないまま、じわじわと歯並び全体に影響を及ぼすケースが多いため注意が必要です。
2.2 原因2 歯周病の進行
歯周病は、歯垢(プラーク)に含まれる細菌が原因で歯ぐきに炎症が起き、進行すると歯を支えている骨(歯槽骨)を溶かしてしまう病気です。30代以上の日本人の多くが罹患していると言われています。
歯を支える土台である歯槽骨が溶かされてしまうと、歯は安定性を失い、グラグラと動揺し始めます。この状態になると、日々の食事で噛む力や、舌で歯を押すわずかな力でさえ、歯が簡単に動いてしまうようになります。この現象は「病的歯牙移動」と呼ばれ、出っ歯になったり、歯と歯の間にすき間ができたりと、歯並びが大きく乱れる直接的な原因となります。詳しくは、日本臨床歯周病学会のウェブサイトでも解説されています。
2.3 原因3 加齢による顎骨や歯の変化
年齢を重ねることも、歯並びに影響を与える一因です。加齢に伴い、全身の骨密度が低下するのと同じように、顎の骨も少しずつ痩せていきます。また、長年使い続けることで歯の先端や側面が摩耗(咬耗)し、噛み合わせの高さやバランスが変化することも少なくありません。
さらに、私たちの歯には元々、奥歯から前歯の方向へ少しずつ移動していく「生理的メジアルドリフト」という性質があります。これらの加齢による複合的な変化が積み重なることで、下の前歯を中心に歯が混み合い、ガタガタになってくることがあります。特に女性の場合は、更年期に女性ホルモンのバランスが変化し、骨がもろくなることも影響すると考えられています。
2.4 原因4 歯ぎしりや食いしばりの癖
睡眠中や日中に集中している時など、無意識のうちに行っている歯ぎしりや食いしばり(ブラキシズム)も、歯並びを悪化させる大きな要因です。食事の際に歯にかかる力は数kg程度ですが、歯ぎしりや食いしばりの際には、自分の体重と同等か、それ以上の非常に強い力が歯や顎にかかっていると言われています。
このような過剰な力が日常的に歯にかかり続けると、歯がすり減って噛み合わせが変わったり、歯がダメージに耐えようと少しずつ動いたりして、歯列の乱れにつながります。また、歯が割れたり、詰め物・被せ物が破損したりする原因にもなります。
2.5 原因5 頬杖や舌癖などの日常的な癖
頬杖をつく、舌で前歯を押す、唇を噛む、いつも同じ側でばかり物を噛む、うつ伏せで寝るなど、日常の何気ない癖も歯並びに影響を及ぼします。矯正治療で歯を動かす力は数十g〜100g程度と非常に弱いものですが、歯は持続的に力が加わることで動きます。
頬杖や舌の癖なども、弱い力であっても毎日長時間繰り返されることで、歯を望ましくない方向へ動かしてしまうのです。どのような癖が歯並びに影響を与えるか、具体例を下の表にまとめました。
| 癖の種類 | 歯並びへの影響の例 |
|---|---|
| 頬杖 | 片方の顎に圧力がかかり、奥歯が内側に倒れ込んだり、噛み合わせがずれたりする。 |
| 舌で前歯を押す癖(舌突出癖) | 上の前歯と下の前歯の間にすき間ができる開咬(かいこう)や、出っ歯(上顎前突)の原因になる。 |
| 唇を噛む・吸う癖 | 下の唇を噛むと出っ歯に、上の唇を噛むと受け口(下顎前突)になりやすい。 |
| うつ伏せ寝・横向き寝 | 長時間にわたって顎や歯に圧力がかかり、歯列が狭くなったり、顔の歪みにつながったりすることがある。 |
2.6 原因6 虫歯や抜歯で抜けた歯の放置
虫歯が重症化したり、歯周病が進行したりして歯を抜くことになった場合、その抜けたスペースを放置しておくのは非常に危険です。歯は隣り合う歯とお互いに支え合ってバランスを保っていますが、1本でも歯がなくなるとその均衡が崩れてしまいます。
具体的には、抜けた歯のスペースに向かって両隣の歯が倒れ込んできたり、噛み合う相手を失った向かいの歯が伸びてきたり(挺出)します。たった1本の欠損から、ドミノ倒しのように全体の噛み合わせが崩壊し、歯並びがガタガタになってしまうことは珍しくありません。歯を失った場合は、ブリッジや入れ歯、インプラントなどで早期に補うことが重要です。
2.7 原因7 過去の歯科矯正の後戻り
10代や20代の頃に一度、歯科矯正で歯並びをきれいに整えた経験がある方でも、再び歯並びが乱れてしまうことがあります。これは「後戻り」と呼ばれる現象です。
矯正治療によって動かした歯は、治療が終わった後も元の位置に戻ろうとする性質があります。そのため、矯正治療後は歯並びを安定させるための保定装置(リテーナー)を一定期間、指示通りに装着する必要があります。しかし、このリテーナーの使用を自己判断でやめてしまったり、装着時間が不十分だったりすると、歯は少しずつ元の乱れた位置へと戻っていってしまうのです。また、前述した歯周病や癖なども、後戻りを助長する原因となります。
3. ガタガタになった歯並びを放置するリスク
「少し歯並びがガタガタしてきただけだから大丈夫」と軽く考えて、そのまま放置していませんか?しかし、乱れた歯並びは見た目の問題だけでなく、お口の中や全身の健康にまで悪影響を及ぼす可能性を秘めています。ここでは、ガタガタになった歯並びを放置することで生じる具体的な4つのリスクについて詳しく解説します。
3.1 虫歯や歯周病が悪化しやすくなる
歯並びがガタガタになっていると、歯が重なり合ったり、複雑な角度で生えたりしているため、歯ブラシが届きにくく、プラーク(歯垢)が溜まりやすくなります。毎日丁寧に歯磨きをしているつもりでも、磨き残しが多く発生してしまうのです。
除去しきれなかったプラークは、虫歯菌や歯周病菌の温床となります。特に歯と歯の間や、歯と歯茎の境目に溜まったプラークは、虫歯だけでなく、歯茎の炎症(歯肉炎)を引き起こします。さらにこの状態が続くと、歯を支える骨(歯槽骨)を溶かしてしまう歯周病へと進行するリスクが非常に高まります。
歯周病は「サイレント・ディジーズ(静かなる病気)」とも呼ばれ、自覚症状がないまま進行することが多い恐ろしい病気です。重度の歯周病になると、歯がグラグラしてきたり、最悪の場合、健康な歯であっても抜けてしまうことがあります。詳しくは、厚生労働省が提供する情報もご参照ください。e-ヘルスネット「歯周病の基礎知識」
3.2 口臭の原因につながる
ガタガタの歯並びは、口臭の発生にも深く関わっています。前述の通り、歯が重なり合った部分にはプラークや食べカスが非常に溜まりやすくなります。これらの汚れが細菌によって分解される際に、不快な臭いを放つ揮発性硫黄化合物(VSC)が発生し、これが口臭の直接的な原因となるのです。
また、歯周病が進行すると、歯周ポケット(歯と歯茎の溝)が深くなり、そこから膿が出たり、歯周病菌自体が特有の強い臭いを発したりします。どんなにケアをしても口臭が改善しない場合、その原因は磨き残しやすい歯並びにあるのかもしれません。
3.3 顎関節症を引き起こす可能性がある
歯並びの乱れは、噛み合わせのバランスを崩す大きな要因です。本来、上下の歯は均等な力で噛み合うようにできていますが、歯並びがガタガタだと特定の歯にだけ強い力がかかったり、顎を不自然な位置で動かして食事をしたりするようになります。
このような状態が長く続くと、顎の関節(顎関節)や周辺の筋肉に過度な負担が蓄積し、顎関節症を引き起こすリスクが高まります。顎関節症になると、以下のような様々なつらい症状が現れることがあります。
| 症状の種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 顎の痛み | 口を開け閉めするとき、食事をするときに顎関節や頬、こめかみが痛む。 |
| 口の開閉障害 | 口がまっすぐ開かない、大きく開けられない(指が縦に2本程度しか入らない)。 |
| 関節音 | 口を開け閉めするときに「カクカク」「ジャリジャリ」といった音がする。 |
| 関連症状 | 原因不明の頭痛、肩こり、首の痛み、耳鳴り、めまいなど全身に症状が及ぶこともある。 |
これらの症状にお悩みの方は、噛み合わせの不調和が原因かもしれません。顎関節症に関する詳しい情報は、日本顎関節学会のウェブサイトでも確認できます。
3.4 見た目のコンプレックスになる
健康面のリスクに加え、ガタガタの歯並びは審美的な問題、つまり見た目のコンプレックスに直結します。歯並びが気になって、人前で思いきり笑えなかったり、会話の際に無意識に口元を手で隠してしまったりする方は少なくありません。
特に大人になってから歯並びが悪化した場合、「以前はこうではなかったのに」という思いから、より強い精神的ストレスを感じることがあります。笑顔に自信が持てないと、初対面の人とのコミュニケーションに消極的になったり、写真に写るのが嫌になったりと、日常生活の様々な場面でネガティブな影響を与えかねません。歯並びは顔の印象を大きく左右する要素の一つであり、コンプレックスを解消することは、自信を取り戻し、より豊かな社会生活を送るためにも非常に重要です。
4. ガタガタになった歯並びの治し方と治療法
大人になってからガタガタになった歯並びは、見た目の問題だけでなく、お口全体の健康にも影響を及ぼす可能性があります。しかし、諦める必要はありません。現在の歯科医療では、さまざまな治療法によって歯並びを整え、機能と審美性の両方を回復させることが可能です。ここでは、ガタガタになった歯並びを治すための主な治療法について、それぞれの特徴や費用、期間を詳しく解説します。
4.1 主な歯並びの治療法 歯科矯正
ガタガタになった歯並びを根本的に改善するための最も代表的な治療法が「歯科矯正」です。歯に継続的に力をかけて少しずつ動かし、正しい位置に並べ直します。かつては子どもの治療というイメージが強かった矯正治療ですが、近年では装置の進化により、大人になってから治療を始める方が非常に増えています。ここでは、主な歯科矯正の種類をご紹介します。
4.1.1 ワイヤー矯正(表側・裏側)
ワイヤー矯正は、歯の表面または裏面に「ブラケット」と呼ばれる小さな装置を接着し、そこにワイヤーを通して歯を動かす、最も歴史と実績のある矯正方法です。対応できる症例の幅が広いのが特徴です。
【表側矯正】
歯の表側(唇側)に装置をつける一般的な方法です。幅広い歯並びの乱れに対応でき、比較的費用を抑えられる傾向にあります。近年では、従来の金属製の装置だけでなく、白や透明で目立ちにくいセラミック製やプラスチック製のブラケットも選択できます。
【裏側矯正(舌側矯正)】
歯の裏側(舌側)に装置をつけるため、外からは装置がほとんど見えず、審美性に非常に優れています。人前に出るお仕事の方や、見た目を気にされる方に人気の治療法です。ただし、表側矯正に比べて費用が高くなることや、舌に装置が触れるため慣れるまで発音しにくい場合があるといった特徴があります。
4.1.2 マウスピース矯正
透明なマウスピース型の装置を、治療計画に沿って定期的に新しいものに交換していくことで、段階的に歯を動かす比較的新しい矯正方法です。代表的なものに「インビザライン」などがあります。
最大のメリットは、装置が透明で目立ちにくく、自分で自由に取り外しができる点です。食事や歯磨きの際は取り外せるため、普段通りに行うことができ、衛生的です。一方で、1日20時間以上の装着が必要であり、自己管理が治療結果を大きく左右します。また、抜歯が必要なケースや歯の移動量が大きい重度の症例には適さない場合もあります。
4.1.3 部分矯正
「前歯のガタガタだけ」「すきっ歯だけ」など、気になる部分だけを限定的に治療する方法です。全体の歯を動かす必要がないため、治療期間が比較的短く(数ヶ月〜1年程度)、費用も全体矯正に比べて安価なのが魅力です。奥歯の噛み合わせに問題がなく、軽度の歯並びの乱れを改善したい場合に適しています。ワイヤー矯正、マウスピース矯正のどちらでも行うことが可能です。
4.2 歯科矯正の費用と期間の目安
歯科矯正は、基本的に保険が適用されない自由診療となります。費用や期間は、お口の状態(症例の難易度)、選択する装置の種類、歯科医院によって大きく異なります。以下はあくまで一般的な目安として参考にしてください。正確な費用と期間は、必ず歯科医院での精密検査とカウンセリングで確認しましょう。
| 治療法 | 費用相場 | 治療期間の目安 |
|---|---|---|
| 表側矯正(全体) | 約60万円~100万円 | 約1年~3年 |
| 裏側矯正(全体) | 約100万円~150万円 | 約2年~3年 |
| マウスピース矯正(全体) | 約70万円~100万円 | 約1年~3年 |
| 部分矯正 | 約20万円~60万円 | 約3ヶ月~1年 |
※上記の費用とは別に、初回のカウンセリング料、精密検査・診断料、毎月の調整料、治療後の保定装置(リテーナー)料などがかかる場合があります。
より詳しい情報については、専門機関のウェブサイトも参考にすると良いでしょう。
参考: 矯正歯科治療について | 公益社団法人 日本矯正歯科学会
4.3 矯正以外の治療の選択肢
ガタガタの状態や患者さんの希望によっては、矯正治療以外にも見た目を改善する方法があります。ただし、これらは歯の根を動かすわけではないため、根本的な噛み合わせの改善にはつながらない点に注意が必要です。
【セラミック矯正(補綴治療)】
歯を削り、その上からセラミック製の被せ物(クラウン)を装着することで、歯の形や向き、色を整える方法です。歯を動かすわけではないため、治療期間が数週間から数ヶ月と非常に短いのが最大のメリットです。しかし、健康な歯を削る必要があり、場合によっては歯の神経を抜く処置が必要になることもあります。
【ダイレクトボンディング】
歯科用のプラスチック(コンポジットレジン)を歯に直接盛り付け、形を整える方法です。歯を削る量を最小限に抑えられ、1日で治療が完了することもあります。軽度の隙間や歯の欠け、形の修正に適していますが、セラミックに比べて強度が劣り、経年で変色する可能性があります。
5. これ以上歯並びをガタガタにしないための予防策
一度崩れてしまった歯並びを自力で元に戻すことは困難であり、多くの場合、歯科矯正などの専門的な治療が必要になります。しかし、今後の歯並びの悪化を防ぎ、現状を維持するためにできる予防策は数多く存在します。ここでは、これ以上歯並びをガタガタにしないために、今日から始められる具体的な予防策を3つご紹介します。
5.1 歯科医院での定期検診とクリーニング
歯並びの悪化を防ぐ上で、最も重要かつ効果的なのが歯科医院での定期的なメンテナンスです。自分では気づきにくいお口の中の変化を専門家である歯科医師や歯科衛生士にチェックしてもらうことで、歯並びが悪化する原因を早期に発見し、対処することができます。
定期検診では、主に以下のような項目をチェックします。
- 虫歯や歯周病の有無と進行度
- 歯石やプラーク(歯垢)の付着状態
- 親知らずの状態や生え方の変化
- 噛み合わせの変化
- 詰め物や被せ物の不適合
- 歯ぎしりや食いしばりによる歯の摩耗
特に、歯並びが悪化する大きな原因である歯周病は、自覚症状がないまま進行することが多い病気です。定期検診で歯周ポケットの深さを測定したり、専門的なクリーニング(PMTC)で歯石を除去したりすることは、歯を支える骨が溶けてしまうのを防ぎ、歯が動いてしまうリスクを低減させるために不可欠です。3ヶ月から半年に一度は歯科医院を受診し、プロによるチェックとケアを受ける習慣をつけましょう。
5.2 日々の癖を見直して改善する
何気なく行っている日常的な癖が、少しずつ歯に力を加え、歯並びを乱す原因になっていることがあります。無意識の行動が多いため、まずはご自身の癖を自覚し、意識的に改善していくことが大切です。
特に注意したい癖とその対策を以下の表にまとめました。
| 癖の種類 | 歯並びへの影響 | 具体的な改善策 |
|---|---|---|
| 頬杖 | 片方の顎や歯に持続的な圧力がかかり、歯列が内側に傾いたり、顔の歪みにつながったりする。 | 意識してやめる。デスク周りに「頬杖禁止」などのメモを貼る。両手を組んで顎の下に置くなど、頬杖ができない姿勢をとる。 |
| 舌で歯を押す癖(舌癖) | 舌で前歯を押し出すことで、出っ歯(上顎前突)や、上下の歯が噛み合わない開咬(かいこう)の原因になる。 | 舌の正しい位置(スポットポジション:上顎の少し手前にある膨らみ)を意識する。改善が難しい場合は、歯科医院で口腔筋機能療法(MFT)の指導を受ける。 |
| うつ伏せ寝・横向き寝 | 長時間にわたり、枕などで顎や歯に圧力がかかる。顔の片側だけが圧迫され、歯並びの乱れや顔の非対称につながる可能性がある。 | できるだけ仰向けで寝るように心がける。体に合った枕を選び、寝返りを打ちやすい環境を整える。 |
| 片側だけで噛む癖(偏咀嚼) | 片側の筋肉ばかりが発達し、顔のバランスが崩れる。使われていない側の歯は汚れが溜まりやすく、虫歯や歯周病のリスクも高まる。 | 食事の際に、左右均等に噛むことを意識する。ガムを左右交互に噛むトレーニングも有効。 |
これらの癖は、一つ一つの力は弱くても、毎日繰り返されることで歯を動かす十分な力となります。自分の癖に気づき、意識してやめる努力をすることが、将来の歯並びを守るための重要な一歩です。口腔筋機能療法(MFT)について詳しく知りたい方は、日本歯科医師会のウェブサイトなども参考にしてみてください。(参考:日本歯科医師会 口腔筋機能療法(MFT))
5.3 歯ぎしり対策用のナイトガードを使用する
睡眠中の歯ぎしりや食いしばり(ブラキシズム)は、自分でコントロールすることが非常に難しい問題です。歯ぎしりの際に歯にかかる力は、食事の時の何倍にもなると言われており、歯のすり減りや破折、さらには歯を動かしてしまう大きな原因となります。
この強力な力から歯や顎を守るために最も有効なのが、歯科医院で製作する「ナイトガード(睡眠用マウスピース)」の使用です。
5.3.1 ナイトガードの効果
- 歯ぎしりの力を分散させ、特定の歯への過度な負担を軽減する。
- 歯がすり減ったり、欠けたりするのを物理的に防ぐ。
- 顎関節への負担を和らげ、顎関節症の症状を緩和・予防する。
ナイトガードは、市販されているものもありますが、自分の歯並びに合っていないものを使用すると、かえって噛み合わせを悪化させたり、顎に負担をかけたりする危険性があります。必ず歯科医院で精密な歯型を採って、ご自身にぴったり合ったものを作製してもらいましょう。歯ぎしりの治療目的でナイトガードを作製する場合、多くは健康保険が適用されますので、費用面でも安心です。朝起きた時に顎が疲れている、家族から歯ぎしりを指摘されたなどの経験がある方は、一度歯科医師に相談することをおすすめします。
6. まとめ
大人になってから歯並びがガタガタになる原因は、親知らずや歯周病の進行、加齢、歯ぎしりや舌癖など様々です。乱れた歯並びを放置すると、虫歯や口臭のリスクが高まるだけでなく、見た目のコンプレックスにも繋がります。ワイヤー矯正やマウスピース矯正など治療法は様々です。これ以上悪化させないためにも、まずは歯科医院で専門家の診断を受け、原因に合わせた適切な対策を始めましょう。
矯正治療のご相談をご希望の方は、下記のボタンよりお気軽にご予約ください。
この記事の監修者

尾立 卓弥(おだち たくや)
医療法人札幌矯正歯科 理事長
宮の沢エミル矯正歯科 院長
北海道札幌市の矯正専門クリニック「宮の沢エミル矯正歯科」院長。
日本矯正歯科学会 認定医。