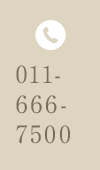中学生・高校生から始める矯正歯科治療|知っておきたいメリットとベストなタイミング

こんにちは。医療法人 札幌矯正歯科 宮の沢エミル矯正歯科の理事長の尾立卓弥です。札幌で矯正歯科を検討中の方は、ぜひ医療法人 札幌矯正歯科 宮の沢エミル矯正歯科でご相談ください。この記事では、中学生・高校生が矯正歯科を始めるメリットを徹底解説します。見た目の改善による自信向上、顎の成長を利用した効率的な治療、虫歯リスク軽減、短い治療期間など、多くの利点があることをお伝えします。さらに、最適な開始時期、ワイヤーやマウスピースといった治療法の種類、費用や期間の目安まで網羅。この記事を読めば、矯正治療への疑問や不安が解消されるでしょう。
1. 中学生や高校生で歯並びに悩んでいませんか?
中学生や高校生という時期は、心も体も大きく成長する大切な期間です。友人関係や部活動、勉強など、新しい経験がたくさん待っています。しかし、その一方で、自分の見た目に対する意識が高まり、些細なことがコンプレックスにつながりやすい時期でもあります。特に、毎日鏡で見る自分の「歯並び」について、悩みを抱えている方も少なくないのではないでしょうか。
「口元が気になって、思いっきり笑えない」「写真を撮るとき、つい口を閉じてしまう」「人前で話すときに、口元を手で隠してしまう」…。そんな経験はありませんか? 歯並びの悩みは、単に見た目の問題だけでなく、自分に自信が持てなくなったり、コミュニケーションに消極的になったりと、学校生活や友人関係にも影響を与えてしまうことがあります。
また、見た目だけでなく、「食べ物がうまく噛めない」「特定の音が発音しにくい(滑舌が悪い)」「歯磨きがしにくく、虫歯や口臭が気になる」といった機能的な問題を抱えているケースもあります。これらの悩みは、日々の生活の中でストレスとなり、学業や部活動への集中力を妨げる一因になる可能性も考えられます。
周りの友達が矯正治療を始めたり、保護者の方から歯並びについて指摘されたりすることで、自分の歯並びがより一層気になり始めることもあるでしょう。「自分も矯正した方がいいのかな?」「でも、いつ始めるのがベストなんだろう?」と、疑問や不安を感じているかもしれません。
まずは、ご自身や、お子様がどのような悩みを抱えているのか、具体的に把握することが大切です。以下に、中学生や高校生が抱えやすい歯並びに関する悩みの例をいくつか挙げてみました。
1.1 中高生が抱えやすい歯並びの悩み 具体例
| 悩みの種類 | 具体的な状況・感情 |
|---|---|
| 見た目・コンプレックス |
|
| 機能的な問題 |
|
| 口腔ケアの問題 |
|
| 心理的な影響 |
|
これらの悩みに一つでも当てはまるものがあれば、それは矯正歯科治療を考えるきっかけになるかもしれません。歯並びの悩みは、決して恥ずかしいことではありません。むしろ、自分の健康や将来について真剣に考えている証拠とも言えます。中学生や高校生という時期は、矯正治療を始める上で多くのメリットがあると言われています。次の章では、その具体的なメリットについて詳しく見ていきましょう。
2. 中学生 高校生から矯正歯科を始めるメリットとは
思春期は、自分の見た目や周りの目が気になり始める多感な時期です。特に、歯並びに関する悩みは、コンプレックスとなり、自信を失う原因にもなりかねません。中学生や高校生というタイミングで矯正歯科治療を始めることには、この時期ならではの多くのメリットがあります。単に見た目を整えるだけでなく、心身の健康や将来にも良い影響を与える可能性があるのです。ここでは、中学生・高校生から矯正歯科を始める具体的なメリットを詳しく解説していきます。
2.1 メリット1 見た目の改善で自信が持てるように
中学生や高校生の時期は、友人関係や社会性が大きく発達する大切な時期です。しかし、歯並びが気になってしまい、人前で自然に笑えなかったり、口元を手で隠してしまったりする生徒さんも少なくありません。歯並びのコンプレックスは、自己肯定感の低下や消極的な性格につながることもあります。
矯正治療によって歯並びが整うと、口元の見た目が大きく改善されます。きれいな歯並びは清潔感を与え、笑顔をより魅力的に見せてくれます。その結果、コンプレックスが解消され、自分に自信を持てるようになります。自信がつくことで、友人とのコミュニケーションが円滑になったり、学校行事や部活動に積極的に参加できるようになったりと、精神的な面で大きなプラスの効果が期待できます。写真撮影や発表の場面など、以前は苦手だったシチュエーションも楽しめるようになるでしょう。
2.2 メリット2 顎の成長を利用して効率的に治療できる可能性
中学生や高校生は、体の成長期にあたり、顎の骨もまだ成長している段階にあります。この顎の成長力を利用できるのが、この時期に矯正治療を始める大きなメリットの一つです。大人の場合、顎の成長はすでに完了しているため、歯を動かすことしかできません。しかし、成長期であれば、顎の成長を適切な方向へ誘導したり、成長をコントロールしたりしながら、歯並びだけでなく、顎の大きさや前後関係のズレ(例えば、受け口や出っ歯など)を改善できる可能性があります。
顎の骨が柔らかいため、歯がスムーズに動きやすく、治療に対する体の反応も良好です。場合によっては、大人になってからでは外科的な手術が必要となるような骨格的な問題も、成長期であれば矯正治療だけで改善できるケースもあります。これを「咬合育成(こうごういくせい)」や「顎顔面矯正(がくがんめんきょうせい)」と呼び、成長期ならではの治療アプローチと言えます。
| 治療時期 | 顎の状態 | 治療のポイント |
|---|---|---|
| 中学生・高校生(成長期) | 顎の骨が成長中で柔らかい | 顎の成長を利用・コントロールしながら、歯と顎の関係を改善できる可能性がある |
| 成人期 | 顎の成長が完了し骨が硬い | 歯の移動が中心。骨格的なズレが大きい場合は外科手術を併用することも |
2.3 メリット3 虫歯や歯周病のリスクを減らす口腔ケアの向上
歯並びがガタガタしていたり、歯が重なり合っていたりすると、歯ブラシの毛先が届きにくい場所ができてしまいます。磨き残しが多くなると、そこにプラーク(歯垢)が溜まり、虫歯や歯肉炎(歯周病の初期段階)の原因となります。特に矯正装置を装着すると、さらに歯磨きが難しくなるため、もともとの歯並びが悪い場合はリスクが高まります。
矯正治療によって歯並びが整うと、歯と歯の間の隙間や重なりが少なくなり、歯ブラシが隅々まで届きやすくなります。これにより、日々の歯磨きで効率的にプラークを除去できるようになり、虫歯や歯周病のリスクを大幅に減らすことができます。また、矯正治療期間中は、定期的に歯科医院に通院し、専門家によるクリーニングやブラッシング指導を受ける機会が増えます。これにより、正しい歯磨きの習慣が身につき、生涯にわたって自分の歯を健康に保つための意識(デンタルIQ)が高まるという副次的なメリットも期待できます。
2.4 メリット4 正しい噛み合わせで全身の健康にも良い影響
歯並びの問題は、単に見た目だけでなく、噛み合わせ(咬合)の異常を伴っていることが多くあります。噛み合わせが悪いと、食べ物を効率よく噛み砕くことができず、消化器官に負担をかけてしまう可能性があります。また、一部の歯に過度な力がかかったり、顎の関節に負担がかかったりすることで、顎関節症(口を開けると痛い、音が鳴るなど)を引き起こすリスクも高まります。
矯正治療によって正しい噛み合わせを獲得すると、食べ物をしっかりと咀嚼できるようになり、栄養の吸収効率が向上します。また、顎への負担が軽減され、顎関節症のリスクを低減できます。さらに、噛み合わせは全身のバランスとも関連があると考えられており、肩こりや頭痛といった不定愁訴が改善されるケースも報告されています。スポーツに取り組んでいる生徒さんにとっては、しっかりと噛みしめることができるようになることで、筋力の発揮や体のバランス感覚が向上し、パフォーマンスアップにつながる可能性も指摘されています。
2.5 メリット5 将来的な抜歯のリスクを低減できることも
歯をきれいに並べるためには、十分なスペースが必要です。顎が小さい場合や、歯が大きい場合には、スペースが不足し、歯がガタガタになったり、前歯が突出したりします。成人矯正では、このスペースを確保するために、健康な歯を抜歯することが少なくありません。
しかし、中学生や高校生の成長期に矯正治療を開始する場合、顎の成長を利用してスペースを確保したり、奥歯を後方に移動させたりすることで、抜歯を回避できる可能性が高まります。顎の幅を広げる装置(拡大床など)を使用できるのも、成長期ならではの治療法です。もちろん、すべてのケースで抜歯を避けられるわけではありませんが、早期に治療を開始することで、非抜歯で理想的な歯並び・噛み合わせを獲得できるチャンスが広がることは大きなメリットと言えるでしょう。自分の歯をできるだけ多く残すことは、将来的な口腔内の健康維持にとっても非常に重要です。
2.6 メリット6 大人と比べて治療期間が短くなる傾向
一般的に、子どもの骨は大人に比べて新陳代謝が活発で、骨が柔らかいため、矯正治療による歯の移動がスムーズに進みやすいと言われています。歯を動かす際には、歯の周りの骨が吸収されたり、新しく作られたりするプロセス(リモデリング)が起こりますが、成長期はこの反応が活発なため、大人よりも短い期間で歯が目標の位置まで移動する傾向があります。
もちろん、治療期間は個々の歯並びの状態、骨格的な問題の有無、選択する矯正装置の種類、そして本人の協力度(装置の装着時間や通院頻度など)によって大きく異なります。しかし、全体的な傾向として、成長期に始めた方が、成人してから始めるよりもトータルの治療期間が短くなる可能性があることは、学業や部活動、受験などで忙しい中高生にとって嬉しいポイントです。治療期間が短いということは、それだけ矯正装置をつけている期間が短くなり、日常生活への影響や精神的な負担も軽減されることにつながります。
3. 矯正歯科を始めるベストなタイミング 中学生 高校生の場合は?
歯並びの悩みは、見た目だけでなく、心や体の健康にも影響を与えることがあります。特に感受性の豊かな中学生や高校生の時期に、コンプレックスを感じているお子さんも少なくありません。「いつから矯正治療を始めるのが良いのだろう?」と悩む保護者の方も多いでしょう。ここでは、中学生・高校生が矯正歯科を始める上でのベストなタイミングについて、顎の成長との関係性も踏まえながら詳しく解説します。
3.1 中学生から始める矯正治療のポイント
中学生の時期は、多くの場合、第二次性徴期にあたり、身長がぐんと伸びるとともに顎の骨も大きく成長する時期です。この顎の成長を利用できることが、中学生から矯正治療を始める大きなメリットとなります。
例えば、上顎や下顎の大きさに問題がある場合(出っ歯や受け口など)、顎の成長をコントロールしたり、適切な方向へ誘導したりする治療(顎骨の拡大や成長誘導)を行うことで、将来的な抜歯や外科手術のリスクを減らせる可能性があります。永久歯が生えそろってくる時期でもあるため、歯を動かすスペースを作りやすく、効率的な治療が期待できます。
また、中学生は比較的新しい環境や変化に対する適応力が高いため、矯正装置への慣れも早い傾向があります。学校生活においても、友人と同じように矯正治療をしているケースも増えてきており、心理的な抵抗感が少ない場合もあります。部活動や学業との両立は考慮が必要ですが、早期に治療を開始することで、高校受験やその先の進路選択の時期までに、ある程度の目処を立てられる可能性もあります。
3.2 高校生から始める矯正治療のポイント
高校生の時期になると、多くの場合、顎の成長は終盤に差し掛かっているか、ほぼ完了しています。そのため、中学生のように顎の成長を積極的に利用した治療は難しくなる傾向にありますが、永久歯列はほぼ完成しており、歯を動かす治療自体は問題なく行えます。
高校生になると、本人の歯並びに対する意識や治療へのモチベーションが高まっていることが多いのが特徴です。なぜ治療が必要なのか、どのように進めていくのかを理解し、治療に対してより協力的になれる年齢と言えます。歯磨きなどの自己管理能力も向上しているため、矯正装置を清潔に保ち、治療をスムーズに進めやすくなります。
大学受験や就職活動など、将来の重要なライフイベントを見据えて、見た目を整えたいという希望から治療を開始するケースも多く見られます。ただし、顎の成長が終わっている場合、歯を並べるスペースを確保するために抜歯が必要になる可能性が中学生よりも高くなることがあります。また、学業や部活動、アルバイトなどで多忙な生活を送っている場合、通院時間の確保や装置装着による制限などを考慮する必要があります。
3.3 顎の成長期と矯正歯科治療の関係性
矯正歯科治療において、顎の成長は非常に重要な要素です。特に骨格的な問題(受け口、出っ歯、開咬など)が関わる場合、顎の成長期に治療を開始することで、より理想的な治療結果を得やすくなります。
成長期を利用した治療では、「機能的矯正装置」や「ヘッドギア」、「上顎前方牽引装置」などを用いて、顎の成長方向をコントロールしたり、顎の骨の幅を広げたりすることが可能です。これにより、歯が並ぶためのスペースを確保し、抜歯の可能性を低減したり、顔貌のバランスを整えたりする効果が期待できます。
顎の成長のピークは個人差が大きく、一般的に女子は男子よりも早く迎えます。身長が急激に伸びる時期と連動していることが多いですが、正確な判断にはレントゲン撮影(特にセファログラムと呼ばれる頭部X線規格写真)による骨年齢の評価などが役立ちます。
成長がほぼ終了した後に骨格的な問題を解決しようとすると、歯の移動だけで対応できる範囲には限界があり、場合によっては外科的な手術(顎変形症治療)が必要になることもあります。そのため、骨格的な問題が疑われる場合は、成長期に一度、矯正歯科医に相談することが推奨されます。
| 成長段階 | 主な治療アプローチ | 期待される効果・特徴 |
|---|---|---|
| 成長期前期(小学生中学年~高学年頃) | Ⅰ期治療(咬合誘導、顎骨の成長コントロール、機能的矯正装置など) | 顎の成長を利用し、骨格的な問題を改善。永久歯が正しく生えるための土台作り。 |
| 成長期ピーク(中学生頃) | 顎骨の成長コントロール、Ⅱ期治療(永久歯列の本格的な矯正、ワイヤー矯正、マウスピース矯正など)の開始 | 顎の成長を最大限に利用できる時期。効率的な歯の移動が期待できる。 |
| 成長期後期(高校生頃) | Ⅱ期治療(永久歯列の本格的な矯正)が中心。顎の成長利用は限定的。 | 歯の移動は問題なく可能。本人の協力が得やすい。抜歯の可能性は中学生より高まる傾向。 |
| 成長終了後(高校卒業以降) | Ⅱ期治療(永久歯列の本格的な矯正)。必要に応じて外科矯正も検討。 | 歯の移動による治療が中心。骨格的な問題が大きい場合は外科手術が必要なことも。 |
※上記の成長段階や年齢はあくまで目安であり、個人差があります。
3.4 まずは矯正歯科に相談 開始時期を見極める重要性
これまで見てきたように、中学生、高校生それぞれに矯正治療を開始するメリットや考慮点があります。「何歳から始めるのが絶対にベスト」という画一的な答えはなく、お子さん一人ひとりの歯並びの状態、顎の成長段階、骨格的な問題の有無、そして本人の希望やライフスタイルによって最適な開始時期は異なります。
最も重要なのは、「気になったら、まずは専門家である矯正歯科医に相談してみる」ということです。早期に相談することで、以下のようなメリットがあります。
- 精密検査(レントゲン撮影、歯型採取、口腔内写真撮影など)に基づき、お子さんの顎の成長段階や歯並びの問題点を正確に把握できる。
- 最適な治療開始時期や、どのような治療方法が適しているかについて、専門的なアドバイスを受けられる。
- 複数の治療オプションやそれぞれのメリット・デメリット、期間、費用などについて詳しい説明を聞き、比較検討できる。
- すぐに治療を開始する必要がない場合でも、定期的な観察を通じて適切なタイミングを見極めることができる。
矯正歯科への相談は、必ずしもすぐに治療を開始することを意味するわけではありません。「うちの子の場合はどうなんだろう?」という疑問や不安を解消するためにも、信頼できる矯正歯科を見つけ、親子で納得のいくまで相談し、適切な開始時期を見極めることが、後悔のない矯正治療への第一歩となります。必要であれば、セカンドオピニオンを求めることも有効な手段です。
4. 中学生 高校生が受けられる矯正歯科の主な種類
矯正歯科治療と一言で言っても、その方法は一つではありません。特に見た目が気になる時期である中学生や高校生にとっては、どのような装置を使って治療を進めるのかは非常に重要なポイントです。ここでは、中学生・高校生が選択できる主な矯正歯科治療の種類について、それぞれの特徴、メリット、デメリットを詳しく解説していきます。
4.1 ワイヤー矯正 表側矯正と裏側矯正
ワイヤー矯正は、歯の表面または裏面に「ブラケット」と呼ばれる小さな装置を取り付け、そこにワイヤーを通して歯を動かしていく、最も歴史があり、多くの症例に対応可能な矯正方法です。大きく分けて、歯の表側につける「表側矯正」と、裏側につける「裏側矯正」があります。
4.1.1 表側矯正の特徴 メリット デメリット
表側矯正(唇側矯正)は、歯の表側(唇側)にブラケットとワイヤーを装着する、最も一般的で実績豊富な矯正方法です。多くの方が「歯の矯正」と聞いてイメージするのがこの方法でしょう。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 特徴 | 歯の表面に金属やセラミック、プラスチック製のブラケットを装着し、ワイヤーで歯を動かす。 |
| メリット |
|
| デメリット |
|
見た目が気になる場合は、ブラケットの素材を金属ではなく、歯の色に近いセラミックやプラスチック製のものを選ぶことで、ある程度目立ちにくくすることが可能です。費用や審美性、機能面などを考慮して素材を選びましょう。
4.1.2 裏側矯正の特徴 メリット デメリット
裏側矯正(舌側矯正、リンガル矯正)は、歯の裏側(舌側)にブラケットとワイヤーを装着する矯正方法です。外からは装置がほとんど見えないため、見た目を気にされる方に人気があります。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 特徴 | 歯の裏側にオーダーメイドまたは既製のブラケットを装着し、ワイヤーで歯を動かす。 |
| メリット |
|
| デメリット |
|
裏側矯正は、高い審美性が魅力ですが、費用や技術的な側面、日常生活での慣れなどを考慮して選択する必要があります。特に部活動で管楽器を演奏する場合などは、事前に歯科医師に相談することが重要です。
4.2 マウスピース矯正 インビザラインなど
マウスピース矯正は、透明なマウスピース型の矯正装置(アライナー)を段階的に交換していくことで歯を動かす比較的新しい治療法です。代表的なシステムとして「インビザライン」があり、日本でも多くの中学生・高校生がこの治療法を選択しています。目立ちにくく、取り外しが可能である点が大きな特徴です。
4.2.1 マウスピース矯正の特徴 メリット デメリット
マウスピース矯正は、コンピューターを用いた3Dシミュレーションで治療計画を立て、患者さん一人ひとりの歯の形に合わせて作製された複数のマウスピースを、通常1~2週間ごとに交換しながら装着します。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 特徴 |
|
| メリット |
|
| デメリット |
|
インビザラインには、中高生向けに設計された「インビザライン・ティーン」というプランもあります。これは、装着時間をモニターできるインジケーターが付いていたり、永久歯が生え揃う途中でも対応できるような工夫がされていたりします。
4.3 自分に合った矯正方法の選び方
ここまでご紹介したように、矯正治療にはそれぞれ異なる特徴、メリット、デメリットがあります。中学生・高校生が自分に合った矯正方法を選ぶためには、以下の点を考慮することが大切です。
- 何を最も優先したいか?(見た目、費用、快適さ、治療期間、確実性など)
- 自分の歯並びの状態(症例)はどの治療法に適しているか?
- 生活習慣や性格(部活動、食事の好み、自己管理能力など)
例えば、とにかく見た目を重視したいのであれば、裏側矯正やマウスピース矯正が候補になりますが、それぞれのデメリット(費用、発音、自己管理など)も理解しておく必要があります。費用をできるだけ抑えたい、あるいは複雑な歯並びで確実な治療効果を期待したい場合は、表側矯正が第一選択となることが多いでしょう。食事や歯磨きを普段通りに行いたい、自己管理に自信があるなら、マウスピース矯正が魅力的に映るかもしれません。
部活動で格闘技や激しい接触のあるスポーツをしている場合は、口の中を傷つけるリスクが少ないマウスピース矯正が有利な場合もありますが、マウスピースの装着規定がある場合や、逆に外れにくいワイヤー矯正の方が適していると判断される場合もあります。吹奏楽部などで管楽器を演奏する場合は、装置の種類によって演奏のしやすさが変わる可能性があるため、必ず事前に相談しましょう。
最も重要なのは、ご自身の歯並びや顎の状態に合った、最適な治療効果が期待できる方法を選ぶことです。そのためには、まず信頼できる矯正歯科医に相談し、精密検査を受けた上で、それぞれの治療法の詳細な説明(メリット・デメリット、費用、期間、リスクなど)を聞くことが不可欠です。
一つの歯科医院だけでなく、複数の医院でカウンセリングを受け、比較検討する(セカンドオピニオン)ことも、納得のいく治療法を選択するために有効な手段です。保護者の方ともよく相談し、ご自身にとってベストな矯正方法を見つけていきましょう。
5. 中学生 高校生が矯正歯科を始める前に知っておくべきこと
中学生や高校生のうちに矯正歯科治療を始めることには多くのメリットがありますが、実際に治療を開始する前には、いくつか知っておくべき大切なポイントがあります。治療期間や費用、痛みへの対処法、日常生活での注意点、そして何よりも信頼できる矯正歯科医院の選び方について、詳しく解説していきます。これらの情報を事前に理解しておくことで、安心して矯正治療に臨むことができるでしょう。
5.1 矯正治療にかかる期間の目安
矯正治療がどのくらいの期間を要するのかは、多くの方が気になる点だと思います。一般的に、歯を動かす「動的治療期間」は1年半から3年程度とされています。しかし、これはあくまで目安であり、個々の歯並びの状態(叢生、出っ歯、受け口など)、顎の骨格、選択する治療方法(ワイヤー矯正、マウスピース矯正など)、年齢、そして治療への協力度(指示通りに装置を使用する、定期的に通院するなど)によって大きく変動します。
特に中学生や高校生の場合、顎の成長がまだ残っているケースが多く、その成長を利用することで効率的に治療を進められる可能性があります。また、新陳代謝が活発なため、歯が動きやすく、大人と比べて治療期間が短くなる傾向が見られることもあります。ただし、抜歯が必要な場合や、骨格的な問題が大きい場合は、期間が長くなることもあります。
動的治療期間が終了した後には、歯並びが元の位置に戻ろうとする「後戻り」を防ぐために、保定装置(リテーナー)を使用する「保定期間」が必要です。この保定期間も、動的治療期間と同じくらいか、それ以上の期間(最低2~3年、場合によっては長期的に)必要になることが一般的です。トータルの治療期間としては、動的治療期間と保定期間を合わせたものになります。
通院頻度は、治療段階や方法によって異なりますが、動的治療期間中は月に1回程度、保定期間中は数ヶ月に1回程度が目安となります。部活動や学業との両立も考慮し、無理なく通院できる計画を立てることが大切です。正確な治療期間については、精密検査の結果をもとに、担当の歯科医師とよく相談して確認しましょう。
5.2 矯正治療にかかる費用の相場
矯正歯科治療は、一部の先天的な疾患や外科手術を伴う顎変形症などを除き、基本的に健康保険が適用されない自由診療(自費診療)となります。そのため、治療費は全額自己負担となり、比較的高額になる傾向があります。費用は、治療の難易度、選択する装置の種類、治療期間、そして各歯科医院の料金設定によって大きく異なります。
以下に、主な矯正装置の種類別の費用相場(総額)を示しますが、あくまで目安として参考にしてください。地域や医院によって差がありますので、必ず事前に確認が必要です。
| 矯正装置の種類 | 特徴 | 費用相場(総額) |
|---|---|---|
| ワイヤー矯正(表側) | 歯の表面にブラケットとワイヤーを装着する最も一般的な方法。金属製やセラミック製など素材を選べる。 | 約70万円~110万円 |
| ワイヤー矯正(裏側・舌側) | 歯の裏側に装置を装着するため、外からは見えにくい。 | 約100万円~150万円 |
| マウスピース矯正(インビザラインなど) | 透明なマウスピースを段階的に交換して歯を動かす。取り外し可能。 | 約80万円~120万円 |
上記の費用には、通常、初診相談料、精密検査・診断料、矯正装置料、毎月の調整料(処置料)、保定装置料などが含まれますが、料金体系は歯科医院によって異なります。「トータルフィーシステム(治療完了までの総額を最初に提示する方式)」を採用している医院もあれば、調整料などが別途かかる場合もあります。契約前に、費用総額と内訳、追加費用が発生する可能性について、しっかりと確認することが重要です。
支払い方法についても、一括払いの他に、分割払いやデンタルローンを利用できる場合がありますので、相談してみましょう。また、矯正治療費は医療費控除の対象となる場合があります。確定申告を行うことで、所得税や住民税の還付・減額を受けられる可能性がありますので、領収書は大切に保管し、税務署や税理士に確認することをおすすめします。
5.3 矯正治療中の痛みはどの程度?
矯正治療というと「痛い」というイメージを持つ方もいるかもしれませんが、痛みの感じ方には個人差が大きく、全く痛みを感じない人もいれば、強く感じる人もいます。一般的に、痛みを感じやすいのは、矯正装置を初めて装着した時や、ワイヤーを調整した後の数日間です。これは、歯が動き始める際に歯根膜(歯と骨の間にある組織)が圧迫されるために起こる痛みで、「歯が浮くような感じ」「噛むと痛い」といった感覚が多いようです。
この痛みは、通常、2~3日から長くても1週間程度で徐々に和らいでいくことがほとんどです。中学生や高校生は、大人に比べて組織の反応が良く、適応力も高い傾向があるため、比較的痛みに慣れるのが早いとも言われています。
痛みが辛い場合は、以下のような対処法があります。
- 歯科医師に相談の上、市販の痛み止め(鎮痛剤)を服用する。
- 治療開始直後や調整後は、おかゆやうどん、スープ、ヨーグルトなど、あまり噛まなくても食べられる柔らかい食事をとる。
- 装置が唇や頬の内側の粘膜に当たって痛む場合は、歯科医院で渡される矯正用ワックスを装置に貼り付けてカバーする。
- 口内炎ができてしまった場合は、軟膏を塗布したり、刺激の少ない食事を心がける。
痛みが長期間続く場合や、我慢できないほど強い場合は、何か問題が起きている可能性もありますので、遠慮せずに早めに歯科医院に連絡し、相談するようにしましょう。
5.4 矯正装置装着中の食事と歯磨きの注意点
矯正装置を装着している期間は、虫歯や歯周病のリスクが高まるため、食事と歯磨き(口腔ケア)に特に注意が必要です。装置の種類によっても注意点が異なります。
5.4.1 食事で気をつけること
ワイヤー矯正(表側・裏側)の場合、装置が固定式で取り外せないため、食事の際に特に注意が必要です。以下のような食べ物は、装置の破損や脱落、虫歯の原因になりやすいため、避けるか、食べ方を工夫するようにしましょう。
- 硬い食べ物:せんべい、ナッツ類、氷、骨付き肉、りんごや人参の丸かじりなど。装置が壊れたり外れたりする原因になります。小さく切ってから奥歯でゆっくり噛むようにしましょう。
- 粘着性の高い食べ物:キャラメル、ガム、餅、ソフトキャンディなど。装置にくっつきやすく、取り除くのが困難で、虫歯のリスクを高めます。また、装置が外れる原因にもなります。
- 繊維質の多い食べ物:ほうれん草やえのきなどの葉物野菜、細い麺類など。装置の隙間やワイヤーに絡まりやすく、歯磨きで取り除くのが大変です。細かく切って食べるなどの工夫が必要です。
- 色素の濃い食べ物:カレー、ミートソース、コーヒー、紅茶、赤ワインなど。特にセラミックブラケットやマウスピースの場合、着色の原因になることがあります。摂取後は早めに歯磨きやうがいをしましょう。
一方、マウスピース矯正(インビザラインなど)の場合は、食事の際に装置を取り外すことができるため、基本的に食べ物の制限はありません。ただし、装着したまま糖分の入った飲み物を飲むのは避け、食事の後は必ず歯磨きをしてからマウスピースを再装着する必要があります。
外食時も、メニュー選びや食べ方に注意し、食後は可能な限り早く歯磨きやうがいをする習慣をつけましょう。
5.4.2 歯磨き(口腔ケア)の重要性と方法
矯正装置の周りは、食べ物のカスや歯垢(プラーク)が非常に溜まりやすく、清掃が不十分だと虫歯や歯肉炎(歯周病の初期段階)のリスクが格段に高まります。矯正治療を成功させるためには、毎日の丁寧な口腔ケアが不可欠です。
ワイヤー矯正の場合、装置の周りやワイヤーの下など、磨きにくい部分が多くなります。以下の点を意識して、時間をかけて丁寧に磨きましょう。
- 毎食後と就寝前の歯磨きを徹底する。
- 歯ブラシは、ヘッドが小さく毛先が細いものや、矯正用の山型カットの歯ブラシなどが磨きやすい。
- 歯ブラシだけでなく、歯間ブラシ、タフトブラシ(ワンタフトブラシ)、デンタルフロス(フロススレッダーを使うと便利)などの補助清掃用具を必ず併用し、装置の周りや歯と歯の間、ワイヤーの下などを丁寧に清掃する。
- フッ素入りの歯磨き粉や、殺菌効果のある洗口液(マウスウォッシュ)を使用するのも効果的。
- 鏡を見ながら、磨き残しがないか確認する習慣をつける。
- 定期的な歯科医院でのプロフェッショナルケア(クリーニング、PMTC)も重要。
マウスピース矯正の場合も、装置を外して歯磨きができますが、油断は禁物です。歯磨きが不十分なままマウスピースを装着すると、汚れが歯の表面に密閉され、虫歯や歯周病のリスクが高まります。食後は必ず丁寧に歯を磨き、マウスピース自体も専用の洗浄剤やブラシを使って清潔に保ちましょう。
正しい歯磨き方法については、歯科医院で指導を受け、しっかりと身につけることが大切です。
5.5 信頼できる矯正歯科の選び方
矯正治療は長期間にわたるため、技術力はもちろん、コミュニケーションが取りやすく、安心して任せられる歯科医院を選ぶことが非常に重要です。特に、多感な時期である中学生・高校生の治療においては、精神的なサポートも考慮したい点です。以下のポイントを参考に、慎重に選びましょう。
5.5.1 認定医・専門医の資格を確認する
矯正歯科治療は専門性の高い分野です。日本矯正歯科学会などの学会が認定する「認定医」や「専門医」の資格を持つ歯科医師は、一定レベル以上の知識、技術、経験を有していると考えられます。資格の有無は、歯科医院を選ぶ上での一つの目安となります。ホームページや院内掲示などで確認してみましょう。
5.5.2 カウンセリングの丁寧さで判断する
最初のカウンセリング(相談)は非常に重要です。以下の点を確認しましょう。
- 患者さん(中高生本人)や保護者の悩み、希望、疑問点を親身になって聞いてくれるか。
- 精密検査の結果に基づき、現在の歯並びや顎の状態、考えられる治療方針、それぞれのメリット・デメリット、治療期間、費用、起こりうるリスクや副作用について、専門用語ばかりでなく、分かりやすい言葉で丁寧に説明してくれるか。
- 一方的に治療法を押し付けるのではなく、複数の選択肢を提示し、一緒に考えてくれる姿勢があるか。
- 質問しやすい雰囲気があり、納得できるまで説明してくれるか。
コミュニケーションが円滑にとれ、信頼関係を築けそうだと感じられるかどうかが、大切なポイントです。
5.5.3 治療実績や症例を確認する
その歯科医院が、これまでにどのような矯正治療を行ってきたか、治療実績や症例写真などを確認することも参考になります。特に、自分と似たような歯並びの症例や、中学生・高校生の治療経験が豊富かどうかをチェックしてみましょう。ホームページやブログ、院内での掲示などで公開されている場合があります。
5.5.4 設備や衛生管理が整っているか
正確な診断と安全な治療のためには、設備が整っていることも重要です。頭部X線規格写真(セファロレントゲン)など、矯正診断に必要な精密検査機器が導入されているか確認しましょう。また、院内が清潔に保たれており、器具の滅菌・消毒などの衛生管理が徹底されているかもチェックポイントです。
5.5.5 通いやすさも考慮する
矯正治療は、動的治療期間中には月1回程度、その後も保定期間のチェックなどで、数年間にわたって定期的に通院する必要があります。そのため、学校帰りや自宅から無理なく通える立地であることは非常に重要です。また、診療時間や曜日が、学業や部活動などのライフスタイルと合っているか、予約が取りやすいかなども確認しておきましょう。
5.5.6 費用体系が明確であること
前述の通り、矯正治療は高額になるため、費用体系が明確であることは必須条件です。治療開始前に、検査・診断料から装置料、調整料、保定装置料まで含めた総額がいくらになるのか、明確に提示してくれるかを確認しましょう。トータルフィーシステム(総額固定制)を採用している医院は、後から追加費用が発生する心配が少ないため安心です。もし調整料などが別途かかる場合は、その金額や支払い頻度、総額の見込みなどをしっかり確認し、書面で提示してもらうようにしましょう。
いくつかの歯科医院でカウンセリングを受け、比較検討することも有効です。焦らず、自分(またはお子さん)にとって最適な歯科医院を見つけることが、満足のいく矯正治療への第一歩となります。
6. まとめ
中学生・高校生のうちに矯正歯科を始めることは、見た目の改善による自信向上はもちろん、顎の成長を利用した効率的な治療や、将来的な虫歯・歯周病リスクの低減など、多くのメリットが期待できます。治療期間も大人に比べて短くなる傾向があります。最適な開始時期は個人差があるため、まずは矯正歯科の専門医に相談し、検査を受けることが重要です。ワイヤー矯正やマウスピース矯正など、ご自身に合った方法を選び、健やかな口元と自信を手に入れましょう。
矯正治療のご相談をご希望の方は、下記のボタンよりお気軽にご予約ください。
この記事の監修者

尾立 卓弥(おだち たくや)
医療法人札幌矯正歯科 理事長
宮の沢エミル矯正歯科 院長
北海道札幌市の矯正専門クリニック「宮の沢エミル矯正歯科」院長。
日本矯正歯科学会 認定医。