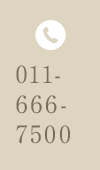歯を削る矯正って大丈夫?リスクとメリット、削らない矯正との違いを徹底解説

こんにちは。医療法人 札幌矯正歯科 宮の沢エミル矯正歯科の理事長の尾立卓弥です。札幌で矯正歯科を検討中の方は、ぜひ医療法人 札幌矯正歯科 宮の沢エミル矯正歯科でご相談ください。「矯正で歯を削るって大丈夫なの?」と不安に思っていませんか?歯を削る矯正治療は、歯並びを整えるための有効な手段ですが、メリットだけでなくデメリットやリスクも存在します。この記事では、歯を削る矯正のメカニズムや種類(IPR、エナメルストリッピングなど)、メリット・デメリット、削らない矯正との違い、費用、矯正歯科医の選び方まで、詳しく解説します。歯を削る矯正治療を受けるべきか、それとも削らない矯正治療を選択すべきか、この記事を読めば、ご自身の歯並びや治療への希望に合った最適な矯正方法を見つけるための判断材料が得られます。疑問や不安を解消し、自信を持って矯正治療を始められるよう、徹底的にサポートします。
1. 歯を削る矯正とは?
歯を削る矯正とは、歯と歯の間のエナメル質を少量削ることで、歯を動かすスペースを作り、歯並びを整える矯正治療法です。歯の表面をわずかに削ることで、歯列の幅を広げ、歯の移動をスムーズにすることを目的としています。この処置は、歯列矯正において補助的な役割を果たし、すべての症例に適用されるわけではありません。主に、軽度の叢生(歯が重なっている状態)や歯列の幅が狭い場合に用いられます。削る量は非常にわずかで、歯の神経に影響を与えることはありません。しかし、歯を削るという処置は不可逆的なものであるため、矯正歯科医との綿密な相談と診断が不可欠です。
1.1 歯を削る矯正のメカニズム
歯を削る矯正のメカニズムは、歯と歯の間のエナメル質を少量削り、歯を動かすスペースを確保することにあります。エナメル質は歯の表面を覆う硬い組織で、人体で最も硬い組織の一つです。このエナメル質を少量削ることで、歯列にわずかな隙間を作り、歯を移動しやすくします。削る量は、歯の状態や治療計画によって異なりますが、通常は0.1mm~0.8mm程度と非常に微量です。この処置により、歯を抜歯せずに矯正治療を行うことが可能になる場合もあります。
1.2 どんな人が歯を削る矯正の対象になるの?
歯を削る矯正は、すべての人に適応されるわけではありません。軽度の叢生や歯列の幅が狭いなど、限られたケースで有効な治療法です。具体的には、以下のような人が対象となります。
| 対象となるケース | 説明 |
|---|---|
| 軽度の叢生 | 歯が少し重なっている程度の軽度の叢生の場合、歯を削ることで歯並びを整えるスペースを作り出すことができます。 |
| 歯列の幅が狭い | 歯列の幅が狭く、歯が並ぶスペースが不足している場合、歯を削ることでスペースを確保し、歯並びを整えることができます。 |
| すきっ歯を改善したい場合 | すきっ歯を改善するために、隣の歯を少し削って、人工歯を装着するスペースを作る場合があります。 |
| 非抜歯矯正を希望する場合 | 歯を抜かずに矯正治療を行いたい場合、歯を削ることでスペースを確保し、非抜歯矯正を可能にする場合があります。 |
ただし、重度の叢生や顎の骨格に問題がある場合、歯を削るだけでは矯正治療が難しいため、他の矯正方法が検討されます。また、エナメル質が薄い、虫歯が多い、歯周病があるなどの場合は、歯を削る矯正が適さないこともあります。矯正治療を受ける際には、矯正歯科医に自分の歯の状態や希望を伝え、適切な治療法を選択することが重要です。
2. 歯を削る矯正のメリット
歯を削る矯正には、歯を削らない矯正治療と比較していくつかのメリットがあります。主なメリットとして、歯の移動距離の減少、治療期間の短縮の可能性、抜歯の可能性の低下が挙げられます。これらのメリットが、治療を受ける患者さんにとってどのような利点となるのか、詳しく見ていきましょう。
2.1 歯の移動距離が少なくて済む
歯を削る矯正では、歯と歯の間のエナメル質をわずかに削ることで、歯を動かすスペースを作り出します。これにより、歯を大きく移動させる必要がなくなり、結果として治療中の歯の負担を軽減できます。歯を削らない矯正では、歯を動かすスペースを確保するために、歯を大きく移動させる必要が生じるケースがあり、治療期間が長引いたり、歯根吸収のリスクが高まったりする可能性があります。歯を削る矯正は、これらのリスクを軽減するのに役立ちます。
2.2 治療期間が短縮できる場合も
歯の移動距離が少なくて済むということは、場合によっては治療期間の短縮にも繋がります。歯を大きく動かす必要がないため、治療期間が短くなる可能性があります。ただし、治療期間は個々の歯並びの状態や治療計画によって異なるため、必ずしも短くなるとは限りません。治療期間については、担当の矯正歯科医とよく相談することが重要です。
2.3 抜歯の可能性が低くなる
歯列矯正において、歯を抜くことは患者さんにとって大きな負担となります。歯を削る矯正は、歯を動かすスペースを確保しやすいため、抜歯を回避できる可能性が高まります。抜歯が必要なケースでも、削る量を調整することで、抜歯する本数を減らせる可能性があります。抜歯を避けたい方にとっては、大きなメリットと言えるでしょう。
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 歯の移動距離の減少 | 歯を削ることで歯を動かすスペースを作り、移動距離を少なくします。 |
| 治療期間の短縮の可能性 | 移動距離が少なくなることで、治療期間が短縮される場合があります。 |
| 抜歯の可能性の低下 | 歯を動かすスペースを確保しやすいため、抜歯の可能性を低減できます。 |
これらのメリットは、あくまで一般的なものであり、すべての人に当てはまるわけではありません。歯を削る矯正が適しているかどうかは、個々の歯並びの状態や治療方針によって異なります。矯正治療を検討する際には、複数の矯正歯科医に相談し、それぞれのメリット・デメリットを比較検討することが重要です。それぞれの治療法の特徴を理解し、自身に最適な治療法を選択しましょう。
3. 歯を削る矯正のデメリット・リスク
歯を削る矯正治療は、歯並びを改善する上でメリットがある一方で、いくつかのデメリットやリスクも存在します。治療を受ける前に、これらのデメリットやリスクをしっかりと理解しておくことが重要です。メリットばかりに目を奪われず、慎重に検討しましょう。
3.1 歯が弱くなる可能性がある
歯を削るということは、歯のエナメル質を薄くすることを意味します。エナメル質は歯の表面を覆う硬い組織で、歯を外部の刺激から守る役割を担っています。エナメル質が薄くなると、歯の強度が低下し、虫歯や知覚過敏になりやすくなるリスクがあります。また、歯が欠けたり、摩耗しやすくなったりする可能性も高まります。
3.2 知覚過敏になるリスク
歯を削ることで、エナメル質が薄くなり、象牙質が露出する面積が増えます。象牙質には神経が通っているため、冷たいものや熱いもの、甘いもの、酸っぱいものなどの刺激に敏感に反応し、痛みを感じやすくなることがあります。この症状は知覚過敏と呼ばれ、日常生活に支障をきたす場合もあります。知覚過敏の程度は個人差があり、一時的な場合もあれば、長期間続く場合もあります。
3.3 歯を削る量は元に戻せない
歯を削る処置は不可逆的なものです。一度削ってしまった歯は、二度と元には戻りません。そのため、治療を受ける前に、将来的なリスクも考慮し、慎重に判断する必要があります。削る量によっては、後々、被せ物や詰め物が必要になるケースも考えられます。
3.4 歯の形態が変わってしまう
IPRなどの歯を削る矯正治療では、歯の側面をわずかに削ることで歯の幅を狭くし、歯並びを整えます。しかし、削り方によっては、歯の形が不自然に見えてしまう可能性があります。特に、前歯など目立つ部分の歯を削る場合は、審美的な影響も考慮する必要があります。熟練した矯正歯科医であれば、自然な仕上がりになるように配慮してくれますが、技術力不足の歯科医に治療を受けると、歯の形が不均一になったり、歯と歯の間に隙間ができたりするリスクがあります。
3.5 隣接面う蝕のリスク増加
歯と歯の間を狭くすることで、歯ブラシが届きにくくなり、隣接面う蝕(歯と歯の間の虫歯)のリスクが高まる可能性があります。歯を削る矯正治療を受けた後は、デンタルフロスや歯間ブラシなどを用いて、丁寧に歯磨きをすることが重要です。適切なセルフケアを行わないと、虫歯のリスクが高まり、将来的に歯を失う可能性も否定できません。
3.6 後戻りの可能性
歯を削る矯正治療は、歯を移動させるスペースを作ることで歯並びを整えますが、他の矯正治療と同様に、後戻りの可能性はゼロではありません。保定期間中に適切な保定装置を使用しないと、歯が元の位置に戻ってしまう可能性があります。後戻りを防ぐためには、矯正歯科医の指示に従い、決められた期間、保定装置をきちんと装着することが重要です。
| デメリット・リスク | 詳細 |
|---|---|
| 歯の強度低下 | エナメル質が薄くなり、虫歯や知覚過敏、破折のリスクが高まる |
| 知覚過敏 | 象牙質の露出により、冷たいものや熱いものへの刺激に敏感になる |
| 不可逆的な処置 | 一度削った歯は元に戻らない |
| 歯の形態変化 | 削り方によっては、歯の形が不自然に見える可能性がある |
| 隣接面う蝕リスク増加 | 歯と歯の間が狭くなり、歯ブラシが届きにくくなる |
| 後戻りの可能性 | 保定期間中に適切な保定装置を使用しないと、歯が元の位置に戻ってしまう |
上記以外にも、歯茎の退縮や歯根吸収といったリスクも稀に存在します。これらのリスクを最小限に抑えるためには、経験豊富で技術力の高い矯正歯科医を選ぶことが大切です。治療を受ける前に、しっかりとカウンセリングを受け、疑問点や不安な点を解消しておきましょう。
4. 歯を削る矯正の種類
歯を削る矯正治療には、主にIPRとエナメルストリッピングという2つの種類があります。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
4.1 IPR(インタープロキシマル・リダクション)
IPR(インタープロキシマル・リダクション)は、歯と歯の間のエナメル質を少量削ることで、歯列にわずかな隙間を作り、歯を移動させるスペースを確保する治療法です。歯を全体的にわずかに削るため、歯並びの微調整に用いられます。
IPRで削る量は、1本あたり0.1~0.5mm程度と非常に微量です。専用の器具を用いて行われ、熟練した歯科医師であれば安全に施術を受けることができます。
4.1.1 IPRのメリット
- 歯の移動スペースを確保できる
- 抜歯の可能性を低減できる
- 治療期間の短縮につながる場合がある
4.1.2 IPRのデメリット・リスク
- 知覚過敏のリスクがある(ごく稀なケース)
- 歯が弱くなる可能性がある(ごく稀なケース)
4.1.3 IPRが適しているケース
- 軽度の叢生(歯の重なり)
- わずかな隙間を閉じたい場合
- 歯列全体の幅を狭めたい場合
4.2 エナメルストリッピング
エナメルストリッピングは、歯の側面のエナメル質を少量削ることで、歯の幅を狭くし、歯並びを整える方法です。IPRよりも削る量は若干多く、歯の形を調整する目的でも用いられます。
エナメルストリッピングも専用の器具を用いて行われ、削る量は1本あたり0.2~0.7mm程度です。歯の表面のエナメル質のみを削るため、神経に影響を与えることはありません。
4.2.1 エナメルストリッピングのメリット
- 歯の幅を調整できる
- 歯の形を整えることができる
- すきっ歯を改善できる
4.2.2 エナメルストリッピングのデメリット・リスク
- 知覚過敏のリスクがある(ごく稀なケース)
- 歯が弱くなる可能性がある(ごく稀なケース)
4.2.3 エナメルストリッピングが適しているケース
- 歯の幅が広い
- 歯の形が不揃い
- 軽度のすきっ歯
4.3 IPRとエナメルストリッピングの比較
| 項目 | IPR | エナメルストリッピング |
|---|---|---|
| 削る部位 | 歯と歯の間 | 歯の側面 |
| 削る量 | 0.1~0.5mm程度 | 0.2~0.7mm程度 |
| 主な目的 | 歯の移動スペースの確保 | 歯の幅や形の調整 |
どちらの方法も、歯を削る量はとても微量であり、健康な歯を維持するために必要なエナメル質の範囲内で行われます。 施術を受ける際は、歯科医師としっかり相談し、自分の歯の状態に合った方法を選択することが重要です。また、施術後のケアについても、歯科医師の指示に従うようにしましょう。
5. 歯を削らない矯正治療の種類
歯を削らない矯正治療には、大きく分けてワイヤー矯正とマウスピース矯正の2種類があります。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
5.1 ワイヤー矯正
ワイヤー矯正は、歯の表面にブラケットと呼ばれる装置を接着し、そこにワイヤーを通して歯を動かしていく方法です。歴史が長く、様々な症例に対応できることが特徴です。
5.1.1 ワイヤー矯正の種類
| 種類 | 説明 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| メタルブラケット | 金属製のブラケットを使用する方法。 | 費用が比較的安価。耐久性が高い。 | 審美性に劣る。 |
| セラミックブラケット | 歯の色に近いセラミック製のブラケットを使用する方法。 | 審美性に優れる。 | メタルブラケットよりも費用が高価。 |
| セルフライゲーションブラケット | ワイヤーとブラケットの摩擦を軽減する仕組みを持つブラケットを使用する方法。 | 痛みが少ない。治療期間が短縮できる場合もある。 | 従来のブラケットよりも費用が高価。 |
| リンガルブラケット | 歯の裏側にブラケットを装着する方法。 | 表からは見えないため審美性に非常に優れる。 | 費用が高価。発音に影響が出ることがある。舌に違和感を感じやすい。 |
5.1.2 ワイヤー矯正のメリット・デメリット
ワイヤー矯正は、複雑な歯列不正にも対応できる点が最大のメリットです。また、治療費用がマウスピース矯正に比べて比較的安価な場合が多いこともメリットと言えるでしょう。一方で、装置が目立ちやすいこと、食事や歯磨きの際に不便さを感じることなどがデメリットとして挙げられます。
5.2 マウスピース矯正(インビザラインなど)
マウスピース矯正は、透明なマウスピース型の装置を装着することで歯を動かしていく方法です。取り外しが可能なため、食事や歯磨きの際に不便を感じにくいことが特徴です。代表的なマウスピース矯正として、インビザラインがあります。その他にもアソアライナー、クリアコレクトなど様々な種類があります。
5.2.1 マウスピース矯正の種類
マウスピース矯正は、様々なメーカーから提供されています。代表的なものとしては、インビザライン、アソアライナー、クリアコレクトなどが挙げられます。それぞれ材質や価格、適用できる症例などが異なります。
| メーカー | 特徴 |
|---|---|
| インビザライン | 世界的に有名なマウスピース矯正ブランド。多くの症例に対応可能。 |
| アソアライナー | 国産のマウスピース矯正ブランド。比較的安価な価格設定。 |
| クリアコレクト | 軽度の歯列不正に特化したマウスピース矯正ブランド。短期間での治療が可能。 |
5.2.2 マウスピース矯正のメリット・デメリット
マウスピース矯正の最大のメリットは、透明なマウスピースを使用するため、装置が目立ちにくい点です。また、取り外しが可能なため、食事や歯磨きの際に不便を感じにくいこともメリットです。一方で、マウスピースの装着時間をきちんと守らないと治療効果が得られないこと、複雑な歯列不正には対応できない場合があること、ワイヤー矯正に比べて費用が高価な場合が多いことなどがデメリットとして挙げられます。
それぞれの矯正方法にはメリット・デメリットがあります。ご自身の歯並びの状態やライフスタイル、予算などを考慮して、最適な方法を選択することが重要です。矯正歯科医とよく相談し、納得のいく治療方法を選びましょう。
6. 歯を削る矯正と歯を削らない矯正、どっちが自分に合ってる?
歯列矯正を検討する上で、歯を削る方法と削らない方法、どちらが自分に適しているのかは大きな悩みどころです。この章では、歯並びの状態、治療期間、費用、審美性といった観点から、それぞれの矯正方法の特徴を比較し、最適な選択をするためのポイントを解説します。
6.1 歯並びの状態
軽度の叢生(歯の crowding )や隙間を閉じたい場合、IPRなどの歯を削る矯正で対応できる可能性があります。一方、顕著な出っ歯や受け口、大きな歯列不正、顎の骨格的な問題がある場合は、歯を削るだけでは改善が難しく、ワイヤー矯正やマウスピース矯正などの歯を削らない矯正治療が必要となるでしょう。
6.2 治療期間
歯を削る矯正は、歯の移動距離が少なくて済むため、症例によっては歯を削らない矯正よりも治療期間が短縮できる可能性があります。しかし、歯を削る矯正も歯を削らない矯正も、治療期間は個々の歯並びの状態や治療計画によって大きく変わるため、一概にどちらが短期間で終わるとは言えません。矯正歯科医との綿密な相談が重要です。
6.3 費用
一般的に、IPR単独で行う矯正治療は、ワイヤー矯正やマウスピース矯正といった包括的な治療に比べて費用が抑えられる傾向があります。しかし、IPRを併用した矯正治療の場合、全体の治療費はワイヤー矯正やマウスピース矯正と同程度、もしくは場合によっては高くなることもあります。また、使用する装置の種類や治療期間によっても費用は変動します。具体的な費用は、必ず矯正歯科医に見積もりを依頼しましょう。
6.4 審美性
歯を削る矯正は、歯の表面をわずかに削るため、歯の形や大きさが変化する可能性は低いですが、場合によっては歯と歯の間に隙間が生じるリスクもゼロではありません。一方、ワイヤー矯正は金属製のブラケットが目立つことがありますが、近年では白いセラミックブラケットやマウスピース矯正(インビザラインなど)といった審美性に優れた矯正装置も普及しています。それぞれの矯正方法のメリット・デメリットを理解し、自身の希望に合った方法を選択することが大切です。
| 項目 | 歯を削る矯正 | 歯を削らない矯正 |
|---|---|---|
| 適応症例 | 軽度の叢生、隙間 | 出っ歯、受け口、叢生、顎の骨格的な問題 |
| 治療期間 | 症例によっては短縮できる可能性あり | 症例による |
| 費用 | IPR単独では比較的安価な傾向 | 装置や治療期間による |
| 審美性 | 歯の形や大きさはほぼ変化なし | 装置の種類による(審美ブラケット、マウスピース型など) |
最終的には、ご自身の歯並びの状態や治療に対する希望、予算などを考慮し、経験豊富な矯正歯科医と十分に相談した上で、最適な矯正方法を選択することが重要です。複数の矯正歯科医院で相談し、セカンドオピニオンを求めることも有効な手段です。
7. 歯を削る矯正に関するよくある質問
歯を削る矯正治療に関する、よくある質問をまとめました。治療を受ける前に疑問や不安を解消しましょう。
7.1 歯を削る矯正は痛みがある?
歯を削る処置自体は、麻酔を使用するため痛みはほとんどありません。麻酔が切れた後、一時的に軽い痛みやしみるような感覚が出る場合がありますが、通常は数日で治まります。ただし、痛みには個人差がありますので、不安な場合は担当医に相談しましょう。
7.2 歯を削る矯正後のケアはどうすればいい?
歯を削る矯正後は、虫歯や知覚過敏のリスクが高まるため、丁寧なケアが必要です。毎食後の歯磨きはもちろん、歯間ブラシやデンタルフロスも使用し、歯垢を徹底的に除去しましょう。フッ素配合の歯磨き粉を使用することも効果的です。また、定期的な歯科検診も重要です。担当医の指示に従い、適切なケアを心がけましょう。
7.3 歯を削る矯正の費用はどのくらい?
歯を削る矯正の費用は、削る量や範囲、使用する装置、矯正全体にかかる費用などによって大きく異なります。IPRのみを行う場合は数千円〜数万円程度ですが、矯正治療全体で考えると、数百万円かかる場合もあります。費用については、事前にしっかりと確認し、納得した上で治療を始めましょう。具体的な費用は、各クリニックによって異なりますので、複数のクリニックで相談してみることをおすすめします。
7.4 歯を削る矯正で歯が欠けることはある?
適切な処置を行えば、歯が欠けることはほとんどありません。しかし、極端に歯を削りすぎたり、強い力が加わったりすると、歯が欠けるリスクが高まります。信頼できる歯科医師のもとで治療を受けることが大切です。
7.5 歯を削る矯正は後戻りする?
歯を削る矯正自体は後戻りするものではありませんが、矯正治療全体としては後戻りの可能性があります。後戻りを防ぐためには、保定装置の使用や定期的な検診が重要です。担当医の指示に従い、適切なケアを継続しましょう。
7.6 どんな矯正歯科医を選べばいい?
歯を削る矯正治療は、高度な技術と経験が必要です。日本矯正歯科学会の認定医や専門医など、矯正治療の専門知識と豊富な経験を持つ歯科医師を選ぶことが重要です。また、治療方法や費用について、丁寧に説明してくれる歯科医師を選びましょう。セカンドオピニオンを求めることも有効です。
7.7 歯を削る矯正とラミネートベニアの違いは?
どちらも歯の形を整える治療ですが、目的が異なります。歯を削る矯正は、歯並びを整えることが目的です。一方、ラミネートベニアは、歯の色や形を改善し、審美性を向上させることが目的です。場合によっては、両方の治療を併用することもあります。
7.8 IPRとエナメルストリッピングの違いは?
| 項目 | IPR(インタープロキシマル・リダクション) | エナメルストリッピング |
|---|---|---|
| 削る部分 | 歯と歯の間の側面 | 歯の表面のエナメル質 |
| 削る量 | 少量(0.1mm~0.5mm程度) | 少量(0.1mm~0.8mm程度) |
| 目的 | 歯と歯の隙間を作ることで、歯の配列を整える | 歯の表面の凹凸を滑らかにし、歯並びを整える、またはラミネートベニアなどの装着スペースを作る |
どちらも歯を少量削る処置ですが、削る部分と目的が異なります。
7.9 マウスピース矯正とワイヤー矯正で歯を削ることはある?
マウスピース矯正とワイヤー矯正のどちらの場合でも、歯を削る処置(IPRなど)を併用することがあります。歯並びの状態によっては、歯を削ることで治療効果を高めたり、治療期間を短縮したりできる場合があります。担当医とよく相談し、最適な治療方法を選択しましょう。
8. 矯正歯科医の選び方
矯正治療は、歯並びだけでなく、顔全体の印象や健康にも大きく影響する重要な治療です。そのため、矯正歯科医選びは慎重に行う必要があります。信頼できる矯正歯科医を見つけるためのポイントを詳しく解説します。
8.1 専門性と資格
矯正治療は高度な専門知識と技術を要します。日本矯正歯科学会の認定医や専門医の資格を持つ歯科医師は、一定水準以上の知識と経験を有していると考えられます。これらの資格は、矯正治療に関する豊富な知識と臨床経験を持つ証です。学会のウェブサイトで認定医・専門医を検索できます。
8.2 治療方針・説明の丁寧さ
矯正治療には様々な方法があり、患者さんの歯並びやライフスタイル、予算に合わせて最適な治療法を選択する必要があります。治療方法のメリット・デメリット、費用、期間などを丁寧に説明してくれるかどうかは重要なポイントです。セカンドオピニオンを求めることも有効です。複数の歯科医師の意見を聞くことで、より自分に合った治療法を見つけることができます。
8.3 設備・技術
最新の設備や技術を導入しているクリニックでは、より精密な診断と治療が可能です。3DスキャナーやCTなどの設備が導入されているか、デジタル技術を活用した治療を行っているかなどを確認しましょう。また、矯正治療に特化したクリニックでは、より専門性の高い治療を受けることができます。
8.4 通いやすさ
矯正治療は、数ヶ月から数年単位の長期にわたる治療となるため、通いやすい場所にあるクリニックを選ぶことが重要です。自宅や職場からのアクセス、診療時間なども考慮しましょう。治療期間中は定期的に通院する必要があるため、通院しやすいクリニックを選ぶことで、治療をスムーズに進めることができます。
8.5 費用
矯正治療の費用は、治療方法や期間、使用する装置などによって大きく異なります。費用体系が明確で、追加費用が発生する場合は事前に説明してくれるクリニックを選びましょう。また、医療費控除やデンタルローンなどの制度についても確認しておくと良いでしょう。当院の費用に関しては、料金表をご覧ください。
8.6 口コミ・評判
インターネット上の口コミや評判も参考になります。ただし、口コミはあくまでも個人の感想であるため、参考程度に留め、最終的には自分でクリニックを訪れて判断することが大切です。実際にクリニックの雰囲気やスタッフの対応などを確認することで、自分に合ったクリニックかどうかを判断できます。
8.7 衛生管理
院内の清潔さや衛生管理も重要なポイントです。感染症対策が適切に行われているかを確認しましょう。清潔な環境で治療を受けることは、安心して治療を受けるために不可欠です。
8.8 緊急時の対応
矯正装置が外れた、ワイヤーが刺さって痛いなどのトラブルが発生した場合の対応についても確認しておきましょう。緊急時の連絡先や対応体制が明確になっているクリニックを選ぶと安心です。
8.9 クリニック選びのチェックポイント
| 項目 | 確認事項 |
|---|---|
| 専門性 | 日本矯正歯科学会の認定医・専門医、豊富な経験 |
| 説明 | 丁寧な説明、メリット・デメリット、費用、期間、セカンドオピニオン |
| 設備 | 3Dスキャナー、CT、デジタル技術 |
| 通いやすさ | アクセス、診療時間 |
| 費用 | 明確な費用体系、追加費用、医療費控除、デンタルローン |
| 口コミ | 参考程度、最終的には自分で判断 |
| 衛生管理 | 清潔さ、感染症対策 |
| 緊急時対応 | 連絡先、対応体制 |
これらのポイントを参考に、信頼できる矯正歯科医を見つけて、理想の歯並びを手に入れましょう。
9. まとめ
歯を削る矯正治療は、IPRやエナメルストリッピングといった方法で歯の幅を狭め、歯並びを整える治療法です。治療期間の短縮や抜歯回避の可能性を高めるメリットがある一方、歯が弱くなる、知覚過敏になるといったリスクも存在します。ワイヤー矯正やマウスピース矯正といった歯を削らない矯正治療も選択肢としてあります。
どの矯正方法が最適かは、歯並びの状態や治療期間、費用、審美性など、個々の状況によって異なります。矯正治療を検討する際は、メリット・デメリットを理解した上で、信頼できる矯正歯科医に相談し、自分に合った治療法を選択することが重要です。
この記事の監修者

尾立 卓弥(おだち たくや)
医療法人札幌矯正歯科 理事長
宮の沢エミル矯正歯科 院長
北海道札幌市の矯正専門クリニック「宮の沢エミル矯正歯科」院長。
日本矯正歯科学会 認定医。わかりやすく丁寧なカウンセリングと、審美・機能性を両立した治療に定評があります。